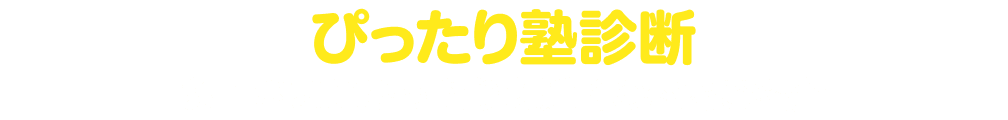大学受験に向けて塾を検討しはじめ、どのくらい費用がかかるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
塾は「費用が高いほどよい」というわけではないため、適切な料金を見極めつつ、子どもの性格や目的にあった塾を選ぶことが大切です。
この記事では、大学受験のために通塾にかかる年間費用の相場やその内訳、塾代を安く抑えるための方法などを紹介します。
大学受験のために塾を探している方は、ぜひ参考にしてください。
- 大学受験の塾費用は月3万~4万円が相場!年間費用の平均も紹介
- 大学受験でかかる塾費用は授業形式によって異なる
- 授業料だけではない!大学受験でかかる塾費用の内訳を紹介
- 入塾金(入会金)
- 教材費
- 季節講習・特別講習費用
- 模試・テスト費用
- 塾の施設使用料や諸経費
- 大学受験のための塾費用に関する注意点
- 「費用が安い=質が低い」わけではない
- 塾代に加えて大学の受験料もかかる
- 【予算別】大学受験に向けた塾の選び方|塾代を安く抑える方法も紹介
- 塾の選び方①費用を抑えて大学受験対策をしたい場合
- 塾の受講科目を絞る
- 集団授業や映像授業を選ぶ
- 季節講習・特別講習の受講を控える
- 入塾時に無料・割引キャンペーンを利用する
- 特待生制度を活用する
- 塾の選び方②大学受験のためなら費用が高くてもよい場合
- 大学受験の塾費用は高額なため複数の塾を比較検討することが大切
大学受験の塾費用は月3万~4万円が相場!年間費用の平均も紹介
大学受験のために高校生が塾に通う際、かかる費用は塾によって異なりますが、文部科学省が公表する「令和3年度子供の学習費調査」によると、高校生の通塾にかかる1年間の平均額は年間36万〜45万円程度、月額に換算すると3万〜4万円程度であるとわかります(※1)。
◆学習塾にかける平均費用
| 高校 | 公立高校(全日制) | 私立高校(全日制) |
|---|---|---|
| 平均年間費用 | 約36.3万円 | 約44.7万円 |
ただし、この金額はあくまでも高校生の通塾にかかる費用であり、大学受験ではなく高校の学習の補助としての通塾も含まれています。
また、このデータを参考にすると、公立高校よりも私立高校に通う高校生のほうが塾にかける年間費用が高い傾向にあることがわかります。
年間費用の割合も見てみましょう。公立・私立高校共に40万円以上の割合が高いことがわかります。
◆高校生の塾にかかる年間費用の金額分布
年間費用 | 公立高校(全日制) | 私立高校(全日制) |
|---|---|---|
〜1万円未満 | 7.7% | 6.3% |
〜5万円未満 | 11.1% | 12.2% |
〜10万円未満 | 9.8% | 11.5% |
〜20万円未満 | 17.2% | 14.8% |
〜30万円未満 | 18.0% | 11.7% |
〜40万円未満 | 12.2% | 9.6% |
40万円以上 | 24.1% | 34.1% |
(※1)参考:文部科学省「調査結果の概要」
塾の費用は、公立・私立といった違いはもちろん、さまざまな要素によって変動します。その要因の1つとして挙げられるのが塾の授業形式です。
塾の授業形式は、主に集団授業・個別指導・映像授業に大別されますが、どの授業形式をメインにしているかによっても塾の費用は異なります。
大学受験でかかる塾費用は授業形式によって異なる
塾の費用(授業料)は、授業形式によっても異なり、一般的に個別指導、集団授業、映像授業の順に安くなる傾向にあります。
週2回授業がある場合の塾費用の相場は、以下の表をご覧ください(※2)。
◆塾・学習塾の月額授業料目安(週2回の場合)
授業形式 | 月謝の相場 | 年間費用 |
|---|---|---|
個別指導 | 3万〜5万円 | 36万〜60万円 |
集団授業 | 2万〜4万円 | 24万〜48万円 |
映像授業 | 1万〜1.5万円 | 12万〜18万円 |
(※2)Ameba塾探し調べ
塾の授業形式によって年間費用は大きく異なるため、紹介した相場を参考にしつつ、通う塾を決めましょう。
なお、現役生や浪人生が予備校に通うためにかかる費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
大手予備校の費用を参考にして具体的に紹介しているため、予備校の利用を検討している方はぜひチェックしてみてください。
授業料だけではない!大学受験でかかる塾費用の内訳を紹介
大学受験のために塾に通う際、塾代は授業料だけではなく、以下のような費用も発生します。
塾を決める前に、パンフレットなどに記載されている料金に対して、上記のような費用がどこまで含まれているかチェックしておくことが大切です。
各費用を以下で詳しく解説しますので、入塾する前に理解しておきましょう。
入塾金(入会金)
入塾金は、入塾時にかかる費用のことで、塾によって金額は異なります。塾ごとに入塾金・入会金・入学料など呼び名が異なる場合がありますが、すべて意味合いは同じです。
塾によっては入塾金がかからないケースや、期間限定で無料になるキャンペーンを実施していることもあるため、公式サイトをチェックしてみましょう。
教材費
教材費とは、授業で使用する教材に対してかかる費用のことです。塾によって授業料に含まれている場合もあるので、入塾前に確認しておきましょう。
もし別途教材費が必要な場合は、受講する科目ごとに教材費が発生し、科目数が多くなるほど高額になる可能性があるため注意が必要です。
季節講習・特別講習費用
季節講習とは、春休みや夏休み、冬休みにおこなわれる講習のことを指し、それぞれに参加費用が発生します。
通常授業と同じく、集団授業よりも個別指導の季節講習のほうが費用が高くなり、冬期講習より実施期間が長い夏期講習のほうが高い傾向にあります。
また、高校1〜2年生よりも、受験対策に特化したカリキュラムでおこなわれる3年生の季節講習のほうが費用が高くなりやすいです。
季節講習は任意参加であるケースがほとんどですが、まれに通常授業の一環に組み込まれて、実質的に参加必須であるケースもあります。入塾前に確認しておきましょう。
また、特別講習は、苦手科目の克服や志望校ごとの入試対策など、ニーズにあわせておこなわれる講習のことを指します。
特別講習への参加は、希望者による任意参加が一般的ですが、季節講習と同じく費用がかかるため、事前に確認しておきましょう。
以下の記事では、春期講習・夏期講習におすすめの塾を紹介しています。受験学年に追い込みをかけたい方はぜひ参考にしてください。
模試・テスト費用
塾では一般的に、全国共通模試や学力・偏差値を測るためのテストが定期的におこなわれます。
とくに受験生となる3年生は何度も受けることになり、1回あたり5千〜1万円程度の費用が発生するため注意が必要です。
模試代は初期費用に含まれているケースや、その都度ごとに支払うケースなど、塾によって異なります。
また、模試・テストの回数や、任意か必須かも塾によって異なります。入塾前によく確認しておくことが大切です。
塾の施設使用料や諸経費
塾によっては施設使用料などの諸経費がかかる場合があります。
諸経費とは、自習室や教室の光熱費、塾のセキュリティシステムなど、塾の運営に必要な費用を指します。
月謝や授業料に含まれていることもあるため、必要ない設備やサポートがないか、あらかじめ確認しましょう。
大学受験のための塾費用に関する注意点
大学受験のために塾を探す際、費用に関して以下の点にも注意するようにしましょう。
「費用が安い=質が低い」わけではない
大学受験の塾を選ぶ際、費用は考慮すべきポイントです。「お得さ」に目がいってしまうものの、「安いということは教育の質が高くないのでは…」と不安に思う方もいることでしょう。
塾の費用については、安いから質が低いわけではありません。費用が安い塾のなかには、広告費用を抑えて低価格で学習機会を提供する塾や、個人で経営している塾などがあります。
費用が安いことが気になる場合は、合格実績がある塾かどうかを確認したうえで、体験授業を受けて指導の質を確認するようにしましょう。
塾代に加えて大学の受験料もかかる
大学受験をする際、塾の費用にのみ注目してしまいがちですが、大学受験時は別途「受験料」がかかります。
私立大学の平均受験料は30,000円~35,000円が相場です(※1)。複数の大学を受験する場合、費用が高くなる可能性がある点をあらかじめ認識しておきましょう。
なお、国公立大学を受験する場合、大学入学共通テストの受験料と、二次試験の受験料がかかり、合計29,000~35,000円ほどになります。
※1 出典:公益財団法人 生命保険文化センター「ライフイベントから見る生活設計」
【予算別】大学受験に向けた塾の選び方|塾代を安く抑える方法も紹介
大学受験のためにかかる塾の費用が予想以上に高いと感じた方もいるのではないでしょうか。
ここでは、予算別に塾選びのポイントを紹介します。塾の費用を安く抑える方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
塾の選び方①費用を抑えて大学受験対策をしたい場合
大学受験のための塾費用をできるだけ抑えたい場合は、以下の点を意識して塾を選んでみましょう。
塾の受講科目を絞る
塾では一般的に科目と受講時間数によって費用が変わるため、必要科目に絞って受講することで費用を抑えられる可能性があります。
すでに受験する大学が決まっているのであれば、学校で勉強している科目すべてを受講するのではなく、受験に必要な科目だけに絞るとよいでしょう。
そのほか、得意科目だけ受講して成績を伸ばす、苦手科目だけを受講して克服するなど、目的に応じて受講科目を限定すれば、その分かかる費用も抑えやすくなります。
たとえば、「個別教室のトライ」では、受講したい科目に絞って指導を受けられます。完全1対1の個別指導なうえ、1科目だけでも可能です。苦手科目だけを克服したいなど、受講したい科目が決まっている方におすすめです。
集団授業や映像授業を選ぶ
塾の費用は、個別指導塾よりも集団授業塾や映像授業塾の方が安価な傾向があります。
集団授業塾は、友人やクラスメイトと切磋琢磨する環境で勉強に取り組める人や、積極的に講師に質問できる人におすすめです。
授業中に質問や発言をすることが苦手な場合でも、授業時間外に質問できるサポート体制が整っている集団授業塾であれば、内向的な性格のお子さんも安心して受講できるでしょう。
通信環境が整った現在では、映像授業にプラスしてオンラインで個別対応をおこなっている塾もあります。こういった塾は全国の高校生を対象にしているため、近くに塾がない方にもおすすめです。
季節講習・特別講習の受講を控える
季節ごとにおこなわれる講習や特別講習は月謝とは別に費用が発生することが多く、その金額も高額になる傾向にあります。
年間の支出として大きな割合を占める費用のため、やみくもに受講するのではなく「期間が長く、学力アップが望める夏期講習だけを受ける」「受験前の追い込みとして冬期講習だけ受ける」といったように、必要なものだけ受けましょう。
また、講習の内容が外部向けに構成されたカリキュラムの場合もあります。講習内容が学習の目的に合致しているかチェックしたうえで、不要と感じるのであれば季節講習を受けないのも選択肢のひとつです。
長期講習では多くの塾で新しい問題集や課題が配布されますが、あまりに多すぎるとどれも中途半端で学習の質が落ちてしまいます。
学習の質を上げるためにも、今ある課題を明確に見極めて、完璧にこなすことを優先させましょう。
塾によっては、季節講習が入塾を検討している方に対するお試しのような一般向けの内容であるケースもあります。
そのため、夏期・冬期講習による出費を増やしたくないという方は、事前に季節講習の内容や主な対象者などを確認して講習の受講を控えるとよいでしょう。
入塾時に無料・割引キャンペーンを利用する
塾によってはお得なキャンペーンを実施していることがあり、キャンペーン中に入塾することで費用を抑えられる可能性があります。
キャンペーンの内容としては、入塾金無料キャンペーンや授業料1か月無料キャンペーンなどがあり、新学期がはじまる直前のタイミングで実施する傾向にあります。
キャンペーンにはそれぞれ適用条件があるため、内容を確認したうえで積極的に活用してみてください。
たとえば「個別指導塾スタンダード」では、入会金無料なうえ、個別指導1か月分の授業料が0円もしくはスタート月謝割引が最大50%OFFになるキャンペーンを実施しています。
さらに、他塾からの乗り換えで5コマ分が無料、友だち紹介でギフトカードプレゼントや教材費の割引クーポンがもらえるキャンペーンなども開催。
キャンペーン内容は時期によっても異なるので、入塾のタイミングで実施中のキャンペーンは見逃さないようにしましょう。
特待生制度を活用する
塾によっては、成績のよい学生を対象に、授業料の免除をおこなっていることがあります。
成績のよい生徒を入塾させることで、塾の合格実績を上げることを目的としており、一般的に「特待生制度」と呼ばれています。
前提として好成績を収める必要がありますが、待遇によっては塾の費用を大幅に削減できる可能性があるため、塾選びの際に特待生制度の有無や条件も一緒に確認しておきましょう。
たとえば「湘南ゼミナール 高等部」では模範特待生制度があり、特定の科目の成績や偏差値に応じて授業料・教材費が25%か50%もしくは全額返金されます。
学力に自信がある方は、このような特待生制度や奨学金制度がある塾を選ぶと支出を抑えられる可能性があります。
塾の選び方②大学受験のためなら費用が高くてもよい場合
「成績が上がり、合格が近づくのであれば、多少費用が高くても問題ない」という場合は、以下の点を重視して塾を選びましょう。
マンツーマンの個別指導塾で徹底的に受験対策をおこなうのもひとつの手ですが、「集団授業塾」と「個別指導塾」、「集団授業塾」と「オンライン塾」など、異なる授業形態の塾を併用して効率よく勉強するのもおすすめです。
また、「予備校」に通いながら、苦手科目や分野を「個別指導塾」でフォローする、という選択肢もあります。予備校は大学受験に特化しているため、より効果的な受験対策が可能。
さらに、季節講習や特別講習など、受験直前まで講習を受講して、苦手分野を克服し、実践力を高めることに注力するのもおすすめです。
大学受験に向けた模試やテストは、Ameba塾探しの調査では、1回につき約2,750円の受験料がかかることがわかっています。現在の学力を把握するためにも積極的に受けるようにしましょう。
なお、予備校については下記の記事で詳しく解説しています。おすすめの予備校も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
塾の授業形式や目的を決めきれていない方は、まずは塾の種類や特徴などについて理解を深めておきましょう。
塾の種類と向いている子どもの特徴については以下の記事をご覧ください。
大学受験の塾費用は高額なため複数の塾を比較検討することが大切
高校生が大学受験のために通う塾費用は、平均すると年間36万〜45万円と高額です。塾によってはそれ以上の費用がかかる場合もあるでしょう。
しかし、塾は費用が高ければよいというものではありません。自分の子どもにあったスタイルで勉強できる塾、予算内で家計を圧迫しない塾を見つけることも大切です。
Ameba塾探しでは、たった10秒で塾が探せる「ぴったり塾診断」があります。大学受験対策できる塾を比較検討する際は、ぜひ診断結果も参考にしてみてください。