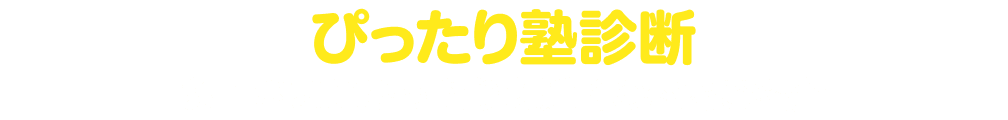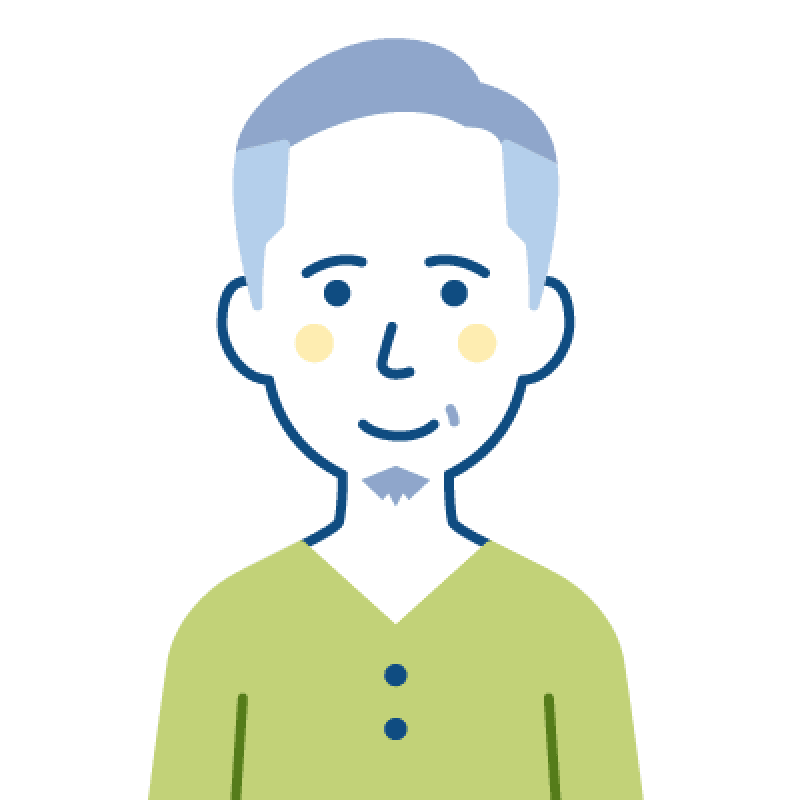さまざまなタイプの塾があるなかでひとつに絞り切れず、塾の掛け持ちを検討している方もいるのではないでしょうか。
掛け持ちが本当に必要かどうか正しく判断するためには、そのメリットとデメリットを把握しておく必要があります。
そこで本記事では、塾を掛け持ちすることのメリット・デメリットを解説したうえで、併用する際のポイントについて説明します。
- 塾を2つ以上掛け持ちするのはあり?実際の割合を紹介
- そもそも塾を2つ以上掛け持ちすることは可能?
- 実際に塾を掛け持ちしている人の割合
- 塾の掛け持ちを成功させる4つのポイントを紹介
- メイン塾とサブ塾を決め、役割を明確に分ける
- スケジュール管理を徹底して無理のない計画を立てる
- 各塾の宿題量を事前に把握して調整する
- 塾同士のカリキュラムが重複しないよう確認する
- 塾を掛け持ちする4つのメリット
- それぞれの塾のいいとこ取りができる
- 複数の塾からより多くの受験情報を得られる
- 塾の施設や設備を効率的に利用できる
- 塾での仲間が増えて交友関係が広げられる
- 塾を掛け持ちする3つのデメリット
- より多くの費用が必要になる
- 指導方法の違いで混乱してしまう可能性がある
- 通塾が負担になってしまう可能性がある
- 中学受験で塾の掛け持ちを行うおすすめの方法
- 集団塾と個別指導塾を組み合わせて苦手科目を克服する
- メイン塾と専門特化塾で得意科目をさらに伸ばす
- 季節講習のみ他塾を活用して効率的に学習する
- 高校受験で塾の掛け持ちを行うおすすめの方法
- 進学塾と補習塾を使い分けて基礎と応用を両立させる
- 5教科対応塾と英数専門塾で効果的に成績を上げる
- 通常塾とオンライン塾を掛け持ちして時間を有効活用する
- 大学受験で塾の掛け持ちを行うおすすめの方法
- 大手予備校と個別指導塾で総合力と弱点克服を両立する
- 予備校の通常授業と映像授業を組み合わせて効率化する
- 科目別に専門塾を使い分けて志望校対策を強化する
- 塾の掛け持ちで失敗しないための注意点
- ①それぞれの塾に通う目的を明確にする
- ②受講する授業の数(コマ数)を多くし過ぎない
- ③お子さんの意見を尊重する
- ④トータルの費用を確認しておく
- 掛け持ちする塾を選ぶときは比較が重要
- 塾の掛け持ちはメリット・デメリットを把握した上で判断しよう
塾を2つ以上掛け持ちするのはあり?実際の割合を紹介
塾の掛け持ちを検討する際、そもそも複数の塾に通うことが可能なのか、実際にどの程度の受験生が掛け持ちをしているのか気になる方も多いでしょう。
実際の塾の掛け持ちの割合について、具体的なデータをもとに詳しく解説していきます。
そもそも塾を2つ以上掛け持ちすることは可能?
「塾ってそもそも掛け持ちできるの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、基本的に塾側がほかの塾との併用を制限することはありません。
塾には、集団授業塾・個別指導塾・オンライン塾といった種類があります。実際に集団塾や個別指導塾に通いつつ、オンライン塾を併用している人もいます。
ただし、むやみに塾を掛け持ちしても学力が上がるというものでもありません。
掛け持ちで通うことのメリットとデメリットを踏まえて、本当に塾を掛け持ちすべきかどうかしっかり検討する必要があります。
実際に塾を掛け持ちしている人の割合
塾を掛け持ちしている人はどれくらいいるのか気になる方も多いでしょう。
調査から年数が経っていますが、文部科学省が平成20年に実施した「子どもの学校外での学習活動に関する実態調査報告」にて、塾の掛け持ちに関する調査がおこなわれています(※1)。
調査によると、小学1年生から中学3年生までの「学習塾・家庭教師・通信添削・ならいごと」利用者のうち、複数を掛け持ちしている子どもの割合は、30〜40%です。
この数値には習い事などの掛け持ちも含まれていますが、複数の学習活動を掛け持ちしている小中学生が一定数いることわかります。
塾を掛け持ちしている人は、決して珍しくはないと考えてよいでしょう。
(※1)参考:文部科学省「子どもの学校外での学習活動に関する実態調査報告」
塾の掛け持ちを成功させる4つのポイントを紹介
塾の掛け持ちで成功させるためには、計画的な準備と運用が欠かせません。
費用や時間の負担を最小限に抑えながら、学習効果を最大化するための重要なポイントを詳しく解説していきます。
メイン塾とサブ塾を決め、役割を明確に分ける
塾の掛け持ちを成功させるために最も重要なのは、それぞれの塾の役割を明確にすることでしょう。メイン塾では受験に必要な全体的なカリキュラムを網羅し、基本的な学習ペースを作ります。
一方、サブ塾は特定の目的に特化した補完的な役割を担うことが効果的です。
たとえば、メイン塾で集団授業を受けながら、サブ塾では苦手科目の個別指導を受けるという使い分けがおすすめです。役割分担を明確にすることで、学習の重複を避け、効率的な時間配分が可能になるでしょう。
塾を選ぶ際は、事前に両塾のカリキュラムや指導方針を確認し、相互に補完関係が築けるかを検討することが大切です。
スケジュール管理を徹底して無理のない計画を立てる
複数の塾に通う場合、スケジュール管理は学習効果を左右する重要な要素となります。
授業時間だけでなく、移動時間や宿題に取り組む時間、さらには休息時間まで含めた総合的な計画が必要です。
週単位でスケジュールを可視化し、無理のない時間配分を心がけることが大切です。特に移動時間は見落としがちですが、往復で1時間以上かかる場合は、体力的な負担も考慮する必要があります。
また、定期テストや学校行事との兼ね合いも重要なポイントといえるでしょう。柔軟にスケジュールを調整できるよう、両塾の振替制度なども事前に確認しておくことをおすすめします。
各塾の宿題量を事前に把握して調整する
塾の掛け持ちで最も負担になりやすいのが、複数の塾から出される宿題の管理です。
事前に各塾の宿題量を把握し、現実的にこなせる量かを検討しましょう。
必要に応じて塾側と相談し、宿題量の調整をお願いすることも選択肢の一つです。多くの塾では、掛け持ちをしている生徒の事情を理解し、柔軟に対応してくれる傾向にあります。
宿題の優先順位をつけることも大切でしょう。メイン塾の宿題を優先し、サブ塾では最低限必要な課題に絞るなど、戦略的な取り組みが学習効果を高めます。
無理に全てをこなそうとすると、かえって学習の質が低下する可能性があるため注意が必要です。
塾同士のカリキュラムが重複しないよう確認する
塾を効率的に掛け持ちするためには、各塾のカリキュラムの重複を避けることが不可欠でしょう。同じ単元を異なる塾で学習すると、時間の無駄になるだけでなく、混乱を招く可能性もあります。
入塾前に年間カリキュラムを詳細に確認し、学習内容の進度や扱う単元を比較検討することが大切です。特に季節講習では重複が起きやすいため、事前の調整が必要といえるでしょう。
ただし、意図的に重要単元を複数の視点から学ぶという戦略もあります。
異なるアプローチで同じ内容を学ぶことで、より深い理解につながる場合もあるため、目的に応じた使い分けが重要です。
塾を掛け持ちする4つのメリット
塾の掛け持ちを検討しているものの「学習がうまくいくのだろうか」と不安を感じる方もいるでしょう。
塾を掛け持ちするメリットとしては、主に以下のようなことが挙げられます。
それぞれのメリットについて詳しく説明します。
それぞれの塾のいいとこ取りができる
塾には、それぞれ強みがあります。
たとえば授業形式で分類した場合、集団授業が中心の塾は質の高い講師の授業が受けられること、個別指導の塾はそれぞれの生徒にあったカリキュラムを組んでもらえることなどが強みです。
集団授業の塾と個別指導塾を掛け持ちすると、「基本的な勉強は集団授業の塾で進め、理解しきれなかった部分を個別指導塾で補う」といったように、それぞれの強みを活かす形で塾の使い分けができます。
これは、難関校合格に向けて効率よく学習したい受験生がよくおこなう掛け持ちのスタイルです。
Ameba塾探しには、塾を掛け持ちした方の口コミも寄せられています。
複数の塾からより多くの受験情報を得られる
多くの塾では、各学校・大学の入試出題傾向など受験情報を収集し、合格者のデータを保有してします。
塾によって保有しているデータは異なるため、掛け持ちすることでより多くの受験情報を得られるかもしれません。
また、数値化されたデータ以外の情報も幅広く集められます。
たとえば、塾によって通う生徒の所属学校や学力レベル、講師の質は異なるため、受験の悩み相談などをするときにはこれまで気づかなかった道を示してくれることもあるでしょう。
学校や塾、インターネットでさまざまな情報が飛び交うなか、有益な受験情報をより多く得ることができるのは、塾を掛け持ちするメリットのひとつです。
塾の施設や設備を効率的に利用できる
塾では自習室を設けていることも多く、自宅だとなかなか集中できない子どもにとって貴重な勉強場所となります。
ただし、塾の場所によっては移動に時間を取られてしまうこともあるので気を付けたいところ。
たとえば、一方の塾はカリキュラムを重視して自宅から遠いところを選び、もう一方は自習室などの施設利用を目的として自宅や学校の近くにあるところを選ぶなどの掛け持ち方法が考えられます。
最近では自習室を充実させている塾も多いため、施設目的で塾を選ぶ場合は自習室の内装や設備にも注目してみましょう。
塾での仲間が増えて交友関係が広げられる
通塾するタイプの塾を掛け持ちすると、塾での交友関係が広がります。交友関係が広がることで、以下のようなメリットが得られます。
- ライバルが増え、学習のモチベーションが上がる
- 志望校や将来の夢、学校生活などに関して新たな知見を得られる
- 受験に関する情報をより早く、より多く入手できる可能性がある
塾によって通っている生徒層や志望校が変わってくるため、掛け持ちするとほかの学校に通う同年代の生徒と出会えるでしょう。
また、交友関係が広がると、得られる情報量が確実に増加します。受験に対するモチベーションが高い生徒と仲良くなれれば、受験勉強にもより一層身が入るはずです。
塾を掛け持ちする3つのデメリット
一方、塾を掛け持ちするデメリットとして以下のような点が挙げられます。
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
より多くの費用が必要になる
複数の塾に通う場合、費用が高くなりやすいです。
たとえば、もともと集団授業の塾に通っており、理解しきれなかった部分のフォローとして個別指導塾に通うことを検討するようなケースで考えてみましょう。
この場合、新たに通いはじめる塾の入会金・入塾金など、授業料以外の費用を余分に負担することになります。
塾の掛け持ちをする場合は、どれくらいの費用がかかるかを事前に見積もり、その費用に見合った効果が期待できそうかどうかを見極めなければなりません。
指導方法の違いで混乱してしまう可能性がある
塾や講師によって指導方法に違いがあります。複数の塾で同じ科目の授業を受ける場合、指導方法が異なることによって勉強の方針が定まらなくなることも考えられるでしょう。
指導方法の違いによる混乱を避けたい場合は、それぞれの塾で異なる科目を受講するようにするなど、自分なりに対処することが大切です。
通塾が負担になってしまう可能性がある
通う塾が増えると、その分だけ通塾に時間がかかります。長時間の通塾および勉強による負担は、疲労やストレスを蓄積する原因となりかねません。
土日に通う塾は家から近くの塾にするなど工夫することで、通塾の負担を多少なりとも和らげることができるでしょう。
塾の掛け持ちは、さまざまな指導方法から自分にあったものを選べる人や、疲労やストレスに強い人でないとあまり向いていないかもしれません。
無理して塾を掛け持ちすると、かえって体力的・精神的に負担となり、目的を達成できないおそれがあることも認識しておきましょう。
中学受験で塾の掛け持ちを行うおすすめの方法
中学受験では、小学生という年齢を考慮した無理のない塾の掛け持ちが求められます。
体力的・精神的な負担を最小限に抑えながら、効果的に学力を伸ばすための具体的な方法を紹介します。
集団塾と個別指導塾を組み合わせて苦手科目を克服する
中学受験でおすすめな塾の掛け持ち方法は、集団塾をメインにしながら、個別指導塾で苦手科目を克服することです。
集団塾では競争意識を持ちながら全体的な学力向上を図り、個別指導では一人ひとりのペースで弱点克服に取り組めます。
特に算数でつまずきやすい単元がある場合、個別指導での丁寧な解説が効果的です。
集団授業についていけない部分を個別にフォローすることで、全体の学習効率が大きく向上するでしょう。
ただし、週の授業回数は合計で4回程度に抑え、小学生の体力に配慮することが大切です。過度な負担は逆効果となる可能性があるため、バランスを重視した併用が必要といえます。
メイン塾と専門特化塾で得意科目をさらに伸ばす
得意科目を武器にして難関校を目指す場合は、専門特化塾との塾の掛け持ちがおすすめです。
たとえば、算数が得意な生徒は算数専門塾で発展的な問題に取り組み、他の受験生との差別化を図ることができます。
理科実験教室や作文専門塾など、特定分野に特化した塾も選択肢の一つです。メイン塾で基礎を固めながら、専門塾で強みをさらに伸ばすという戦略は、入試での得点力向上につながるでしょう。
志望校の出題傾向に合わせて専門塾を選ぶことも重要です。
記述問題が多い学校なら作文塾、思考力を問う学校なら算数専門塾など、目的を明確にした選択が成功への鍵といえます。
季節講習のみ他塾を活用して効率的に学習する
通年での掛け持ちが難しい場合は、季節講習期間のみ他塾を利用する方法もおすすめです。
塾を併用し、夏期講習や冬期講習で苦手分野の集中対策を行うことで、効率的な学力向上が期待できるでしょう。
大手塾の季節講習は、志望校別の特別講座や弱点補強プログラムなど、多彩なコースが用意されています。普段通っている塾にない専門的な講座を選択することで、学習の幅を広げることが可能です。
費用面でも通年での塾の掛け持ちより負担が少なく、短期集中型の学習は小学生にとっても取り組みやすいといえるでしょう。
ただし、講習期間中の宿題量は増加するため、計画的な時間管理が必要となります。
高校受験で塾の掛け持ちを行うおすすめの方法
高校受験では、内申点対策と入試対策の両立が求められます。
学校の定期テストと受験勉強のバランスを取りながら、効果的に塾を併用する方法について詳しく解説していきましょう。
進学塾と補習塾を使い分けて基礎と応用を両立させる
高校受験において効果的な塾の掛け持ち方法は、進学塾で応用力を養いながら、補習塾で学校の授業など基礎的な内容を学習することです。
進学塾では入試レベルの問題に取り組み、補習塾では定期テスト対策を中心に内申点向上を目指します。
中学3年生になると、学校の授業進度と受験対策のギャップが大きくなりがちです。
補習塾で学校の予習復習をきちんと行うことで、内申点を確保しながら受験勉強に集中できる環境が整うでしょう。
部活動との両立を考える場合、時間的な制約も考慮する必要があります。週2回ずつの通塾など、無理のないペースで両立を図ることが、継続的な学習につながるといえます。
5教科対応塾と英数専門塾で効果的に成績を上げる
公立高校入試では5教科の総合力が求められる一方、英語と数学でつまずきがちです。
そのため、5教科対応塾で全体的な学力を底上げしながら、英数専門塾で重点科目を強化する塾の掛け持ちがおすすめでしょう。
英語と数学は積み上げ型の科目であり、一度つまずくと取り戻すのが困難です。専門塾での体系的な指導により、基礎から応用まで着実にステップアップすることが可能になります。
理社国については5教科対応塾での学習で十分な場合も多く、効率的な時間配分ができるでしょう。
志望校の配点や自身の得意不得意を考慮して、最適な組み合わせを選択することが重要といえます。
通常塾とオンライン塾を掛け持ちして時間を有効活用する
部活動や習い事で忙しい中学生には、通塾とオンライン塾の掛け持ちがおすすめです。
メインの塾には週2~3回通いながら、空いた時間にオンライン塾で補強学習を行うことで、時間を有効活用できるでしょう。
オンライン塾は移動時間が不要で、自宅で好きな時間に受講できるメリットがあります。苦手単元の復習や、欠席した授業のフォローなど、柔軟な活用が可能です。
録画授業なら繰り返し視聴できるため、理解度に応じた学習ペースで進められます。
通塾での対面指導とオンラインの利便性を組み合わせることで、効率的な受験対策が実現できるでしょう。
大学受験で塾の掛け持ちを行うおすすめの方法
大学受験では、志望校や学部によって必要な対策が大きく異なります。限られた時間で最大の成果を上げるため、戦略的な塾の活用方法について具体的に見ていきましょう。
大手予備校と個別指導塾で総合力と弱点克服を両立する
大学受験でおすすめの塾の掛け持ち方法は、大手予備校をベースにしながら個別指導塾で弱点を補強することです。
予備校の体系的なカリキュラムで全体的な学力を向上させつつ、苦手科目は個別指導でピンポイントに対策できます。
大手予備校の集団授業では質問しづらい場合も、個別指導なら納得いくまで解説を受けられるでしょう。特に数学や物理など、理解の積み重ねが重要な科目では個別指導の効果が高いです。
費用は増加しますが、浪人を回避できる可能性を考えれば、投資価値は十分にあるでしょう。
週1~2回の個別指導を加えることで、予備校の授業理解度が格段に向上する場合が多く見られます。
予備校の通常授業と映像授業を組み合わせて効率化する
時間効率を重視する受験生には、予備校の通常授業と映像授業の組み合わせがおすすめです。
得意科目は映像授業で効率的に学習し、苦手科目は対面授業でじっくり理解を深めるという使い分けが可能でしょう。
映像授業は倍速再生や一時停止が可能なため、自分のペースで学習を進められます。通学時間や空き時間を活用して視聴することで、限られた時間を最大限に活用できるでしょう。
『東進衛星予備校』や『スタディサプリ』など、質の高い映像授業サービスが充実しています。
予備校の授業と映像授業を効果的に組み合わせることで、コストパフォーマンスの高い受験対策が実現できます。
科目別に専門塾を使い分けて志望校対策を強化する
難関大学や特殊な入試形式の大学を目指す場合、科目別に専門塾を使い分ける方法がおすすめです。
英語は英語専門塾、数学は数学専門塾など、各科目のスペシャリストから指導を受けることで、より包括的な対策が可能になります。
医学部受験なら医系専門予備校、美術系なら実技対策塾など、進路に特化した塾の活用も重要です。一般的な予備校では対応しきれない専門的な指導を受けることで、合格の可能性が大きく向上するでしょう。
ただし、複数の塾を掛け持ちする場合は、スケジュール管理がより重要になります。
各塾の課題や模試日程を一元管理し、優先順位を明確にすることが、塾を掛け持ちする際のポイントです。
塾の掛け持ちで失敗しないための注意点
塾の掛け持ちは可能ですが、お子さんの負担にならないようにいくつか注意すべき点があります。
おもに以下の点に注意して塾を選びましょう。
①それぞれの塾に通う目的を明確にする
塾を掛け持ちするなら、それぞれの塾に通う目的を明確にしましょう。
たとえば、受験に向けて短期集中で学力を伸ばしたい場合は、一方の塾では受験に向けて発展的な内容を学習し、もう一方の塾では理解しきれなかった部分を補う授業をしてもらう、といった掛け持ちスタイルがおすすめです。
役割を分けて考えることで、それぞれの塾の強みを最大限活かせます。
②受講する授業の数(コマ数)を多くし過ぎない
塾を掛け持ちすると、当然ながら受講するコマ数も自然と多くなります。
しかし、あまりにコマ数が多いと予習・復習に十分な時間が取れず、学習効率がかえって悪くなりかねません。
塾で質の高い授業を受けることはもちろん大事ですが、自分で学習する時間を確保することも同じぐらい重要です。
掛け持ちすると1週間の勉強スケジュールがキツくなってしまう場合は、それぞれの塾で受講する授業数を減らすことも検討しましょう。
また、もうひとつの案としては、通塾タイプの塾を掛け持ちするのではなく、オンライン塾を使って自宅学習ができる環境を整えるという手があります。
最近はオンライン塾にもさまざまなタイプが登場しているため、無理に通塾タイプで掛け持ちしようとせず、自分のニーズにあったオンライン塾との掛け持ちも検討してみましょう。
③お子さんの意見を尊重する
塾に通うのは、保護者ではなくお子さんです。「成績が上がらないから」「今通っている塾がよくないのだ」と一方的に決めつけて塾の掛け持ちを決めるのではなく、お子さんと状況を話し合ったうえで対応を決めましょう。
無理して塾を掛け持ちさせると、精神的に負担がかかってしまいます。
お子さんがどうしたいか、という意志を尊重することが大切です。
④トータルの費用を確認しておく
前述したとおり、塾を掛け持ちすると費用面の負担が増すケースがあります。
費用の詳細を把握しないまま通塾すると、「授業料だけかと思っていたら特別講習費用が想定外にかかり、家計を圧迫してしまった」という状況になりかねません。
塾によって内訳や金額は異なりますが、以下のような費用がかかると仮定して、通塾に総額いくらかかるのかをあらかじめ算出しておきましょう。
掛け持ちする塾を選ぶときは比較が重要
塾の掛け持ちにはメリットもデメリットもあり、どの塾を選ぶかしっかり吟味する必要があります。
塾・学習塾の検索サイト「Ameba塾探し」では、塾の形式・科目・通う目的など、掛け持ちする塾を選ぶときに気になるさまざまな条件を指定して検索が可能。
悩みや要望にあったおすすめの塾を10秒で診断する「ぴったり塾診断」もあります。
全国9万教室以上のなかから条件にあう塾を比較・検討できるため、ぜひ活用してみてください。
塾の掛け持ちはメリット・デメリットを把握した上で判断しよう
塾の掛け持ちには、それぞれの塾のいいとこ取りができるメリットがあります。
その反面、通塾時間や授業時間が増えることで、負担やストレスにつながる可能性があるといったデメリットもあります。
塾を掛け持ちすることのメリットとデメリットを正しく把握したうえで、それぞれの塾のメリットを最大化できるよう意識して通いましょう。
また、自分にあった塾を選ぶには、さまざまな判断軸で複数の塾を比較検討することが大切です。
Ameba塾探しでは、授業形式や学年・科目・特別講習などのさまざまな項目から塾を検索できるほか、塾同士を簡単に比較できます。
「どんな塾に通うか決めかねている」「今通っている塾と掛け持ちしやすそうな塾が知りたい」という方は、ぜひAmeba塾探しを利用してみてください。