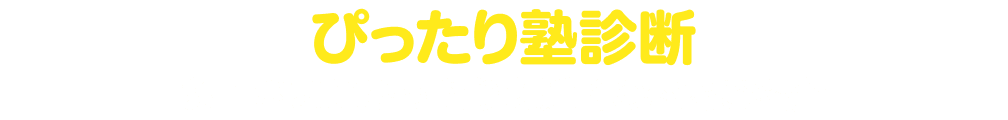中学生や高校生のなかには、塾や予備校の夏期講習に行くべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
夏期講習は通常の塾の授業とは異なるカリキュラムで集中して学習できるため、苦手克服や受験対策に効果的です。そのため、目的や志望校がはっきりしているのであれば、夏期講習を受けることをおすすめします。
本記事では、夏期講習のメリット・デメリットを解説するとともに、夏期講習が向いている人・向いていない人の特徴を紹介します。
時間と費用を無駄にしないためにも、夏期講習を選ぶ際の注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
夏期講習に行くべきか判断するポイントを紹介
夏期講習に行くべきか悩んでいる場合は、以下に挙げるチェックポイントに自分が当てはまるかどうかで考えてみるとよいでしょう。
冒頭でも触れたように、夏期講習の受講は苦手克服や受験対策にとても効果的です。夏期講習向けに特別に組まれたカリキュラムによって、効率的な学力向上が望めるでしょう。
また、夏休み中は学校がないので勉強の機会は生徒自身に委ねられますが、自宅で学習することが苦手な方もいるでしょう。夏期講習に通えば学校に通っているのと同じように、ある意味強制的に勉強することができるので、勉強しない期間が続くことを避けられます。
学校の授業が進むスピードが速く、授業についていけないと悩んでいる方にとって、夏期講習で予習・復習をしっかりおこない、学力の土台を築いておけば、2学期以降の学校の授業についていきやすくなるでしょう。
なお、夏期講習では連日塾に通う日程でカリキュラムが組まれていますが、通常の塾の授業とは別に費用がかかる場合が多いです。比較的時間を確保しやすく、費用を負担することに問題ない方は、先に挙げたチェックポイントにひとつでも当てはまれば、夏期講習を受講することをおすすめします。
夏期講習が向いている人・向いていない人
ここでは、夏期講習はどんな人が向いているのか、受講が必要な方と、そうでない方の具体例を紹介します。夏期講習の受講が向いているのは、以下に挙げるような人です。
夏期講習では、塾が組んだカリキュラムで計画的に勉強することができます。自分で勉強計画を立てて進めるのが苦手な方にとって、夏期講習に通う意義は大きいでしょう。
自宅だとゲーム・漫画・テレビなどさまざまな誘惑があるので、勉強しようと思ってもついサボってしまう方もいるかもしれません。夏期講習に通うことで、集中して勉強に取り組むことが可能です。
加えて、効率的に受験対策をしたい方にも夏期講習はおすすめです。受験傾向を熟知している講師陣の授業によって、受験に必要な知識をピンポイントで吸収できるでしょう。
また、苦手科目を克服したいという方にも、夏期講習の授業は役立ちます。塾によっては「○○特別講座」や「○○特訓」などのように、特定の分野に絞った授業を設けている場合があります。そういった授業を選んで受講することで、苦手科目の克服が見込めるでしょう。
夏期講習は学校の授業が進まない夏休み中に実施されるので、学校の進度を気にせずに勉強することができます。期間も1か月半程度と長いので、基礎固めをするのにはうってつけです。
一方、夏期講習に向いていない、夏期講習に通う必要がないのは、以下に挙げるような人です。
夏期講習では、基本的に塾側が勉強の方針を定めてカリキュラムを組んでくれますが、それを自分でできる方もいるでしょう。知識と経験が豊富な講師による授業を受けられるというメリットはもちろんありますが、自分で計画的に勉強できる方にとっては、夏期講習に通う意義が少ないかもしれません。
また、夏休み中は部活動の練習や合宿・試合などで忙しい方もいますし、家族で長期の旅行に行く方もいます。夏期講習では数日間をひとつの区切りとして授業する場合が多いので、部活動などで忙しくスケジュール調整が難しい方は夏期講習に通うのに向いていないでしょう。
夏期講習のメリット・デメリットを紹介
夏期講習に通うかどうかを判断するためには、夏期講習のメリット・デメリットを把握しておかなければなりません。夏期講習のメリット・デメリットを次より詳しく説明します。
夏期講習のメリット
夏期講習を受講するメリットとして、主に以下の点が挙げられます。
夏期講習は1か月半という短い期間で、集中して勉強に打ち込むことができます。短期集中だからこそ「学力向上」という成果もすぐに出やすく、勉強に対するモチベーションを高く維持できるでしょう。
塾の夏期講習では、知識や経験が豊富なプロ講師による指導を受けられます。わかりやすく要点をおさえた授業によって、学力が着実に向上していくのを感じられるでしょう。
中3生や高3生は、約半年後に受験が控えています。受験対策をいつからするかは個々の状況次第ですが、塾の夏期講習では「○○大学(高校)特別講座」といった志望校に特化した対策講座・コースも設けられています。そういった授業を受講することで、しっかりと受験対策をすることが可能です。
また、人によっては学習習慣が身についていないこともあるでしょう。夏期講習では連続してほぼ毎日授業がありますし、次の授業までに終わらせるべき宿題も出されます。受けた授業の復習をして宿題を解くなかで、自然と勉強する習慣が身につくでしょう。
夏期講習で設けられているカリキュラムは塾によって異なりますが、「長文対策講座」「図形応用講座」のような授業を設けている塾もあります。苦手分野に特化した授業を受講することで、夏休みの間に効率的に克服することが可能です。
また、塾では学力や志望校別にクラス分けされることが多いです。同じような目標を持つ生徒たちと切磋琢磨できる環境に身を置くことで、勉強により一層身が入るでしょう。
夏期講習のデメリット
一方、夏期講習を受講するデメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。
夏期講習は学力向上や苦手克服に効果的ですが、いくつも授業を受講すると費用が高額になります。通う塾や学年によっては数万円〜十数万円の費用が必要になることもあるので、受講する内容を考慮しなければなりません。
上述したように、塾の夏期講習のカリキュラムでは数日間の授業を1セットとすることが多いです。それだけの日程を夏期講習の授業で固定されると、スケジュールがタイトになり、部活や家族の用事などとの両立が難しくなる懸念も出てくるでしょう。
また、複数の授業を受講すると、ほぼ1日中塾にいるようなことも考えられます。授業の復習をして宿題を解いて…といったように勉強に打ち込めるのはよい点ではありますが、自主学習の時間が減ってしまう可能性があることは念頭に置いておく必要があります。
とくに集団塾の夏期講習でのカリキュラムは、多くの生徒にあわせた最大公約数的な内容になっているケースが多いです。「ここは知っているからあまり時間を割く必要がないのに…」「この分野はよくわかっていないからもっと説明してほしいのに…」と、講習の内容に不満を持つ可能性も否定できません。
夏期講習に行かない場合の学習法
夏期講習に行かないと判断した場合、塾に頼らずに自分で勉強を進める必要があります。夏期講習に行かない場合に効果的な学習法としては、主に以下が挙げられます。
スケジュールの問題で塾の夏期講習に通うのが難しい場合は、オンライン講座の活用がおすすめです。塾に行かずとも自宅で授業を受けることができるので、勉強習慣を身につけるのにも役立ちます。
独学で勉強を進める場合は、事前に学習計画を立てるのがおすすめです。1日・1週間・1か月単位でスケジュールを立てて、自主学習しましょう。自分で学習計画を立てることで、苦手分野はどこか、何に重点を置いて勉強すべきかを認識しやすくなります。
また、家庭教師やオンライン個別指導を検討するのもよいでしょう。どちらも塾に通わずとも自宅で勉強ができますし、自分のためだけに組まれたカリキュラムによるマンツーマン指導も大きな魅力です。
夏期講習を選ぶ際の注意点|5つのポイントをチェックしよう
夏期講習に行こうと決めても、塾の選択肢が多すぎて悩んでしまうこともあるかもしれません。夏期講習で通う塾を選ぶ際は、以下に挙げるようなポイントをチェックするとよいでしょう。
それぞれのポイントを次より詳しく説明します。
目的にあわせたコース・講座はあるか
夏期講習に通う目的は、一人ひとり異なります。塾によって特定の単元の復習に特化したカリキュラムを組んでいるところもあれば、新学期で習う分野を先取りして勉強するカリキュラムのところもあります。また、受験生を対象に志望校対策をおこなう塾・予備校もあります。
夏期講習に通う目的を明確にし、その目的を達成できるコース・講座がある塾を選びましょう。
集団授業や個別指導など授業形式
塾の授業形式は、「集団授業」と「個別指導」に大別されます。
集団授業では、学校の授業と同じように十数人~数十人程度の生徒と一緒に授業を受けます。授業の進め方は講師によって異なり、ほぼ一方的に説明と板書を続ける講師もいれば、適宜生徒に質問を投げかけてコミュニケーションを取りながら授業を進める講師もいます。
塾のクラスはレベル別で分けられていることが多いので、同じくらいの学力の生徒と一緒に切磋琢磨できる点がメリットです。ただし、人によっては「比べられている感じがして嫌だ」「質問しにくい」と感じることもあるかもしれません。
個別指導では、講師1名に対して生徒が1~3名程度で授業がおこなわれます。マンツーマンもしくはそれに近い形での授業になるので、授業は講師と生徒で会話を交わしながらおこなわれるのが一般的です。
生徒の理解度や進度に応じて柔軟にカリキュラムを組んでもらえるため、ほかの生徒が気になることもありません。ただし、講師と生徒の距離が近いことで緊張感が減ってしまうケースも考えられます。
どちらの授業形式があっているかはお子さん自身の性格次第なので、よりあっているほうを選びましょう。
授業料や模試代などトータルの費用
夏期講習の費用相場は、集団授業の塾と個別指導塾で異なります。受講するコースや講座によっても変動しますが、授業料のほかに模試代や教材費などがかかる場合があるため、トータルでいくらかかるのか確認するようにしましょう。
なお、宿泊を伴う夏合宿に参加したり特別講座を受講したりする場合は、別途費用が必要となることが多いため、費用面の負担も考えなければなりません。
夏期講習後にそのまま塾に通い続ける可能性がある方は、通常授業の費用も一緒に確認しておくのがおすすめです。
小学生から高校生まで、学年ごとの費用相場については、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
無理なく受講できるスケジュールか
夏期講習が始まる時間は塾によってさまざまですし、選ぶ授業によって曜日も異なります。たとえば学校で部活に入っている場合、部活動の練習や合宿と両立できるスケジュールであることが重要です。
受験学年は部活もラストシーズンです。最後まで悔いなく部活動に打ち込めるように、勉強と部活動を無理なく両立できるスケジュールの塾を選びましょう。
塾のサポート体制や学習環境
塾のサポート体制や学習環境も、塾選びにおいて重要なポイントです。授業後に質問対応を受け付けてくれたり、体調不良や部活動への参加などで授業を受けられなかった場合のフォローアップがあったりするのは、プラス要素といえるでしょう。
塾で自習をしたい方は、そもそも自習室はあるのか、自習室は勉強に集中できる環境かどうかも確認しましょう。長丁場の場合は塾でお弁当を食べるようなこともありますので、食事をするスペースの有無も確認しておくのが賢明です。
受験生は、受験を検討している高校や大学の資料・過去問などが充実しているかも確認することで、より納得のいく塾選びができるでしょう。
口コミなどでも塾のサポート体制を知ることができますので、気になる塾があれば口コミや評判もチェックすることをおすすめします。
夏期講習に行くべきかどうかは目的や状況にあわせて検討しよう
夏期講習は、受講することで短期間での集中的な学習ができる、受験対策に有利、苦手克服が可能など、いくつものメリットがあります。ただし、自分で学習計画を立てられて勉強を進められる方は、必ずしも夏期講習を受講する必要はありません。
プロ講師によるわかりやすい授業を受けたい、ライバルと一緒に切磋琢磨したい方には、夏期講習の受講がおすすめです。自分の学習状況や客観的に判断された志望校の合格可能性などを踏まえて、夏期講習に行くべきかどうかを判断しましょう。
夏期講習を実施している塾は多いので、どの塾を選ぶべきかと悩んでしまうことも考えられます。塾が設けているコースや講座、塾の指導形式、スケジュールなどを総合的に判断して決めましょう。
夏期講習におすすめの塾については、「Ameba塾探し」にてランキングで紹介していますので、ぜひ参考にしてください。自分にあった塾を見つけて、夏期講習を実りあるものにしましょう!