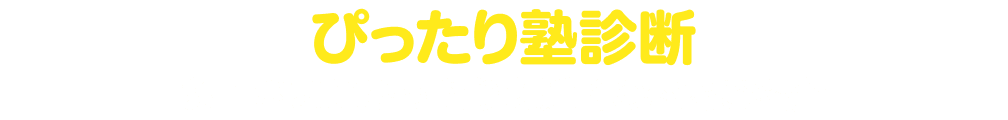子どもを塾に通わせたいと思っているものの、家計への負担を考えるとなかなか厳しい…と感じている保護者の方もいることでしょう。
また、現在塾に通っている方のなかには、授業料はもちろんのこと、講習費や模試代などの追加費用が家計を圧迫し、塾代がきついと感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、塾代がきついと感じる場合にご家庭でできる対処法を紹介します。
さらに、塾の費用が高額になる要因も解説しますので、塾にかかる費用を抑えたい保護者の方は、ぜひ参考にしてください。
- 塾代がきついと感じて当然!塾の費用は月3万円が相場
- 塾代は月3万円が相場!小学生から高校生までの平均費用を紹介
- 塾代がきつい理由とは?塾費用が高額になる要因5つ
- 子ども一人にかかる教育コストが高騰している
- 専門的な講師陣の人件費が高額
- 長期化する受験準備期間の影響
- 充実した設備・教材への投資
- 塾業界の競争激化による差別化の影響
- 塾代が家計圧迫してきつい時の対処法6つ
- ①通塾コストがかからないオンライン塾を利用する
- ②地方自治体の制度を利用する
- ③塾の特待生制度を利用する
- ④受講するコマ数・科目を減らす
- ⑤キャンペーンや各種割引制度を利用する
- ⑥パートなどで収入を増やす
- 塾代がもったいないと感じたら?受験別に塾の必要有無を解説
- 中学受験で塾が必要なケース・不要なケース
- 塾が必要なケース
- 塾が不必要なケース
- 高校受験で塾が必要なケース・不要なケース
- 塾が必要なケース
- 塾が不要なケース
- 大学受験で塾が必要なケース・不要なケース
- 塾が必要なケース
- 塾が不要なケース
- 塾代がきついときこそ受講内容を見直し、塾を賢く利用しよう!
塾代がきついと感じて当然!塾の費用は月3万円が相場
まだ子どもが塾に通うような年齢ではない方のなかには、「子どもを塾に通わせる出費がそんなに厳しいのか?」と思う方もいるかもしれません。
以下であらためて触れますが、子どもを塾に通わせるための費用の相場は月3万円です。
水道光熱費などの固定費に加えて、新たに毎月3万円の出費が増えると考えると、きついと感じるのも当然でしょう。
次より子どもを塾に通わせるための費用について説明します。
塾代は月3万円が相場!小学生から高校生までの平均費用を紹介
塾代として必要な費用は、子どもの学年や通っている学校の公立・私立などによって多少変わりますが、月3万円程度が相場です。
文部科学省が公表した令和5年度「子供の学習費調査」の「学習塾費」によると、小学生~高校生の子どもがいる家庭で、塾費用を1円以上支払っている場合の平均費用は以下のとおりです。
【学年別・塾費用の年間平均】
| 学年 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
小学生 | 56,167円 | 264,241円 |
中学生 | 230,343円 | 168,058円 |
| 高校生 | 147,746円 | 112,639円 |
※出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」
塾費用の月額平均が月3万円ということは、年間で36万円の費用がかかることになります。多少の差はあるものの、どの学年でもおおむね近い金額に収まっていることがわかるでしょう。
なお、塾代の「きつさ」を適切に考えるためには、日本の平均年収が過去30年でほとんど上がっていないことを考慮しなければなりません。
昨今は物価高に悩まされている方も多いと思いますが、それに伴い年収も上昇しているのであれば、きつさも常識的な範囲に収まってくれるはずです。
1989年~2018年の30年間における平均年収の推移を5年ごとにデータにまとめると、以下のようになります。
【平均年収の推移】
| 年 | 平均年収 |
|---|---|
1989年 | 452.1万円 |
1994年 | 465.3万円 |
1999年 | 463.6万円 |
2004年 | 455.7万円 |
2009年 | 421.1万円 |
2014年 | 419.2万円 |
2018年 | 433.3万円 |
※出典:厚生労働省「令和2年版厚生労働白書」
この30年間で平均年収は上がっていないどころか、少し下がっていることがわかります。そして昨今の物価高が重なっているわけですから、家計が苦しくないわけがありません。
塾代をきついと感じるのは当然のことですし、多くのご家庭に共通した悩みといえます。
塾代がきつい理由とは?塾費用が高額になる要因5つ
塾費用は年々上昇傾向にあり、多くの家庭にとってきついと感じる要因となっています。
なぜこれほど高額になってしまうのか、その背景にある主要な要因を5つの観点から詳しく解説します。
子ども一人にかかる教育コストが高騰している
この30年、日本の平均年収はほとんど上がっていないにも関わらず、習い事の月謝や塾代は年々上がり続けているのが現状です。
そのため、塾代がきついと感じるのは当然のことでしょう。
文部科学省がおこなっている「子供の学習費調査」によると、塾代などに該当する「学校外活動費」の金額は、平成20年→平成26年→令和3年→令和5年と以下のように推移しています。
【学校外活動費の推移】
| 平成20年 | 平成26年 | 令和3年 | 令和5年 | |
|---|---|---|---|---|
公立小学校 | 21.0万円 | 21.9万円 | 24.8万円 | 21.6万円 |
私立小学校 | 56.4万円 | 60.4万円 | 66.1万円 | 72万円 |
公立中学校 | 30.5万円 | 31.4万円 | 36.9万円 | 35.6万円 |
私立中学校 | 28.9万円 | 31.2万円 | 36.8万円 | 42.2万円 |
公立高校 | 15.9万円 | 16.7万円 | 20.4万円 | 24.6万円 |
私立高校 | 19.8万円 | 25.5万円 | 30.4万円 | 26.3万円 |
※出典:文部科学省「平成26年度子供の学習費調査」
※出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
※出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」
専門的な講師陣の人件費が高額
中学受験の指導には各中学の試験内容が特有のものである場合が多く、専用の対策を行う必要があるため、専門性を高めるための講師の研修や教材研究にも時間とコストがかかります。
また、大学受験の指導には、各科目の深い知識と効果的な指導技術が求められ、特に難関大学の対策では、東大・京大・医学部などの出身者や、長年の指導実績を持つベテラン講師が必要不可欠です。
こうした優秀な人材を確保するには、一般的な教育機関よりも高い報酬を提示する必要があります。
また、試験内容は毎年傾向が変わるため、講師は常に最新の入試問題を分析し、指導法をアップデートしなければならず、これも人件費が高額になる要因でしょう。
長期化する受験準備期間の影響
近年の大学受験では、準備期間の長期化が顕著になっています。
以前は高校3年生から本格的な受験勉強を始めるのが一般的でしたが、現在では高校1年生、さらには中学生から塾に通い始める生徒が増加しています。
文部科学省の令和5年度「子供の学習費調査」によると、高校生(全日制)の学習塾費支出率(実質的な通塾率)は以下の通りです。
【高校生の通塾率】
| 学年 | 公立高等学校(全日制) | 私立高等学校(全日制) |
|---|---|---|
| 1年生 | 約28-31% | 約32-35% |
| 2年生 | 約34% | 約38% |
| 3年生 | 約38% | 約42-48% |
※出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」
また、ベネッセ教育総合研究所の「学校外の学習機会」を見ると、1990年の通塾率は約13%でしたが、2015年には約27%になっており、2023年(令和5年)では全体で約35%に上がっていることが理解できます。
この背景には、大学入試の難化や、推薦入試での評定平均値の重要性の高まりがあるためといえるでしょう。
早期から通塾することで、基礎学力の定着や苦手科目の克服に時間をかけられるメリットはありますが、その分トータルの塾費用は膨大になります。
充実した設備・教材への投資
現代の学習塾では、単に授業を提供するだけでなく、総合的な学習環境の整備が求められています。
快適な自習室の完備は必須となっており、個別ブース型の自習スペースや、質問対応可能なチューターの配置など、授業時間外の学習サポート体制も重要です。
また、タブレット端末を使った学習システムや、AIによる個別最適化された問題演習、欠席時でも受講できる映像授業の配信など、最新の教育技術への投資も欠かせません。
これらのシステム開発や維持には多額の費用がかかります。
さらに、独自の教材開発も要素としては大きく、市販の参考書では対応できない、各塾オリジナルの教材やテスト問題の作成には、専門スタッフの人件費や印刷費など相当なコストが必要となり、これらすべてが授業料に反映されているといえるでしょう。
塾業界の競争激化による差別化の影響
少子化が進む中、塾業界では競争が年々激しくなっており、各塾は他塾との差別化を図るため、授業以外のサービスも充実させる傾向にあるといえるでしょう。
定期的な保護者面談、進路相談担当の配置、など、付加価値サービスは多岐にわたります。
また、合格実績を上げるための少人数制クラスや、志望校別の特別講座の開設も増えており、これらは生徒にとってメリットが大きい一方で、講師一人あたりの生徒数が減少するため、必然的にコストは上昇します。
また、塾代の詳細については、下記の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
塾代が家計圧迫してきつい時の対処法6つ
塾代がきついと感じても、子どもの将来を考えると「塾に継続して通わせたい」と思うのが親心でしょう。
塾にかかる費用をなるべく抑えることができれば、子どもを塾に通わせることが現実的になるはずです。
そこで、ここからは家計への負担を抑える方法を紹介します。
①通塾コストがかからないオンライン塾を利用する
家計への負担を抑えて塾に通うには、集団塾や個別指導塾よりも塾代が安い傾向にあるオンライン塾を利用するのも、ひとつの手です。
オンライン塾は設備費用がかからないうえ、自宅で受講するので通塾するための交通費がかかりません。
通信インフラが整備され、スマートフォンやタブレットなどが普及していることにより、オンライン塾を受講するハードルは下がってきています。
また、オンライン塾は、学習管理システムやAIを活用した個別学習プラットフォームが整備されていることから、個別に最適化された学習が可能なのもメリットです。
なお、オンライン塾は自宅などの好きな場所で好きな時間に受講できるのがメリットですが、自己管理能力が必要となるため、自信のない方にはオンライン個別指導の利用をおすすめします。
②地方自治体の制度を利用する
地方公共団体によっては、塾費用の補助がおこなわれているところもあります。
たとえば東京都では、「受験生応援チャレンジ支援貸付事業」という制度があり、一定所得以下の世帯に、学習塾をはじめ受験対策講座、通信講座、補助教室の受験料など、必要な資金の貸付をおこなっています。
この制度では、中学3年生を対象に、一部の塾に限り塾費用や受験料を20万円まで無利子で貸付を受けることが可能です。
志望校に合格した場合、返済が免除されるも場合もあるので、東京都で通塾を検討している方は調べてみるとよいでしょう。
また、大阪市では市内在住の小学5年生~中学3年生を対象に、学習塾や家庭教師などの費用を月額1万円を上限に助成する「大阪市習い事・塾代助成事業」をおこなっています。
ほかにも、つくば市には条件を満たした方を対象に、月額5,000円を上限に学習塾の利用にかかる授業料の一部を助成する制度があります。
各自治体によって制度の内容が異なるため、住んでいる地域の奨学金制度や補助制度について調べてみましょう。
③塾の特待生制度を利用する
塾によっては、成績のよい学生を対象に、授業料の免除をおこなっていることがあります。
成績のよい生徒を入塾させることで、塾の合格実績を上げることを目的としており、一般的に「特待生制度」と呼ばれています。
たとえば湘南ゼミナールでは、中学生のコースで「模範特待生」に選ばれると、毎月の授業料から3,000円~20,000円の割引を受けることが可能です。
毎月3,000~20,000円、年間36,000~240,000円が免除されると、教材などの購入費用や今後の教育費用に充てられます。
ただし、適用には一定の条件があるため、「うちの子は該当するだろうか?」と心配な場合は、あらかじめ情報を確認したうえで塾に問い合わせてみましょう。
④受講するコマ数・科目を減らす
受講する科目数やコマ数が増えるほど費用は高くなるので、必要なカリキュラムを選定して受講する科目やコマ数を絞ることで、費用を抑えられます。
とくに、個別指導塾は受講する科目やコマ数によって料金が大きく変わるので、独学で取り組む自信がない科目や、成績アップが厳しいと感じる科目だけに絞るとよいでしょう。
また、塾では追加での科目受講を勧誘されることもあるので、きちんと目的意識を持って科目を選ぶことが大切です。
⑤キャンペーンや各種割引制度を利用する
キャンペーンを利用することで入会金や講習費が無料になる塾もあるので、入塾を検討している塾がキャンペーンをおこなっているかどうか、公式サイトで確認してみてください。
また、塾によっては兄弟割引や複数受講割引、ひとり親家庭割引など各種割引をおこなっていることがあります。
利用できるキャンペーンや割引があれば、積極的に活用して家計への負担を抑えましょう。
「候補の塾はあるけれど、うちの子にはどんな塾があうのかわからない…」とお悩みの方は、簡単な質問に答えるだけでおすすめの塾がわかる「ぴったり塾診断」も使ってみてください。
⑥パートなどで収入を増やす
家計支出を見直しても塾代の捻出が困難な場合は、収入を増やすという選択肢も検討しましょう。
子どもの学校時間や塾の時間を活用して、パートやアルバイトを始めることで月3〜5万円の収入増加が期待できます。
一般的な塾代は月3万円程度が相場となっているため、主婦の方も普段の生活の空き時間で、塾代分を十分に賄うことが可能といえるでしょう。
塾代がもったいないと感じたら?受験別に塾の必要有無を解説
塾代の負担が大きいと感じる保護者の方は多いでしょう。
受験の種類によって塾の必要性は異なるため、中学受験・高校受験・大学受験において塾が必要なケース、不要なケースをそれぞれ解説します。
中学受験で塾が必要なケース・不要なケース
中学受験は特殊な受験対策が求められるため、塾の利用率が高い傾向にあります。しかし、すべての子どもに塾が必要というわけではありません。
塾が必要なケース
難関私立中学や国立中学を目指す場合、塾での専門的な指導が有効です。
これらの学校では、小学校の授業内容を大きく超えた問題が出題されます。特に算数の特殊算や国語の記述問題は、独学での対策が困難でしょう。
志望校の出題傾向に精通した講師の指導を受けることで、効率的な学習が可能になります。また、同じ目標を持つ仲間との切磋琢磨も、モチベーション維持に役立ちます。
塾が不必要なケース
公立中高一貫校のみを受験する場合や、基礎学力の定着を重視する中学校を志望する場合は、必ずしも塾は必要ありません。
適性検査型の入試では、思考力や表現力が重視されるため、家庭学習や通信教育でも対策が可能です。
子どもが自主的に学習できる環境があり、保護者がサポートできる時間的余裕がある家庭では、市販の問題集や通信教育を活用した学習でも十分な場合があります。
例えばスタディサプリ(小学講座・中学講座)は月額約2,000円という低価格でプロ講師の授業を受けられます。何講座受講しても定額なので、費用面の負担がおさえられます。
スタディサプリは、自分のペースで学習を進められるのが魅力で人気のある映像授業サービスなので塾代がきついと感じる場合などには活用を検討してみましょう。
高校受験で塾が必要なケース・不要なケース
高校受験は中学受験や大学受験よりも多くの生徒が経験する受験ですが、学校の授業と自主学習で対応できるケースも少なくありません。
塾が必要なケース
難関高校や上位校を目指す場合、塾での体系的な学習が効果的です。
これらの学校では、教科書レベルを超えた応用問題が出題されることが多く、学校の授業だけでは対策が不十分になりがちです。
苦手科目がある生徒や、学習習慣が身についていない生徒にとっても、定期的な通塾により学習リズムが作れ、分からない箇所をすぐに質問できる環境は大きなメリットでしょう。
塾が不要なケース
学校の成績が安定しており、自主学習の習慣が身についている生徒は、塾なしでも十分に対応可能です。
特に公立高校の中堅校を目指す場合、学校の授業内容をきちんと理解していれば合格圏内に入れるでしょう。
部活動に打ち込みたい生徒や、経済的な負担を抑えたい家庭では、市販の参考書や問題集を活用した自主学習が現実的な選択となります。
また、最近では無料の学習動画も充実しており、これらを活用すれば塾に通わなくても質の高い学習が可能です。
大学受験で塾が必要なケース・不要なケース
大学受験は最も多様な選択肢がある受験です。国公立大学と私立大学、一般入試と推薦入試など、受験方式によって必要な対策が大きく異なります。
塾が必要なケース
難関大学や医学部を目指す場合、予備校や塾での専門的な指導が重要です。
これらの大学では、高度な思考力や専門知識が要求されるため、独学での対策には限界があります。
複数科目で基礎から学び直す必要がある生徒や、学習計画の立案が苦手な生徒にとっても、塾は強い味方となるでしょう。
浪人生の場合、生活リズムの維持や仲間との情報交換の場として、予備校は重要な役割を果たします。自宅学習だけでは孤独になりがちな浪人生活において、予備校は精神的な支えにもなるでしょう。
塾が不要なケース
学校の授業レベルが高く、自主学習の習慣が確立している生徒は、塾なしでも十分に対応できます。
特に推薦入試を狙う場合、学校の成績維持が最優先となるため、学校の勉強に集中することが大切です。
また、地方在住で近くに適切な予備校がない場合も、オンライン学習や通信添削を活用することで、都市部の受験生と同等の学習が可能になっています。
塾代がきついときこそ受講内容を見直し、塾を賢く利用しよう!
なかなか上がらない年収に物価高と、子どもを塾に通わせるための費用を捻出するのに苦労している家庭も多いと思います。
費用が抑えめに設定されているオンライン塾に通わせるのもひとつの方法ですし、地方自治体や塾で設けられている制度を利用するのも、塾にかかる出費をなるべく減らすためには有効です。
目標達成のために、より多くの科目を受講するよう塾から提案があるかもしれませんが、子どもの学力や得意分野・苦手分野を踏まえて、本当に必要な科目のみ受講するようにしましょう。
Ameba塾探しを利用すれば、それぞれの塾の「平均月額料金」を確認しながら塾選びができます。なるべく費用を抑えながら子どもにあった塾を探す際に、ぜひ参考にしてください。