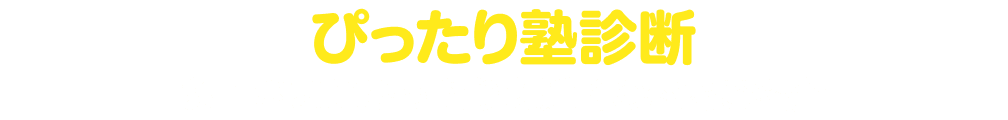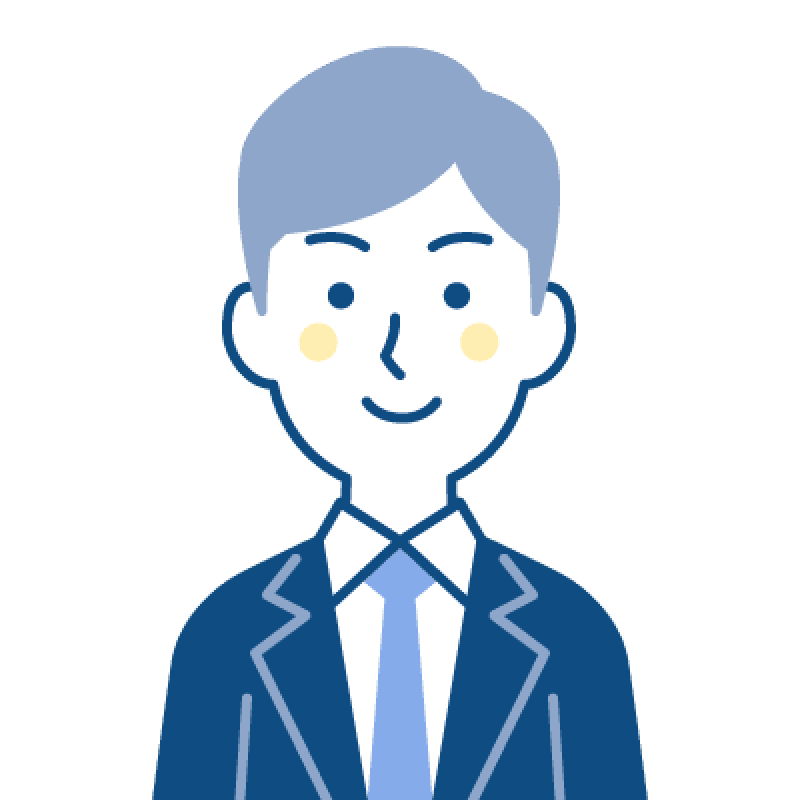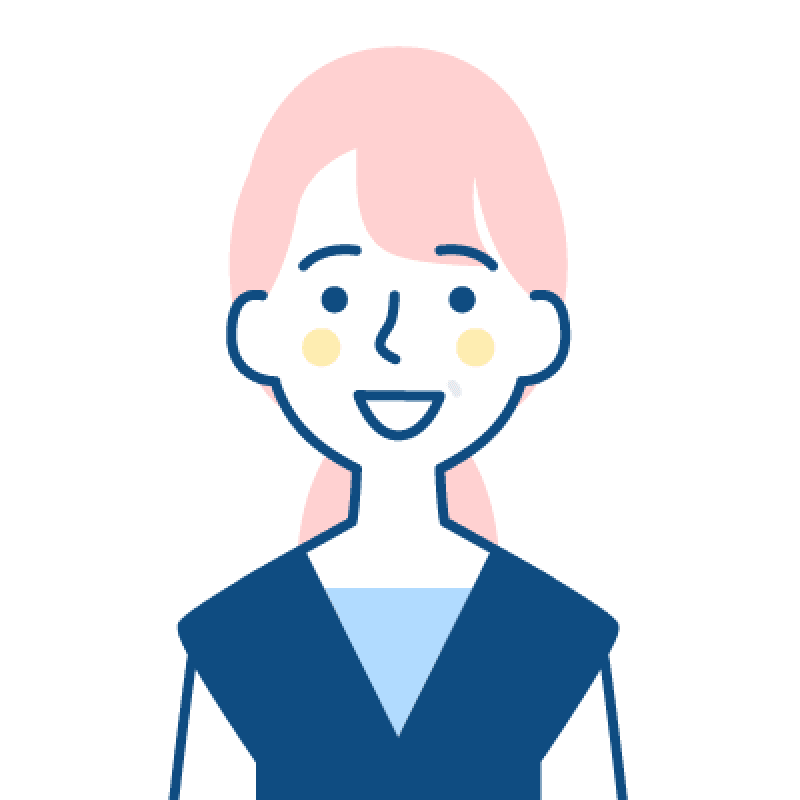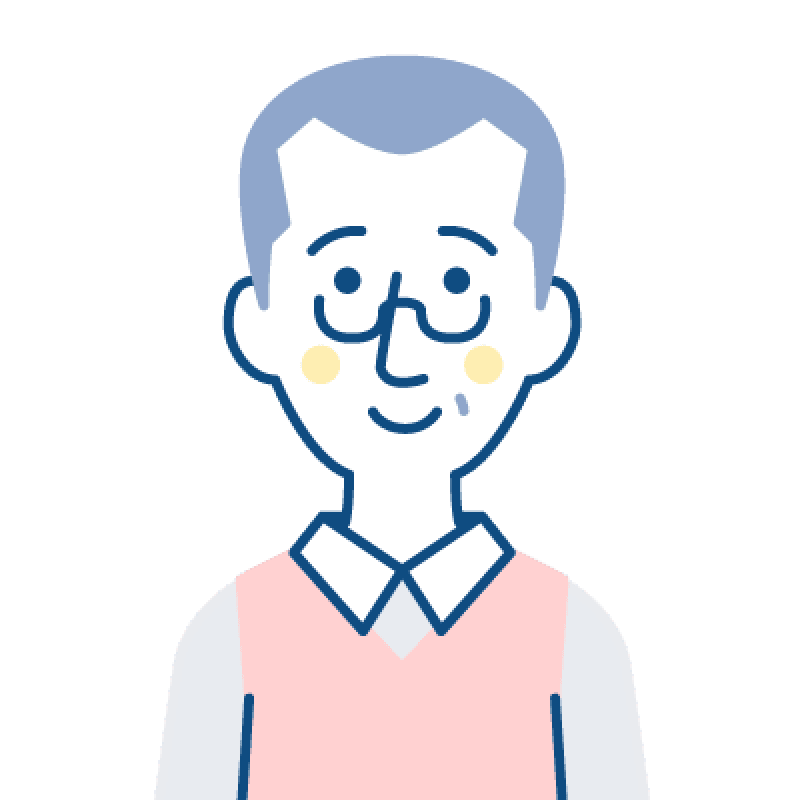「予備校と塾の違いは?」
「費用はどれぐらいかかるのだろう」
高校生や高卒生のなかには、このような疑問を抱く方がいるかもしれません。詳細は本文で解説しますが、予備校とは、大学受験や各種試験の合格を目指す教育機関を指します。河合塾や駿台予備学校が、予備校の代表例です。
河合塾などの予備校は、指導方針、カリキュラム、費用など、塾とは異なる点が多々あります。そのため、塾よりも予備校のほうが向いている方もいます。
ただ、向き・不向きにかかわらず、予備校と塾の違いについては、事前に把握しておくべきでしょう。そうすれば、「どちらを選ぶべきか?」を正確に把握でき、自分にとって最適な勉強環境を手に入れられます。
そこでこの記事では、予備校とは何かだけでなく、塾との違いや、選び方、自分に最適な予備校の探し方を解説します。「予備校のことを知って、自分に最適な予備校がどこかを知りたい!」という方は、ぜひ参考にしてください。
- 予備校とは大学受験のため通う教育機関のこと
- 予備校の定義
- 予備校の歴史
- 予備校の種類
- 予備校のシステム(学習サイクル)
- 予備校の設備
- 予備校の費用
- 予備校と塾の違いは勉強目的や授業スタイルなど
- 指導方針・カリキュラム
- 授業形式
- 講師
- 費用
- サポート体制
- 予備校と塾、自分にあうのはどっち?特徴やメリットを紹介
- 予備校に通うメリット・デメリットと向いている人
- 塾に通うメリット・デメリットと向いている人
- 予備校に通う現役生と浪人生の1日のスケジュール
- 現役生のスケジュール
- 浪人生のスケジュール
- 予備校を探す際の具体的な手順
- 各予備校の情報収集
- 複数予備校の比較検討
- 体験授業に参加
- 費用や環境など!予備校選びのポイント
- 志望大学に対応したコースの有無
- 豊富かつ優秀な講師陣の在籍
- きめ細かな進路指導体制
- 快適に学べる自習環境の整備
- 定期的な模擬試験の実施状況
- 通学の利便性・アクセス
- 学習者のレベルにあわせたカリキュラム
- 手厚いサポート体制
- 利用者からの口コミ・評判
- 高校生・浪人生におすすめの予備校を紹介
- 「駿台予備学校」はAI技術を導入した効率的な学習を実現
- 「河合塾」は弱点の底上げを目指した受験対策ができる
- 「代々木ゼミナール」は2種類の授業形式で徹底理解を追求
- 「東進ハイスクール」は短時間で効率的な学習ができる
- 「四谷学院」は個人能力を高めるダブル教育を受けられる
- 予備校に関するよくある質問
- Q.予備校はいつから通い始めたらいいですか?
- Q.オンライン予備校とは何ですか?
- Q.予備校に通わないと大学に合格できない?
- Q.予備校の寮や学生マンションはありますか?
- 予備校の特徴や塾との違いを理解し、最適な学習環境を選ぼう
予備校とは大学受験のため通う教育機関のこと
まずは予備校に関する基本情報を解説します。
予備校の定義
順番に解説すると、まず学校教育法に基づくと、予備校は「専修学校」または「各種学校」に該当します。
学校教育法とは、日本における幼稚園から大学までの、学校教育の組織と運営に関わる基本原則を規定する法律のことです。
予備校に該当する「専修学校」と「各種学校」は、この学校教育法にて、それぞれ以下のように定義されています。
専修学校は、第一条の学校(幼稚園・小中高・大学など)以外で、職業技能や実生活で役立つ能力、あるいは教養を体系的に教える教育機関を指します。
詳しくは後述しますが、予備校は広義には職業訓練や資格取得を目指す教育機関も含みます。一部の予備校、とくに公務員試験や医療系資格などの職業訓練をおこなう学校は、専修学校として認可されている場合があります。そのため全部ではありませんが、一部予備校は専修学校に当てはまるといえます。
どの学校が専修学校に該当するかは文部科学省で公表されていますので、参考にしてみてください。
その一方で、各種学校については、以下のように定義づけられています。
各種学校は、法律上の学校には当てはまりませんが、カリキュラムや運営の面で学校に近い教育活動をおこなう民間や公的な教育機関として位置づけられています。どちらかというと、こちらのほうが現在の予備校のイメージに当てはまりますね。
そのこともあり、たとえば駿台予備学校札幌校や河合塾札幌校は行政、厳密には文部科学省から以下のように各種学校に認定されています。
【各種学校に認定されている学校(一部抜粋)】
| 記載項目 | 河合塾情報 | 駿台予備学校 |
|---|---|---|
| 学校No. | 103-1 | 101-1 |
| 学校名 | 河合塾札幌校 | 駿台予備学校札幌校 |
| 郵便番号 | 060-0809 | 060-0806 |
| 位置 | 札幌市北区北9条西3丁目3番地 | 札幌市北区北6条西6丁目1-7 |
| 設置者名 理事長(代表者名) | 学校法人河合塾 河合英樹 | 学校法人駿河台学園 山﨑良子 |
| 校長名 | 北山健一 | 斎藤資晴 |
| 科別 | 予備校 | 予備校 |
| 昼夜別 | 昼 | 昼 |
| 設置年月日 | 昭28.4.22 | 平10.7.31 |
| 電話 | 011-708-8581 | 011-709-7111 |
※参考資料:北海道|各種学校名簿(2025年7月17日時点)
以上のことから、予備校は「専修学校」または「各種学校」に該当するといえます。そして先述したように、各学校が「大学受験や各種試験の合格を目指す教育機関」であるため、専修学校と各種学校に該当する予備校もそのように定義づけられるわけです。
また、予備校を運営しているのは学校法人や財団法人、株式会社などさまざまです。しかし、授業形態や志望校合格を目指す生徒が集まるなど、共通した部分がたくさんあります。
在籍している講師陣も難関私立大学や国立大学を卒業した人が多く、講師の経験を踏まえながら志望校を目指せるのが特徴です。
レベルの高い学生ばかり通うイメージもありますが、成績ごとにクラス分けをしている予備校もあり、自分のペースで成長できるよう配慮されているケースも多いです。
予備校の歴史
予備校の歴史は非常に古く、明治時代にまでさかのぼります。
明治5年に学制、12年に教育令が制定されていますが、以降より旧制中学校や旧制専門学校・旧制高等教育機関・大学への入学を目標とする予備教育の諸学校が次々と設立されるようになりました。これが今でいう予備校です。
明治時代に設立された主な予備校は、以下のとおりです。
【明治時代に創立された予備校一覧】
| 創立年 | 創立時の校名 | 後の校名もしくは所在 |
|---|---|---|
| 1871年もしくは1878年 | 共立学校 | 東京開成中学校 |
| 1880年 | 三田予備校 | 錦城中学校 |
| 1883年 | 独逸学協会学校 | 独逸学協会中学校 |
| 1885年 | 東京英語学校 | 日本中学校 |
| 1888年 | 国民英学会 | - |
| 1889年 | 郁文館 | 郁文館中学校 |
| 1889年 | 正則予備校 | 正則中学校 |
| 1891年 | 高等商業学校予備門 | 私立商工中学校 |
| 1896年 | 正則英語学校 | 正則商業学校 |
| 1897年 | 研数学館 | - |
| 1900年 | 官立学校予備校 | 東京物理学校内 |
| 1902年 | 正則予備学校 | - |
| 1903年 | 開成予備学校 | 開成中学校内 |
| 1903年 | 早稲田高等予備校 | 早稲田中学校内 |
| 1904年 | 京都予備校 | - |
| 1905年 | 錦城予備学校 | 錦城中学校内 |
| 1905年 | 中央高等予備学校 | 中央大学内 |
| 1906年 | 高等予備校 | 専修学校内 |
| 1906年 | 日本高等予備校 | 日本大学内 |
| 1907年 | 明治高等予備校 | 明治大学内 |
| 1908年 | 東洋高等予備校 | 東洋大学内 |
| 1910年 | 東京高等予備校 | 法政大学内 |
※参考資料:
西暦1897年から1910年の間までに設立された予備校は、旧制中学の卒業生が旧制高等学校や旧制専門学校入試に失敗したものに対して設置した補習学校として知られます。このころには、今の予備校の原型が出来上がっていたといえますね。
また、明治末期には、都市部で受験志願者が急増したため、多彩な私立・官立の予備校(三田予備校、独逸学協会学校ほか)が次々と設立され、旧制中学卒業者向けの補習校も広まりました。
当時の予備校は単なる試験対策校にとどまらず、進学希望者の学力補充から受験指導まで一貫して担う教育機関だったといえるでしょう。
予備校の種類
現在の予備校の種類は多種多様です。主に以下のとおりです。
【予備校の種類一覧】
| 予備校の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 大学受験予備校(総合型予備校) | 河合塾
駿台予備学校
代々木ゼミナール 四谷学院 東進ハイスクール・東進衛星予備校 |
| 音楽学校受験予備校 | 東京音楽学院
中尾音楽学院 faith music school ASAKAアートスクール 小金井音楽アカデミー メイト 音楽学院 ラ・ネージュ音楽院長野音大予備校 |
| 美術大学受験予備校 | トーリン美術予備校
仙台美術予備校 千葉美術予備校 |
| 教員採用試験予備校 | 教栄学院
教職ゼミナール メセナ予備校 |
| 医師国家試験・薬剤師国家試験予備校 | CES医歯薬国試予備校
明治鍼灸柔整予備校 東京理学看護予備校 悠久看護予備校 |
| 助産師国家試験受験予備校 | 京都看護医療予備校
関西看護医療予備校 東京理学看護予備校 日本看護医療予備校 |
| 公務員試験予備校 | ヴィッセン公務員試験予備校 |
※2025年7月15日時点
一般に「予備校」といえば、河合塾や駿台予備学校のような大学受験に特化した学習塾を想起しがちですが、広義には職業訓練や資格取得、教養講座なども含む教育機関全般を指します。そのため、音楽や美術に特化させた予備校や、医師や公務員などの職業に特化させた予備校も存在します。
ただし、高校生・高卒生の大学受験に限っていえば、大学受験予備校(総合型予備校)、音楽学校受験予備校、美術大学受験予備校のいずれかを選択することが多いでしょう。
予備校のシステム(学習サイクル)
予備校のシステム(学習サイクル)を簡単にまとめると、以下になります。
上記を何度も繰り返すことにより、学力アップを目指すのが予備校です。単に学習するだけでなく、講師への質問や模試を受けることにより、効率的な学力アップを期待できます。
また、予備校で受けられる講座や模試は以下のとおりです。
【予備校の学習システム例】
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 講座の指導形態 | 大講義型
少人数ゼミ型 個別指導型映像授業型 ハイブリッド型(対面&映像授業など) |
| 講座の種類 | 基礎力養成講座
応用・発展講座 小論文などの専門分野講座など |
| 講座のコース | 学年別コース
進路系統別コース 志望大学別コースなど |
| 特別講座 | 夏期講習
冬期講習 勉強合宿など |
| 模試 | 全国統一模試
大学別入試実戦模試 共通テスト対策模試など |
予備校では、勉強を効率よく進めるために、大人数を対象とした大講義型や、教員と受講生が少人数で深く議論できる少人数ゼミ型かを選べます。予備校によっては、個々の理解度にあわせて進める個別指導型、いつでもどこでも受講できる映像授業型、そして対面と映像を組みあわせたハイブリッド型まで、さまざまな指導形態があります。
また、基礎力強化を目的とした講座や、応用・発展を目指す講座、小論文や専門分野を扱う講座といった専門性の高いコースが揃っているため、自分の志望校や学習状況に応じたコース選択が可能です。
夏期講習や冬期講習、さらには仲間と一緒に集中して取り組む勉強合宿などの特別講習を利用すれば、短期間での学力アップを期待できるでしょう。
最後に、定期的に実施される全国統一模試や志望大学別の入試実戦模試、共通テスト対策模試などで学習の到達度を測り、効率的なステップアップも期待できます。
予備校の設備
予備校の設備として、以下が挙げられます。
【予備校の設備例】
| 設備 | 具体例 |
|---|---|
| 講義教室 | ホワイトボード
大型スクリーン完備の授業スペース |
| 自習室・自習ブース | 自由席の大部屋型自習室
仕切り付き個別ブース |
| 図書室・資料室 | 過去問
参考書 赤本の閲覧コーナー大学案内パンフレット |
| PCルーム・ITラウンジ | オンライン模試
Web演習用PC席 学習進捗管理システムへのアクセス端末 |
| 面談室・相談ブース | 担任
個別面談用スペース |
| ラウンジ・休憩スペース | 飲食可能なフリースペース
ソファ テーブル |
| カフェテリア・売店 | 軽食やドリンク販売コーナー
提携店舗のテイクアウト |
| ロッカー・荷物置き場 | 教材、上着を収納する個別ロッカー
大きめ荷物用置き場 |
| セキュリティ設備 | ICカード入退館管理システム
防犯カメラ 非常誘導灯 防災備品 |
| 環境設備 | 無料Wi‑Fi 冷暖房完備 空気清浄機 |
| バリアフリー設備 | エレベーター 多目的トイレ 車椅子対応通路や入口 |
※利用できる設備は予備校、校舎によって異なります。
予備校には、快適かつ効率的に学習を進められるよう、多種多様な設備が整っています。たとえば、図書室や資料室では過去問や参考書、赤本、各種大学案内パンフレットなどを自由に閲覧できます。過去問などを自由に閲覧できるのは、予備校ならではです。
もちろん学習環境だけでなく、長時間の勉強で疲れたときや、気分転換を図りたいときに役立つ設備も充実しています。これにより、メリハリをつけながら効率的に学習を継続できます。これは、予備校の大きな特長といえるでしょう。
予備校の費用
予備校の費用は主に、入学金+年間授業料+特別講座費+模試代+諸経費で計算されます。
たとえば、高卒生が河合塾の東大理類アドバンストコース、スーパー早慶大文系コースを受講する場合、費用は以下のとおりです。
【予備校の費用例|河合塾の場合】
| 予備校 | 予備校費用の概算 | 内訳 |
|---|---|---|
| 河合塾
※9月からの入塾した場合の費用 | 国公立(東大):954,180円
私立(早慶):914,180円 | 入学金:70,000円 国公立授業料※1:594,000円 私立授業料※2:554,000円 夏期講習:106,000円 冬期講習:98,500円 河合模試:0円(一般生は8,800円) 塾生サポート料:85,680円 |
※1:参考資料:河合塾|東大理類アドバンストコース(2025年7月16日時点)
※2:参考資料:河合塾|スーパー早慶大文系コース(2025年7月16日時点)
上表は、9月入学、夏期講習・冬期講習はともに5講座と想定したシミュレーション結果です。
河合塾の場合だと、理系や文系、夏期講習など特別講習の受講数、共通テスト対策の有無など、コースによって授業料は異なりますが、9月から通う場合は90万円以上の費用が必要となることが多いでしょう。年間で通う場合は、さらに高額になる可能性があります。
もうひとつ例を挙げますと、東進衛星予備校の場合、高3生がユニット10を受講すると、年間の費用は下記のとおりです。
【予備校の費用例|東進衛星予備校の場合】
| 予備校 | 予備校費用の概算 | 内訳 |
|---|---|---|
| 東進衛星予備校 | 1,067,550円 | 入学金:33,000円
担任指導費:77,000円 模試費:29,700円 通期講座料:727,100円 夏期講習:104,500円 冬期講習:96,250円 |
※参考資料:市川市(本八幡)の東進|東進衛星予備校|市川八幡校|諸費用について (2025年7月16日時点)
上表はあくまで一例ですが、約100万円になることがわかりました。受講するユニットにもよりますが、ひとつの目安といえます。
なお、東進衛星予備校では、入学金は一律料金となり、担任指導費や模試費は受験学年かどうかで変わります。
また、東進衛星予備校に限った話ではありませんが、予備校の費用は「現役生、高卒生どちらか」「対面型授業、映像授業どちらか」「週の授業時間数」などの要素で大きく変動します。
予備校や塾の費用について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
予備校と塾の違いは勉強目的や授業スタイルなど
予備校と塾は、学習できる環境は整っている点では共通しています。しかし、主に以下の点で違いが見られます。
予備校と塾で優劣があるわけではないため、「自分にとって向いていそうか」「より勉強に集中できそうな環境か」といった点を踏まえて、通学先を選びましょう。
それぞれの違いについて、以下で詳しく解説します。
指導方針・カリキュラム
予備校と塾では、指導方針やカリキュラムに以下のような違いがあります。
【指導方針・カリキュラムの違い】
指導方針 | カリキュラム | |
|---|---|---|
予備校 | 大学受験対策 | 受験範囲を効率的に対策することが最優先 |
塾 | 学校の授業やテストのサポートから受験対策までさまざま | 基礎から応用に進めるように段階的に進む |
予備校の目的は、大学を中心に生徒の志望校合格なので、指導方針も「受験合格」を最優先にしています。
一方、塾に通う生徒の目的は、学校の授業内容のフォローをしてほしい、将来的な受験に向けて学力を高めたいなど、さまざまです。
そのため、塾によって指導方針はまちまちで、学校内容のフォローやテスト対策を中心におこなうところもあれば、大学受験に向けた学習をおこなうところもあります。
カリキュラムについても同様の観点から違いが見られ、予備校では、授業中に受験範囲を効率的に網羅することを優先したカリキュラムが組まれているので、基礎的な部分のキャッチアップは生徒自身でおこなう必要があります。
一方、塾では通い続けて勉強を継続することで学力を伸ばせるように、基礎から応用に徐々に進んでいくようなカリキュラムが組まれているのが一般的です。
とくに個別指導塾の場合は、生徒の理解度や進度にあわせて柔軟にカリキュラムを変更するのが、大きな特徴といえるでしょう。
授業形式
予備校と塾の授業形式の違いは、以下のとおりです。
予備校の授業形式は講師による説明がメインであり、生徒はそれを聞きながら板書を取ります。
最小限の授業回数で受験に必要な内容を学ぶことができる点はメリットですが、基礎的な内容は自学自習で身につけなければならない場合もあります。
一方、塾の授業形式はさまざまです。大学受験対策に注力している塾であれば予備校に近い形式をとるケースもあるでしょう。
ただし、学校の学習内容に対するサポートを主な目的としている塾は、生徒の理解度を確認しながら授業を進めるので、生徒に対して適宜質問が投げかけられることもあります。
質問が来るかもしれないと考えながら授業を聞くことで、授業内容に対する理解度が深まる点で期待できますが、人によっては多くの生徒の前で質問されることに抵抗感を覚えるかもしれません。
講師
予備校の講師は、講師を専門に務めるプロ講師であることが大半で、基礎的な学習内容を理解していることを前提にハイレベルな指導をおこないます。
授業は基本的に一方通行であり、生徒に集中して話を聞いてもらわなければならないため、とくにトップ講師を中心にして話術や人を惹きつけるような話し方に長けている人もいます。
予備校には、自分が指導している分野に関する著書がある講師もいるので、高い指導力があると考えてよいでしょう。
一方で、塾はプロ講師が務めていることももちろん多いですが、大学生がアルバイト講師として指導していることもあります。予備校と比較して、親身になってくれる講師が多く、質問もしやすい環境でしょう。
大学生の講師に対して不安を抱く方がいるかもしれませんが、つい先日まで高校生だったこともあり、生徒が抱える悩みやつまずきやすいポイントを、解像度高く把握している可能性もあります。
生徒と双方向のやり取りをしながら授業を進めていくという点においても、「生徒との距離の近さ」はプラス要素になりやすいでしょう。
費用
費用面でも、塾と予備校に違いがあります。
予備校と塾というくくりで分けるのは難しいことを前提として、総じて予備校のほうが金額に幅が少なく、塾のほうが幅があるといえます。
予備校は1年間通うことを前提としており、入学時に授業料を一括払いするところが多く(※分割払いに対応している予備校もあります)、金額は年間で50~60万円程度です。ただし、浪人生が通う場合は、受講する講義の数が多くなることから100万円を超える場合もあります。
高校生が通う場合でも、「○○特講」や「○○直前対策」のような講義を追加で受講すると、授業料はもう少し高くなることが想定されます。
一方、塾の費用は集団塾か個別指導塾かによって違いがあり、集団塾の場合は高校生で30~70万円程度、個別指導塾の場合は60~100万円超程度です。
いずれの場合も、受講する講義の数によって金額は多少変動することを念頭に置いておきましょう。
予備校・塾の費用については以下の記事でも解説していますので、詳細が気になる方はご確認ください。
サポート体制
サポート体制に関しては、指導内容に対するサポート体制は予備校のほうが整っており、家庭に対するサポート体制は塾のほうが整っているのが一般的です。
予備校では、講義をおこなう講師のほかに、生徒からの質問に対応したり勉強計画の策定を手助けしたりする「チューター」と呼ばれる人がいます。
チューターは予備校が開いている時間は基本的に常駐しているので、生徒側からアプローチをおこなうことで、さまざまなサポートを受けることが可能です。
また、生徒が志望している大学や学部を踏まえて、ほかの大学・学部の選択肢を提示してくれたり、受けておいたほうがいい模試の情報を教えてくれたりすることもあります。
一方、塾に通う生徒は「学校の成績を上げること」が目的となっていることもあり、多くの場合、それは保護者がお子さんを塾に通わせる目的でもあります。
そのため、塾ではどのような方針で指導をしているか、今後のカリキュラムはどうなっているか、家庭ではどのようなことをしてほしいかといったことを保護者の方に伝える保護者説明会を、定期的に設けている塾もあります。
とくに個別指導塾ではそういったサポートが手厚い傾向にあるので、お子さんにあわせたサポートを受けられる塾をお探しであれば、個別指導塾を中心に検討するのがおすすめです。
予備校と塾、自分にあうのはどっち?特徴やメリットを紹介
前述したように、予備校と塾に優劣があるわけではありません。それぞれの特徴を理解したうえで、自分にあった方を選びましょう。
ここでは、予備校と塾のメリット・デメリットを紹介するとともに、どのような人に向いているのかを解説します。
予備校に通うメリット・デメリットと向いている人
予備校に通うメリット・デメリットおよび、それを踏まえて予備校に向いている人は、以下のとおりです。
【予備校に通うメリット・デメリットと向いている人】
メリット | ・受験に関する最新の情報を知ることができる ・プロ講師による授業が受けられる ・同じ目的をもつ生徒と講義を受けることでやる気が持続する ・勉強に集中できる環境が整えられている |
|---|---|
デメリット | ・予習や復習は生徒任せ ・通うだけで勉強できていると感じてしまう |
向いている人 | ・信頼性が高い情報が欲しい人 ・受験に向けてのコツやテクニックが知りたい人 ・受験に向けてライバルと切磋琢磨したい人 ・自分で予習や復習ができる人 |
予備校では、受験に関する最新の情報を蓄積しており、各大学の赤本・青本も最新のものを揃えていることが多いです。
そのため、受験に向けて信頼性が高い情報が欲しい人にとって、予備校はとても適した環境といえます。
また、予備校で講義をおこなっているのは、基本的に知識や経験が豊富なプロ講師です。授業内容は受験対策として最適化されたものとなっており、受験に向けてコツやテクニックを知りたいと思っている人からすると理想的な授業が受けられるでしょう。
ただし、授業がわかりやすいがゆえに聞いただけで「勉強している」という気になってしまう場合があります。
講義の内容をもとにして、予習や復習をきちんと自分でできる人でなければ、期待していたほど理解が深まらない可能性が高い点には注意が必要です。
さらに、志望校別に講義がおこなわれる場合、同じ講義を受講している生徒はみな受験におけるライバルということになります。周囲の生徒に負けないように切磋琢磨できる人であれば、予備校は向いている環境といえるでしょう。
なお、予備校には自習室が備えられており、お弁当などを食べる休憩室があることも多いです。それだけ勉強に集中できる環境が整えられているのも予備校の大きなメリットです。
塾に通うメリット・デメリットと向いている人
一方で、塾に通うメリット・デメリットおよび、それを踏まえて塾に向いている人は、以下のとおりです。
【塾に通うメリット・デメリットと向いている人】
メリット | ・基礎的な内容から教えてもらえる ・講師と生徒の距離が近い ・カリキュラムを柔軟に変更してもらえる(とくに個別指導) |
|---|---|
デメリット | ・指導する講師がプロ講師ではない場合がある ・学習環境や受験に関する情報が不十分な場合がある |
向いている人 | ・基礎固めをしたい人 ・学習計画を立ててほしい人 ・講師とコミュニケーションを取りながら講義を受けたい人 ・学校内容のフォローもしてほしい人 |
塾によって指導方針はさまざまですが、基礎的な内容からしっかり指導して学校の内申点を上げるような方針の塾もあります。
基礎的な部分から不安があり一から指導してほしい人や、自分で学習計画を立てるのが難しい人には、塾が向いています。また、塾は予備校と比べると講義あたりの生徒の人数が少なく、生徒に適宜質問をしながら講義を進めていくスタイルが多いので、講師と生徒の距離が近いのも特徴です。
講義の前後で講師とコミュニケーションを取りながら勉強を進めたい人にとっては、予備校よりも塾のほうが向いているでしょう。
ただし、塾では大学生を中心としたアルバイト講師が指導している場合もあります。アルバイト講師にもメリット・デメリットはありますが、アルバイト講師の指導力に不安を覚える場合は、予備校を選ぶほうがよいかもしれません。
なお、個別指導形式の塾では、授業を通じた生徒の進度や理解度に応じてカリキュラムを柔軟に変更してもらえます。生徒側からの要望に応じる形でのカリキュラム変更にも対応しているので、普段は学校内容の先取りをしつつ、テスト直前には学校内容のフォローもしてもらう、というような授業も可能です。
ただし、受験に向けて通わせる場所という観点で考えると、最新の受験情報や充実した学習環境という点において集団授業塾や予備校のほうが優れている場合が多いことは、念頭に置いておきましょう。
予備校に通う現役生と浪人生の1日のスケジュール
授業の取り方や選択コースなどによって異なる場合もありますが、現役生と浪人生の平均的な1日のスケジュールを紹介しましょう。
現役生のスケジュール
現役生のスケジュールは学校がある平日と休日で異なります。まず、平日のスケジュールの目安は以下のとおりです。
【現役生の平日スケジュール例】
時間帯 | 内容 |
|---|---|
8:30〜16:00 | 学校に通う |
16:00〜17:00 | 予備校に移動 |
18:00〜19:00 | 自習もしくは夕食 |
19:00〜22:00 | 授業 |
現役生の場合、平日は学校があるので、予備校に通うのは夕方からとなります。
予備校に到着したら、自分が選択している授業を1〜3講義ほど受講します。全国規模で校舎が設置されている予備校では校舎内に自習室を設けていることが多く、授業の空き時間に自習室を利用して予習や復習をおこないます。
現役生の休日スケジュールの目安は以下のとおりです。
【現役生の休日スケジュール例】
時間帯 | 内容 |
|---|---|
7:30〜8:00 | 朝食・支度 |
9:00〜12:00 | 授業 |
12:00〜13:00 | 昼食 |
13:00〜16:00 | 授業 |
17:00〜18:00 | 夕食 |
18:00〜22:00 | 授業 |
休日の場合、朝から夜までみっちり授業を受けるのが基本的な流れです。授業の終了時間によっては、就寝時間が深夜になる場合もあります。
浪人生のスケジュール
一方で、浪人生のスケジュールの目安は、以下のとおりです。
【浪人生のスケジュール例】
時間帯 | 内容 |
|---|---|
7:00〜8:00 | 朝食・支度 |
9:00〜12:00 | 自習や授業 |
12:00〜13:00 | 昼食 |
13:00〜17:00 | 自習や授業 |
17:00〜18:00 | 夕食・休憩など |
19:00〜22:00 | 自習や授業 |
浪人生は、週15〜20講義程度を受講することになり、基本的に食事以外は自習や授業でスケジュールが埋まるでしょう。
勉強漬けの日々を送る浪人生をサポートするために、浪人生専門の校舎を置いたり、寮制度を設けたりなど、勉強に集中できる環境づくりを実践している予備校もあります。
家族からのプレッシャーやスマートフォン、テレビの誘惑など、自宅での勉強を阻害する要素を断ち切れるのは、受験生にとっては嬉しいポイントです。
予備校を探す際の具体的な手順
次に、予備校を探す際の具体的な手順を解説します。
各予備校の情報収集
効率的な情報収集手段として、以下が挙げられます。
まずは、予備校の公式サイトで、合格実績やコース・費用といった情報を確認してみてください。
これらの情報を集めておくことで、予備校を比較しやすくなります。事前に志望大学、せめて国公立にするか私立にするかを決めておくと、情報収集がスムーズになります。
公式サイトの確認が済んだら、オンライン説明会に参加しましょう。公式サイトで確認できなかったこと、気になったことを直接確認するためです。もちろんオフラインの無料相談会に参加してもよいのですが、オンライン説明会のほうが、時間と手間をかけずに質問できます。あらかじめ質問リストを作っておくとよいでしょう。
比較サイトやSNSに投稿されている口コミ・意見にも目を通しましょう。公式サイトや担当者が表立って言いにくい情報を収集できる可能性があるからです。とくに口コミは、利用者の意見をチェックできることが多いため、目を通すべきでしょう。
複数予備校の比較検討
各予備校の情報をひととおり収集できたら、必ず比較しましょう。合格実績・料金・コース・指導形態・設備などが異なるためです。たとえば、2025年度の東京大学合格実績ひとつをとっても、各予備校で以下のように異なります。
【各予備校の東大合格者人数】
予備校 | 2025年度|東京大学合格実績 |
|---|---|
東進ハイスクール | 815名 |
秀英予備校 | 5名 |
栄光ゼミナール | 4名 |
※参考資料:東進|現役合格実績[2025年](2025年7月16日時点)
※参考資料:秀英予備校|大学受験合格実績(2025年7月16日時点)
※参考資料:栄光ゼミナール|2025年 大学入試合格実績(2025年7月16日時点)
合格者にこれだけの差がある場合、東京大学を志望しているのであれば、東進ハイスクールに入るのが一番よい選択に感じますよね。このように、予備校を比較することで見えてくることもあるのです。
各予備校の情報収集が完了したら、それぞれを比較、検討するのがよいでしょう。自分にとって最適な予備校がどこかを把握できます。
体験授業に参加
比較、検討が完了したら、もっとも気になっている予備校の体験授業に参加しましょう。自分にとって本当に最適な予備校であるかを確認するためです。
ネット上の情報だけでは「実際のところ、授業はどうなのか?」までは確認できません。授業を実際に体験し、指導方針・教材レベル・空気感を確認しましょう。
「自分に最適だ!」と感じたのであれば、その予備校を選べばよいですし、納得がいかなかった場合は、別の予備校の体験授業に参加するのがおすすめです。
もちろん、すべての予備校の体験授業に参加してから決めるのもおすすめです。納得がいくまで、参加するとよいでしょう。
費用や環境など!予備校選びのポイント
ここでは、予備校選びの際に確認すべきポイントを解説します。
志望大学に対応したコースの有無
予備校選びのポイントとして、志望大学に対応したコースの有無が挙げられます。大学ごとの受験科目数・出題傾向にあわせた学習が容易だからです。
極端な例を挙げますと、東京大学と早稲田大学では、出題される試験科目が大きく異なります。
【東京大学と早稲田大学の受験科目例】
東京大学(共通テスト) | 早稲田大学(法学部) | |
|---|---|---|
科目 | 国語×1
地理歴史・公民×2 数学×2 理科×2 外国語×1 情報×1(2025年度より東大の必須科目) | 外国語
国語 世界史・日本史・政治経済・数学のうちいずれか1つ |
※参考資料:東京大学|令和7(2025)年度東京大学入学者選抜(一般選抜)における(2025年7月15日時点)
※参考資料:早稲田大学|一般選抜(2025年7月15日時点)
そのため、早稲田法学部を受験するのであれば、理科や情報を勉強する必要はありません。数学が含まれているコースを選択するのは、無駄であることがわかります。国語や英語に特化したコースを選んだほうが、合格を効率的に目指せますよね。
また、同じ国公立大学、私立大学でも出題傾向が異なるケースもあります。基礎英語を重視する大学があれば、実用英語を重視する大学もあるなどです。
たとえば、実用英語を重視する国際基督教大学教養学部だと、以下のように英語の外部試験スコアの提出が求められます。
※① IELTS ② TOEFL iBT ③ 英検 ④ Cambridge English Qualifications ⑤ GTEC
上記は「英語外部試験利用入試」といい、英語外部試験のスコア、級を大学入試の合否判定に利用する入試です。もし国際基督教大学教養学部に入学したいのであれば、TOEFLなどのテストで高得点をとれる英語力、すなわち高いレベルの実用英語が求められます。
もちろん、ある程度の基礎英語は必要です。しかし、他大学の英語入試試験と先述した外部英語試験の出題傾向を比較すると、後者のほうが実用的な問題が多いでしょう。そうなると、実用的な英語を勉強したほうが合格に近づきます。
このように、同じ私立大学でも入試傾向が異なる、つまり求められる学力が異なる可能性があります。ケースバイケースではありますが、それぞれの大学に特化させたコースがあるのかを、予備校に直接質問してみるとよいでしょう。
いずれにせよ、志望大学に対応したコースの有無は、予備校選びにおいて非常に重要なポイントです。必ず確認してください。
豊富かつ優秀な講師陣の在籍
予備校選びにおいて、豊富かつ優秀な講師陣が在籍しているかも重要です。なぜなら質の高い講師は、成績向上と学習意欲の維持に大きく関わるからです。
たとえば、ある高校生が大学受験を目指して予備校に通うことになった場合、基礎が弱い教科は、「なぜそうなるのか」を丁寧に説明してくれる先生の存在が重要です。
そもそも基礎が弱いというのは、知識がないだけでなく、仕組みや考え方がわからない状態を指します。表面的に答えを覚えるのではなく、「なぜその答えになるのか」という過程を理解することで、知識が本当の意味で定着します。
これを繰り返すことにより成績の向上はもちろん、生徒は「わかった!」という達成感も得られるでしょう。学習意欲のアップにもつながります。生徒をこのように導いてくれる優秀な講師が在籍しているのであれば、その予備校を積極的に選ぶべきでしょう。
さらに、さまざまなレベルに対応できる講師が揃っていれば心強いです。自分のレベルが上がる前、上がった後でも的確な指導を期待できます。効率よく学力を伸ばせます。
ただし、パンフレットやホームページの情報だけでは講師の実力はわかりにくいこともあります。これに対しては、体験授業に参加して実際の教え方を確認したり、生徒や保護者の口コミを参考にしたりすることで、自分にあった講師陣かどうかを判断できます。
きめ細かな進路指導体制
予備校を選ぶ際、きめ細かな進路指導体制があるかどうかも、重要なポイントとして挙げられます。各生徒の目標や悩みに対し、具体的な道筋を示すことで、合格の可能性を高められるからです。
たとえば、志望校が決まっていない高校生がいたとして、その子が何となく「文系にしようかな」と考えていたとします。
もし進路指導が充実していれば、まず本人の得意科目や将来やりたいことを丁寧に聞き取ってくれます。適性や学力を踏まえた現実的な選択肢をいくつか提示し、模試の成績や志望校の入試傾向に基づき、どの時期に何をすべきかを明確に教えてくれるでしょう。
自身が迷わず努力できます。その結果、効率的な勉強の実現が可能です。
反対にサポートが少ないと努力の方向がズレ、時間だけが過ぎてしまうおそれがあります。予備校を選ぶ際は、個別面談の有無や頻度、指導実績の内容まで事前にしっかり確認することをおすすめします。
快適に学べる自習環境の整備
予備校を選ぶ際に、快適に学べる自習環境が整備されているかもポイントです。なぜなら、集中力を維持しやすい空間が、学習効率を大きく左右するからです。
たとえば、自習室に仕切りがあり、周囲の視線や雑音が遮られていれば、周りを気にせず目の前の課題に集中できます。さらに、机が広くて手元の教材を広げやすく、照明が十分に明るくて目が疲れにくい空間なら、長時間の勉強も苦になりません。
また、席の確保しやすさなども、ストレスの少ない学習環境に直結しています。混んでいていつも座れない自習室では、やる気があっても勉強のスタートすら切れません。このような状況が続くと、自然と予備校への足が遠のいてしまい、勉強時間が減るおそれがあります。
見学時に実際の自習スペースを自分の目で確認し、座席数、利用時間、空調、静かさなど細かい点もチェックしたうえで、自分にとって快適に勉強できるかどうかを判断材料にすることが重要です。
定期的な模擬試験の実施状況
予備校選びの際、定期的な模擬試験が実施されているかも確認すべきです。自分の実力や苦手分野を把握しやすくなるからです。
たとえば、学校の定期テストだけでは、本番入試のような形式やプレッシャーには慣れにくいものです。しかし、予備校で模試が定期的におこなわれれば、試験の雰囲気や時間配分のコツをつかめるようになります。
それだけでなく、模試の結果をもとに、点数が伸び悩んでいる教科を見つけて重点的に復習することができます。模試ごとの成績推移を見ることで、自分の努力がどう結果に結びついているかも実感できます。次に何をどのように勉強すればいいかが明確になり、学習の効率も上がるでしょう。
もちろん、模試を受けっぱなしにすると意味がありません。模試後に個別フィードバックや復習指導をしてくれる予備校を選ぶことで、受けるだけで終わらせず、確実に学力を伸ばすことができます。
通学の利便性・アクセス
予備校選びのポイントとして、通学の利便性・アクセスのしやすさが挙げられます。通学にかかる負担が少ないほど、学習への集中力を保ちやすくなるためです。
たとえば、自宅から電車で15分ほどの場所にある予備校と、乗り換えが複数回必要で通学に1時間かかる遠方の予備校では、毎日の移動時間や疲労感に大きな差が生じます。時間に関していえば、片道45分の差、往復で1時間半、週5通学と仮定すると7.5時間もの差があります。疲労のたまりやすさがまったく違うでしょう。
とくに季節や天候によっては通学が大きなストレスになり、モチベーションが下がる要因になるかもしれません。
さらに、体力に余裕がない日が続くと、授業に集中できず、学力の伸びにも影響が出るおそれがあります。アクセスがよい予備校なら、無理のない時間で通え、生活リズムも安定しやすくなります。
基本的には、通学時間がそれほどかからない予備校に通うのが無難です。
学習者のレベルにあわせたカリキュラム
予備校を選ぶ際は、学習者のレベルにあわせたカリキュラムが用意されているかを確認してください。理由は、自分に最適な内容を学ぶことで、学習効率を飛躍的に高められるからです。
たとえば、全体授業で高校の英語文法を学んでいるとします。すでに基本が身についている生徒にとっては復習の繰り返しとなり、時間の無駄に感じるでしょう。一方で、基礎が不安定な生徒が難しい応用問題ばかり扱うクラスに入ってしまうと、内容についていけず自信を失うおそれがあります。
このように、学力にあっていないカリキュラムでは、どちらの立場にとっても非効率です。レベル別に分かれた予備校では、たとえば「基礎徹底コース」や「応用発展クラス」などがあり、個々の学習状況に応じて最適な授業を受けられます。
その結果、理解度に応じた指導が受けられ、無理なく成績を伸ばしていけるのです。 ただし、最初のレベル分けがあっていないと逆効果になるため、学力診断テストや担当者との面談などを活用して、現状にもっともあったコースを選ぶ工夫が必要です。各予備校に問いあわせて、確認するとよいでしょう。
手厚いサポート体制
予備校選びとして、手厚いサポートがおこなわれているかもポイントとして挙げられます。勉強以外の悩みにも対応してもらえるからです。
そもそも受験勉強は、生活リズム、メンタル面の不安など、さまざまな悩みがついてまわるものです。高校生は多感な時期であるため、さまざまな悩みが出てきても不思議ではありません。
サポート体制が整っていなければ、生徒が困っている、または落ち込んでいることすら把握できないでしょう。放置した結果、勉学に悪影響が出てしまい、成績が落ち込む可能性があります。
しかし、手厚いサポート体制が整っていれば、このような事態の回避を期待できます。担当者が毎週面談をして声をかけることで、前向きな気持ちになりやすいでしょう。気持ちが安定すれば、勉学に集中しやすくなります。
利用者からの口コミ・評判
予備校選びのポイントとして、口コミや評判を確認することが挙げられます。なぜなら、実際に通った人の声を通じて、広告やパンフレットには載らないリアルな情報を得られるからです。 たとえば、駿台予備学校に通った方からは、以下のような口コミが寄せられました。
どのような学生に向いているのか、リアルな声を参考にすれば判断しやすいですよね。
ただし、口コミや評判を確認するときは、必ず複数を確認してください。ひとつの口コミを鵜吞みにするのではなく、複数の口コミを確認したうえで、総合的に判断することをおすすめします。
Ameba塾探しでは各予備校の口コミを記載していますので、ぜひ参考にしてください。
高校生・浪人生におすすめの予備校を紹介
それぞれの特徴を解説するので、ぜひ参考にしてください。
「駿台予備学校」はAI技術を導入した効率的な学習を実現
駿台予備学校が導入したAI教材の「atama +」は、一人ひとりの学習理解度を分析しながら演習します。
単に苦手問題を出すのではなく、問題の量や頻度、順番までも細かくナビゲートするので、最短最速で基礎から応用力を身につけられます。また、重要なことをピンポイントで提供してくれるので、効率的な学習が可能です。
さらに、志望校合格を視野に入れたオリジナルテキストと校内模試によって、学力の底上げをおこないます。
過去問や最新の入試傾向を分析したテキストにより、入試に必要なポイントを重点的に学習し、理解度を確認するために、本番さながらの模試を実施。
模試後は、採点や解説などのフィードバックを受けられるので、モチベーションを落とすことなく積極的な学習に取り組めます。
「河合塾」は弱点の底上げを目指した受験対策ができる
80年以上にわたって大学入試を研究している実績とデータに基づき、受験合格に必要なエッセンスを凝縮した授業を受けられます。
近年の入試では思考力を問う問題が多く出題されており、過去問を解くだけでは対策が不十分です。
河合塾では、なぜその答えが導き出されるのかを論理的に考えるので、応用問題にも対応できる思考力と実践力が身につきます。
予備校は講師との距離感が遠く、質問しにくいと思われがちですが、河合塾の場合は講師室がオープンスペースになっているので、休憩時間を活用して講師とコミュニケーションが取れる環境が整っています。
「代々木ゼミナール」は2種類の授業形式で徹底理解を追求
教室でおこなう対面授業では、生徒の反応や理解度を考慮しながら進めているので、一般的な予備校よりも講師とのコミュニケーションが取りやすいのが魅力です。
個別ブース授業では、対面授業の映像を何度も繰り返し視聴できるので、不明点がそのままにならず、理解度を深められます。また、映像を倍速で流せることから、短時間でも授業内容を網羅できるのもポイント。
さらに「SAPIX YOZEMI GROUP 模試」を開催しており、本番さながらの模試が受けられます。志望校の合格判定や細かいフィードバックが得られるので、改善点が明確になることも嬉しいポイント。
2種類の授業で基礎項目を確認し、模試によって応用力や実践力の定着させる仕組みが整っています。
「東進ハイスクール」は短時間で効率的な学習ができる
ITを活用した最先端の学習方法が特徴で、一般的な学習塾が1年かけて取り組む内容を最短2週間から3か月で学習することが可能。最重要事項を学べるのはもちろん、受験対策の遅れを取り戻したい方にもおすすめです。
東進ハイスクールでは、志望校合格から逆算をした学習計画をもとに、目標を確認しながら日々の学習に取り組みます。
小さな成功体験がモチベーションの向上につながり、自立的な学習意欲が身につくことも魅力。
また、記述・論述問題に対応できるよう、 国立大学や難関私立大学の受験を想定した「記述型答案講座」を実施。添削から復習、添削指導といったサイクルをおこなうことで、思考力が問われる問題にも強くなれるのです。
「四谷学院」は個人能力を高めるダブル教育を受けられる
科目別能力授業では、受験勉強の基盤となる理解力を養います。科目ごとのレベル判定によって振り分けられたクラスで授業をおこなうので、一人ひとりの学力に応じた学習ができます。
55段階個別指導では、入試問題を分析して作成された「55テスト」をおこないます。成績によって次のステージに進めるので、予習と復習を繰り返すサイクルが習慣化され、応用力や実践力が身につきます。
「勉強方法や学習計画が立てられない」「成績が悪くて自信がない」など受験生特有の悩みに全力で向き合ってくれるので、常に高いモチベーションで学習できることも魅力です。
予備校に関するよくある質問
最後に予備校に関してよくある質問をまとめました。予備校に通うことを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
Q.予備校はいつから通い始めたらいいですか?
予備校に通い始めるタイミングは人によって異なるため、「この時期がベスト」とは一概にいえません。現在の成績や志望校、生活スタイルなどを踏まえて、自分にあった時期を見極めることが大切です。
たとえば、思うように成績が伸びない場合や苦手科目がある場合には、早めに通い始めるのがおすすめです。とくに難関大学を志望するのであれば、高校1・2年生のうちから予備校に通うとよいでしょう。学習習慣がなかなか定着しない場合も、予備校に通うことで改善しやすくなります。
部活や習い事で忙しい場合は、それらが落ち着いてから通い始めるのもひとつの方法です。ただし、長期間通うほど費用はかさむため、大学受験までにかかる総額を考慮しながら無理のないタイミングを見極めましょう。
Q.オンライン予備校とは何ですか?
オンライン予備校とは、通学せずに自宅や好きな場所で授業を受けられる予備校のことです。パソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスとインターネット環境があれば、場所を選ばず学習できます。
通学時間がかからないため、部活や習い事で忙しい方でも効率的に勉強できます。また、地域に関係なく有名講師や難関校対策に強い予備校を選べるので、とくに地方在住の方は、選択肢を大きく広げることができるでしょう。
また、一般的に通学型の予備校よりも費用が抑えられる傾向にあり、コスト面でもメリットがあります。
Q.予備校に通わないと大学に合格できない?
予備校に通わなくても合格することは十分可能です。反対に、予備校に通ったからといって合格が保証されるわけではありません。
ただし、予備校を利用することで、現在の成績や志望校にあわせた効率的な学習プランを立てやすくなります。わからない部分をすぐに質問して解決できる点も、大きなメリットです。また、一緒に勉強する仲間ができることで、モチベーションを維持しやすい環境も得られることがあるでしょう。
志望校に合格できるかは、予備校に通うかどうかで決まるものではありませんが、今の成績や学習方法に不安がある場合は、検討してみましょう。
Q.予備校の寮や学生マンションはありますか?
はい、あります。予備校が管理・運営する寮があるケースや、提携する寮や学生マンションが用意されているケースが多くあります。予備校の寮や近隣の学生マンションに入居すると、学習に集中できる環境が整うだけでなく、食事や健康管理といった生活面でのサポートも受けられるのがメリットです。
なお、予備校が直接運営している寮は、主に浪人生を対象とする場合が多く、学習に専念できるよう厳しいルールが設けられていることがあります。一方、提携寮や学生マンションでは、大学生や社会人も一緒に暮らしているケースがあり、施設ごとに生活ルールは異なります。
予備校の特徴や塾との違いを理解し、最適な学習環境を選ぼう
塾・学習塾は苦手分野の克服や学校の成績アップが目的なのに対し、予備校は大学受験に特化した授業を受けられます。
予備校は講師と距離があると思われがちですが、おすすめの予備校のなかには、生徒に手厚いサポートをおこなうところもあります。
予備校と塾の特徴を踏まえ、ご自身の目的にあう学習環境を選びましょう。