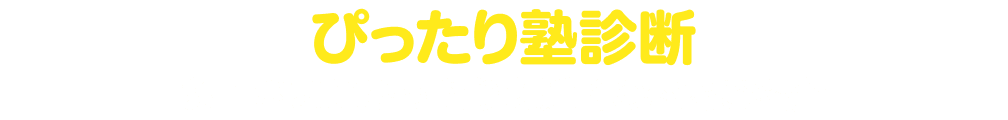「毎日ちゃんと勉強しているのに、成績が上がらない」「もっと成績が上がる勉強法ってないのかな?」と悩んでいる高校生は多いのではないでしょうか?
高校生になると、中学生の頃よりも勉強の難易度が上がり、科目数も増えます。そのため、単に時間をかけて勉強するだけでは、成績を上げるのは難しくなります。
大切なのは、高校の学習にあわせた効率的な勉強法を身につけることです。
そこでこの記事では、高校生が「勉強しても成績が上がらない」と感じる原因や、定期テストの成績を上げるための具体的な勉強法などについて解説します。
今の自分の勉強法を見直し、効率的に成績を上げましょう。
- 【高校生】成績が上がらない主な原因
- 勉強時間が足りない
- 間違った勉強法を続けている
- アウトプットの機会が不足している
- 基礎が十分に身についていないのに、応用問題に挑戦している
- すでに理解している内容ばかりを繰り返し勉強している
- 計画性がなく、場当たり的に勉強している
- 高校生向け成績を上げるための勉強法【基礎】
- 学校の授業を活用する|予習・復習のやり方
- ノートの取り方・使い方を見直す
- テスト範囲の勉強は「逆算」で考える
- テスト15日前
- テスト2週間前から1週間前頃
- テスト1週間前から3日前頃
- テスト3日前から直前
- 高校生向け成績を上げるための勉強法【応用】
- 科目別に対策する
- 英語
- 数学
- 国語
- 社会
- 理科
- 隙間時間を活用する
- 大学受験を見据えた定期テスト対策をする
- 受験勉強は戦略的に取り組む
- 【高校生向け内申点対策】学校の成績や評定平均を上げる方法
- 提出物・課題の提出を徹底する
- 授業や小テストに意欲的に取り組む
- 先生に好印象を残すコミュニケーションを心がける
- 高校生がやってはいけない勉強法
- 「とにかく長時間勉強する」は逆効果
- わからない問題を放置して先に進む
- 「まとめノート」を作るだけで満足してしまう
- 高校生の成績は「正しい勉強法」と「継続」で上げよう!
【高校生】成績が上がらない主な原因
勉強を頑張れば頑張るほど、結果が出ないことへの焦りや悩みは本当につらいものです。
確実に成績を上げるためにも、まずは成績が上がらない主な原因を知ることから始めましょう。
勉強時間が足りない
高校では学習科目の数と範囲が大幅に増加するため、中学時代と同じ勉強時間では足りません。実際に、高校の学習量は中学の5~10倍になるともいわれています。
また、高校の学習内容は、各学年の知識が次の学年の土台となる「積み重ね式」の構造です。そのため、一部の理解が不十分だと、その後の学習内容の理解が難しくなり、一度遅れを取ると挽回が難しくなります。
中学時代はテスト直前の詰め込み学習で対応できた人も、高校ではそのやり方は通用しないため、日々の学習を着実に積み重ねて知識を定着させることが重要になります。
間違った勉強法を続けている
勉強時間を十分に確保しても、勉強法が間違っていると、なかなか成績は上がりません。
アウトプットの機会が不足している
間違った勉強法のよくある例として、教科書や参考書を読むだけで満足し、実際に問題を解くなどのアウトプットの機会が不足しているケースが挙げられます。「覚えたはずなのに、テストで思い出せない」という経験は、アウトプット不足が原因かもしれません。
知識をインプットすることも大切ですが、知識を使う練習をしなければ、記憶は時間とともに薄れてしまいます。
学んだことを自分の言葉で説明したり、問題演習を繰り返したりするなど、意識的にアウトプットの機会を増やすと、知識が定着し、本当に使える力が身につきます。
基礎が十分に身についていないのに、応用問題に挑戦している
高校の勉強において、とくに重要なのが基礎固めです。英語の単語や文法、数学の公式、社会の用語といった基礎的な知識を確実に理解することが、その後の応用力を養ううえで重要な土台となります。
基礎が十分に身についていない状態で応用問題に挑戦しても、解けないことが多く、結果として学習へのモチベーションが低下してしまうことも少なくありません。
まずは焦らずに基礎をしっかりと固め、段階的に問題の難易度を上げていくことが、学力向上への近道です。
すでに理解している内容ばかりを繰り返し勉強している
勉強の目的は「わからないことをわかるようにする」ことです。しかし、意外にもこの目的を見失い、すでに理解している内容ばかりを繰り返して学習しているケースは少なくありません。
自分のレベルよりも簡単な問題ばかりを解いていたり、得意な教科や分野の勉強に偏っていたりするのが典型例です。
「できた!」という安心感よりも、「できなかったことができるようになった!」という成長を大切にしましょう。
計画性がなく、場当たり的に勉強している
学習計画を立てずに、場当たり的に勉強すると、非効率な学習になる可能性が高くなります。「今日は何を勉強しようか」と考えているうちに時間が過ぎてしまったり、集中力が途切れてしまったりします。
このような状況を避けるためには、事前に学習計画を立てることが重要です。また、勉強する目的や志望大学が明確でない場合、あれもこれもと手を出しすぎてしまい、広く浅い学習になる傾向があります。
できるだけ早く志望大学を決めることで、目標が定まり、日々の学習で何を優先すべきかが見えてきます。
高校生向け成績を上げるための勉強法【基礎】
高校の勉強は範囲も広く、難易度も上がるため、いざ勉強を始めようと思っても、何から手をつけたらいいのかわからない高校生も多いでしょう。
もしかしたら、その原因は「勉強の土台」となる基礎的な部分を見落としているからかもしれません。難しい応用問題に目が行きがちですが、実はどんな科目でも、しっかりとした基礎力なくして成績を上げることは難しいのです。
ここでは、まず確実に押さえておきたい「成績アップの基礎固め」につながる勉強法を紹介します。
学校の授業を活用する|予習・復習のやり方
学校の授業内容を確実に理解し、知識を定着させるためには、予習と復習が大事です。予習と復習をセットでおこなうことで、学習効果をより高められます。
予習は、次の授業範囲の教科書に事前に目を通し、大まかな内容を把握しておきましょう。授業中の説明が理解しやすくなり、学習内容がスムーズに頭に入ってきます。
復習は、週末にまとめておこなうのではなく、毎日継続することが重要です。その日に学んだ内容を振り返り、関連する問題集の該当範囲の問題に挑戦してみましょう。
理解が曖昧な箇所や解けない問題があれば、教科書やノートを見返して疑問点を解消してください。日々の積み重ねによって、知識は確実に定着します。
ノートの取り方・使い方を見直す
高校生が成績を上げるためには、ノートの取り方と使い方を見直すことも大事です。
あとから見返してテスト勉強に活用できるノートを作成しましょう。必ずしも時間をかけて清書した「まとめノート」を作る必要はありません。
たとえば、ノートを見開きで使い、左ページには「黒板に書かれた授業内容」や「先生の説明」を記述し、右ページには「関連する重要なポイント」や「疑問点」、「補足情報」などを書き込む方法があります。授業ノートがそのまま復習やテスト対策の教材となるため便利です。
教科ごとにノートを分けて日付を記入したり、重要な箇所にマーカーで印をつけたりすると、後から情報を見つけやすくなります。
効率的なノートの取り方・使い方を意識すれば、ノート作成に時間を取られすぎることなく、問題演習や暗記など、ほかの学習に十分な時間を充てられます。
テスト範囲の勉強は「逆算」で考える
高校の定期テストで着実に成果を上げるためには、「逆算思考」を取り入れた学習計画が有効です。逆算思考とは、テスト当日をゴールとし、そこから遡って各時期に取り組むべき学習内容を設定していく考え方です。
テスト15日前
まず、テスト準備期間の開始時(テスト15日前)には、各科目で具体的な目標点数を設定しましょう。「数学Ⅰで80点」「英語で90点」のように目標を明確にすることで、達成のために何をすべきかが見えてきます。
学習計画は完璧に作り込みすぎず、あくまで「目安」として柔軟に考えましょう。勉強を進めるなかでズレが生じるのは当然なので、その都度、焦らずに計画を見直していくことが大切です。
テスト2週間前から1週間前頃
テスト2週間前から1週間前頃には、多くの科目でテスト範囲が発表されます。全体の学習範囲を把握し、自分の苦手な分野や理解が不十分な箇所を特定してください。
テスト1週間前から3日前頃
テスト1週間前から3日前頃にかけては、特定した苦手分野を集中的に学習します。一度で完璧を目指すのではなく、繰り返し復習することが知識の定着に効果的です。
テスト3日前から直前
最後に、テスト3日前から直前にかけて、学習内容全体の最終確認と、どうしても覚えきれない箇所の重点的な暗記をおこないます。
このように、ゴールから逆算して計画的に学習を進めることで、効率的にテスト対策をおこなえます。
高校生向け成績を上げるための勉強法【応用】
「基礎的な勉強はひと通り押さえたはずなのに、模試や実力テストになると、あと一歩点数が伸び悩む…」そんな経験はありませんか?
あるいは、「もっと上のレベルを目指したいけれど、今の勉強法で本当に通用するんだろうか?」と、目標に対して壁を感じている高校生もいるかもしれません。
基礎固めができた次のステップは、知識を自在に使いこなし、応用問題にも対応できる「本物の学力」を身につけることです。それは、ただ難しい問題に手当たり次第に取り組むのとは少し違います。
ここでは、基礎力を土台にして、さらに成績を上げるための「応用的な勉強法」を紹介します。
科目別に対策する
特定の科目で成績が伸び悩んでいる場合、その科目の特性にあわせた学習方法へ切り替えることが重要です。教科ごとに効果的なアプローチは異なります。
英語
英語では、出題範囲の長文を丁寧に読み込み、使われている英単語や文法事項を確実に記憶することが基本となります。
数学
数学においては、まず公式や定義を正確に暗記し、そのうえでテスト範囲の問題を繰り返し解くことで、解法をスムーズに引き出せるようにしましょう。
国語
国語では、現代文は文章中の不明な語句を辞書で確認しながら読解を進め、内容への理解を深めます。古文や漢文は、重要単語や文法ルールの暗記が重要です。
社会
社会(歴史や地理・公民など)は、まず出来事や制度の大きな流れをつかみ、その後に詳細な人名や年代、用語などを関連付けて覚えていくと効率的です。
理科
理科では、科目によって学習のポイントが異なります。生物や化学は、教科書を繰り返し読み込み、知識を正確に暗記することが中心となります。一問一答形式の問題集や授業プリントも活用しましょう。
一方、物理は公式を暗記したあと、さまざまな問題を繰り返し解く勉強法が効果的です。
隙間時間を活用する
日々の生活のなかには、意識していないだけで多くの「隙間時間」が存在します。
たとえば、通学中の電車やバスでの移動時間、授業の合間の短い休憩時間、帰宅後の夕食前やお風呂の前、寝る前の時間など、工夫次第で貴重な学習時間に充てられます。
「たった数分で何ができるの?」と感じるかもしれませんが、実はこの短い時間こそ、集中して暗記系の学習に取り組むのに適しています。
隙間時間の具体的な活用法として、覚えたい内容を小さな紙にまとめた「暗記メモ」を作成し、常に持ち歩きましょう。
日本史なら年代・出来事・人物、英語なら単語や短いフレーズなど、5分程度で区切りよく学習できる量を書き出しておけば、いつでもどこでもメモを取り出して確認することが可能です。
このように隙間時間を積み重ねることで、まとまった学習時間が取りにくい日でも、着実に知識を増やせます。
大学受験を見据えた定期テスト対策をする
高校の学習内容は、中学時代と比較して各教科がより専門的に細分化されます。
たとえば、国語は現代文・古文・漢文に、理科は物理・化学・生物・地学に分かれるため、試験科目数が増加し、学習範囲も広がります。そのため、テスト直前の詰め込み学習だけでは対応が難しくなるでしょう。
定期テスト対策では、単なる丸暗記ではなく、学習内容を理解するまで繰り返し勉強することが重要です。定期テストでしっかり勉強しておくと、大学受験の準備にも役立ちます。大学入試では、高校での学習内容を深く理解し、応用する力が問われるためです。
高校の学習範囲は広く、学習量も多いため、どうしてもわからない箇所や苦手な分野が出てきます。定期テストで高得点を目指すなら、テスト範囲のすみずみまで理解を深め、苦手な箇所を残さないレベルまで仕上げておくことが重要です。教科書やノート、問題演習などを活用し、理解できるまで繰り返し学習に取り組みましょう。
解き方がわからない問題が出てきたら、決してそのままにせず、学校の先生に積極的に質問してください。先生に質問するのは気が引ける人も多いですが、わからないところを聞くのは恥ずかしいことではありません。
疑問点を放置すると、定期テストの点数だけでなく、将来の大学入試の結果にも影響を及ぼす可能性があります。
受験勉強は戦略的に取り組む
大学受験の勉強は、単に長時間努力するのではなく、志望校の入試科目や出題傾向を調べ、計画的に進めることが大切です。
早い段階で志望校と受験科目を決めると、勉強に集中する時間を十分に確保でき、ほかの受験生よりも一歩リードできます。入試の出題傾向をじっくり分析したり、過去問を解いたりして、本番を意識した演習をおこなうことで、合格の可能性を高めることが可能です。
苦手科目に対しても、「この科目を克服すれば合格に大きく近づける」という具体的な目標意識が生まれ、学習へのモチベーションを維持しやすくなります。
模擬試験は、定期テストと違って出題範囲が広いため、短期間の詰め込み学習では十分な対策ができません。日々の学習の積み重ねが得点力につながります。
模試の結果は、志望校合格という目標に対して、現時点での自分の実力や立ち位置を客観的に把握する指標になるため、積極的に受けるようにしましょう。
なお、模擬試験は受けて終わりではなく、受験後の復習が大事です。間違えた問題や理解が曖昧だった部分をしっかり復習することで、次の学習に活かせます。
【高校生向け内申点対策】学校の成績や評定平均を上げる方法
大学の受験方式が多様化するなかで、学校の成績や評定平均(内申点)の重要性を感じている高校生は多いのではないでしょうか?
普段の授業態度や提出物、定期テストの結果が内申点に影響すると思うと、プレッシャーを感じるものです。「具体的に何をどう頑張れば、成績や内申点が上がるんだろう?」と、具体的な方法を探している方もいるかもしれません。
実は、日々のちょっとした意識や取り組み方を変えるだけで、学校の成績や内申点を着実にアップさせることが可能です。
ここでは、内申点アップにつながる具体的な対策や、成績を効果的に上げるためのヒントを紹介していきます。
提出物・課題の提出を徹底する
学校の成績や評定平均を上げるためには、授業で課されるプリントやレポート、課題といった提出物を、期限内に必ず提出しましょう。
ただ期限を守って提出するだけでなく、内容も評価の対象となることを忘れてはいけません。一つひとつの課題に真剣に取り組み、丁寧に作成してください。
カラーペンを使って重要な箇所をわかりやすくしたり、自分なりに情報を整理したりするなど、見やすさや理解度を高めるために工夫することも学習意欲を示すうえで効果的です。
授業や小テストに意欲的に取り組む
学校の成績の評価は、テストの点数だけでなく、日々の授業への取り組み方も重視されます。
授業に意欲的に取り組み、疑問点があれば積極的に質問することが大切です。たとえテストの成績がよくても、授業態度が悪ければ、成績が下がる可能性があります。
また、出席状況も評価に含まれるため、できるだけ遅刻や欠席をしないようにしましょう。音楽や美術、体育などの実技教科が不得意でも、あきらめずに真面目に取り組む姿勢が大事です。
英単語や漢字の小テストなど、日々の小テストの結果が内申点に影響を与えることもあります。一つひとつの学習の機会を大切にしましょう。
先生に好印象を残すコミュニケーションを心がける
学校の成績の評価、とくに評定平均(内申点)は、主に定期テストや小テストの結果で決まるため、必ずしも先生に気に入られる必要はありません。
しかし、授業態度や提出物の評価など、一部の評価項目は先生の判断にゆだねられます。そのため、学習に真摯に取り組み、先生によい印象を与えることは、結果として評価を高めるうえでプラスに働く可能性があります。
先生に媚を売る必要はありませんが、その教科に一生懸命真面目に取り組んでいる姿勢を見せることは大事です。たとえば、積極的に授業に参加したり、疑問点を質問したりする自主的な学習態度は、先生に好印象を与え、内申点アップにつながる可能性があります。
高校生がやってはいけない勉強法
一生懸命勉強に取り組んでも、なかなか結果に結びつかない場合、もしかすると知らず知らずのうちに「非効率な勉強法」や「成績アップを妨げるやり方」に陥ってしまっている可能性があります。
ここでは、せっかくの努力を無駄にしないために、「高校生がやってはいけない勉強法」を紹介します。
自分に当てはまるものがないかチェックして、より効果的な学習習慣を身につける参考にしてください。
「とにかく長時間勉強する」は逆効果
「長時間机に向かっていれば、いつかは成果が出るはず」と信じて、ひたすら時間をかけて勉強しようとする方もいるかもしれません。
しかし、ただ時間を長く費やすだけの学習は効率的とはいえず、むしろ逆効果になることもあります。
人間の集中力には限界があり、一般的に持続するのは90分程度です。
そのため、何時間も連続して勉強しようとすると、途中で集中力が途切れてしまい、学習内容が頭に入りにくくなります。勉強時間を区切って集中し、適度に休憩を挟みましょう。
タイマーなどを活用して学習時間を設定し、合間に短い休憩を入れてください。ときには友だちと遊んだり、趣味の時間を持ったりするなど、自分にあった方法でリフレッシュすることも、長期的に学習意欲を維持するためには大切です。
また、長時間の学習を優先するあまり睡眠時間を削ってしまうと、日中の集中力や記憶力が低下し、学習効率が悪化してしまいます。質の高い学習のためには、十分な睡眠時間の確保も大切です。
わからない問題を放置して先に進む
勉強を進めていると、どうしても理解できない問題や、つまずいてしまう箇所が出てくるものです。
自分一人で解決できない場合は、遠慮せずに先生や友だちに質問しましょう。 友だちと教え合うことも、互いの理解を深めるうえで効果的です。
人に説明できるレベルまで理解することで、知識はより確実なものになります。わからないまま放置してしまうと、その知識が土台となる次の学習内容の理解も難しくなり、結果として学習全体の効率を下げてしまう可能性があります。
間違えた問題や理解できなかった箇所に直面したときは、単に答えを書き写して終わりにするのではなく、「なぜ間違えたのか」「どこが理解できていなかったのか」という原因を徹底的に分析することが大切です。
「まとめノート」を作るだけで満足してしまう
丁寧にまとめられたノートを見ると、達成感があり、勉強した気になる方もいるかもしれません。
しかし、単に教科書や黒板の内容をきれいに書き写すだけの「まとめノート」作りは、学習効果の観点から見ると、あまり効率的とはいえません。
まとめノート作りは、本来の目的である「知識を深く理解し、記憶に定着させる」ことから外れ、ノートを完成させること自体が目的となってしまうことがあるためです。
定期テスト対策や受験勉強のように、限られた時間のなかで最大限の成果を出す必要がある場合、見た目の美しさにこだわったノート作成に時間を費やすよりも、その時間を使って基礎的な知識を徹底的に固めたり、重要なポイントを確実に暗記したりするほうが学習効率は高まります。
ノートはあくまで学習を助けるツールの一つです。目的と手段を混同せず、本当に学力向上につながる使い方を意識しましょう。
高校生の成績は「正しい勉強法」と「継続」で上げよう!
この記事では、高校生が成績を上げるための方法について、成績が上がらない主な原因の分析から、基礎・応用の勉強法、内申点への対策まで幅広く解説しました。
まずは、成績が伸び悩んでいる原因を正しく把握しましょう。勉強時間が不足しているのか、勉強法そのものに問題があるのか、原因を特定することがスタートラインになります。
そのうえで、インプットとアウトプットのバランスを考え、基礎を固めてから応用に進む「正しい勉強法」を継続しましょう。やみくもに机に向かうのではなく、予習・復習の習慣化など、効率的に知識を定着させるための工夫も必要です。
まずは「これなら自分にできそう」と思える勉強法を一つ見つけて、続けてみてください。新しい勉強法を試しても、すぐには結果が出ず、焦りを感じることもあるでしょう。学んだ知識が「わかる」から「使える」に変わるまでには、少し時間が必要だからです。
しかし、焦らず一つひとつの課題を着実に乗り越えていけば、その努力は必ずテストの点数という成果に結びつきます。
もし自分一人での勉強に行き詰まりを感じたら、塾でプロのアドバイスをもらうのもおすすめです。
個別指導形式の塾なら、自分専用の学習計画を立ててもらえるうえ、学校の授業でわからなかったこともその場で質問しながら解決できるため、効率的に学習を進められます。
最適な学習環境で成績アップを目指しましょう。