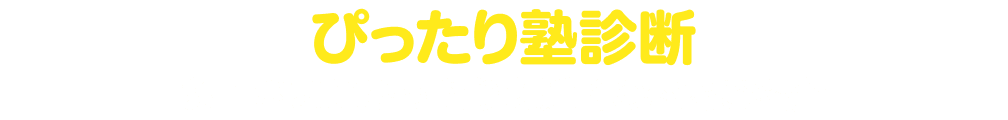「自分の勉強時間はほかの人と比べて短いんじゃないか…」と気になっている中学生や、子どもの勉強時間が短いのではないかと心配している保護者の方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、中学生の平均的な勉強時間や、効率的かつ質の高い勉強をおこなうための方法を紹介します。
勉強時間を伸ばすためのコツや保護者ができるサポートの具体例も紹介するので、勉強時間が足りないと感じている中学生や保護者の方は参考にしてください。
- 中学生の平均的な1日の勉強時間はどのくらい?教育機関が推奨する目安
- 中学生の成績アップに必要な勉強時間の目安は?
- テストに向けた勉強時間の目安|平日と休日の違い
- 高校受験に向けた勉強時間の目安|学年別の平均勉強時間
- 勉強時間が足りない中学生におすすめ!効率と質を高めるコツ
- ①弱点や苦手科目を洗い出して優先順位をつける
- ②明確な目標を決めて学習スケジュールを立てる
- ③毎日決まった時間に勉強して習慣化する
- ④問題集やテストでアウトプットする
- ⑤わからない箇所は理解するまでやる
- 中学生が勉強時間を増やすために心がけたいポイント
- 毎日の時間の使い方を客観的に把握する
- 隙間時間を有効に活用する
- 規則正しい生活リズムを身につける
- 集中できる環境で勉強する
- 中学生の子どもの勉強時間を伸ばすために親ができるサポート
- ポジティブな声かけをする
- 生活面や体調管理のサポートをする
- 学習環境を整える
- 勉強に関する悩みや相談を一緒に考える
- 中学生は勉強時間の長さにこだわらず、効率や質を高めることが大切
中学生の平均的な1日の勉強時間はどのくらい?教育機関が推奨する目安
文部科学省が小学5年生から高校3年生を対象におこなった調査によると、中学生の授業以外の学習時間でもっとも多かったのは、中学1〜2年生で1時間以上2時間未満、3年生で2時間以上3時間未満です。
【学校外の学習時間】
| 授業時間以外の1日の勉強時間 | 学年別の回答割合 ※小学5〜6年生、高校3年生の回答割合を除く | ||
|---|---|---|---|
| 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 | |
| まったく、ほとんどしない | 14.3 | 17.1 | 8.5 |
| 30分未満 | 11.9 | 12.2 | 5.6 |
| 30分以上1時間未満 | 20.0 | 18.1 | 9.6 |
| 1時間以上2時間未満 | 29.7 | 28.9 | 23.1 |
| 2時間以上3時間未満 | 17.7 | 17.8 | 28.4 |
| 3時間以上 | 5.0 | 4.6 | 23.6 |
| 無回答 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
出典:文部科学省「4.学校外の学習時間について」
一方、「学年×10分+10分以上」が授業以外の勉強時間として推奨する教育機関もあります(※)。
義務教育期間を9年間と考えると、中学1年生は7学年、中学2年生は8学年、中学3年生は9学年になり、計算すると以下の勉強時間になります。
【中学生の推奨勉強時間】
| 学年 | 1日あたりの推奨される勉強時間の目安 |
|---|---|
中学1年生 | 80分 |
中学2年生 | 90分 |
中学3年生 | 100分 |
※参照:北海道教育委員会 時間の目安を決めて 子どもの生活リズムを整える!
中学生の成績アップに必要な勉強時間の目安は?
中学生の成績アップに必要な勉強時間は、テストや受験など目的によっても異なります。
次より一般的な目安を紹介していきます。
テストに向けた勉強時間の目安|平日と休日の違い
テストに向けた勉強時間の一般的な平均は、平日2〜3時間程度、休日6~8時間程度です。
テストがおこなわれる2〜3週間前から勉強を始めるケースが多い傾向にあります。
なお、中学生の定期テスト対策については下記の記事で詳しく解説しています。教科別の勉強方法やスケジュールの立て方についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
高校受験に向けた勉強時間の目安|学年別の平均勉強時間
高校受験に向けての勉強時間は、学年や時期によっても異なります。とくに夏休みや受験前の9〜12月は勉強時間が長くなる傾向にあります。
なお、Ameba塾探しがおこなった勉強時間に関するアンケートによると、高校受験のために勉強した1日の平均時間は以下の結果になりました。
【高校受験のために勉強した1日あたりの平均時間】
| 1日あたりの平均勉強時間 | 割合(%) | |
|---|---|---|
平日 | 休日 | |
30分未満 | 2.3 | 2.7 |
30分~1時間 | 10.4 | 5.0 |
1時間~2時間 | 30.5 | 14.3 |
2時間~3時間 | 31.7 | 22.0 |
3時間~4時間 | 12.3 | 20.5 |
4時間~5時間 | 7.3 | 12.7 |
5時間~6時間 | 1.2 | 8.1 |
6時間~7時間(※) | 2.3 | 5.8 |
7時間~8時間 | - | 3.5 |
8時間~10時間 | - | 3.5 |
10時間以上 | - | 1.9 |
上記のとおり1日の平均勉強時間は、平日・休日ともに2〜3時間が多い傾向にあります。1日どのくらい勉強するかは、目指している志望校や学習の状況によっても変わるでしょう。
受験を目指す場合、いつから勉強するべきかについては以下の記事で詳しく紹介しています。併せてご覧ください。
勉強時間が足りない中学生におすすめ!効率と質を高めるコツ
勉強時間が足りないと感じると、長時間勉強しようとしてしまうかもしれません。しかし、勉強時間が足りないときこそ、一度状況を客観的に把握し、効率的かつ質の高い勉強方法を取り入れることが大切です。
効率的な勉強をおこなうためには、以下の流れを意識しましょう。
それぞれ詳しく紹介します。
①弱点や苦手科目を洗い出して優先順位をつける
テストや受験勉強までは時間が限られているため、自分の弱点や苦手科目を明確にし、何にどれくらいの時間を割いて勉強するかを決めることが大切です。
すべての科目の全範囲を勉強できれば理想ですが、範囲や科目を広げすぎると、すべてが中途半端になってしまいます。
たとえば、「英語が苦手」「数学が苦手」など、抽象的なものではなく「英語の文法は得意だけど、長文読解が苦手」「数学は、方程式はわかるけと、関数が理解できていない」など、細かく分類して弱点を洗い出しましょう。
洗い出すことで、優先すべき分野が見えてきます。苦手科目や分野が克服できれば、効率的に成績やテストの点数を伸ばせるでしょう。
②明確な目標を決めて学習スケジュールを立てる
効率よく勉強を進めるためには、「何を、いつまでに、どの程度できるようになるか」目標を設定し、逆算して学習スケジュールを立てることが重要です。
目標は、受験や期末テストなどの中長期的な目標と、直近の小テストなど短期的な目標に分けて考えましょう。
たとえば、「来月の定期テストで数学を15点アップさせる」という具体的な目標を立てれば、毎週何をすべきか、どれだけ時間を確保すべきかが把握しやすくなります。
スケジュールは理想ではなく、達成可能な現実的なものにすることが大切です。
③毎日決まった時間に勉強して習慣化する
勉強を継続するためには習慣化が重要なポイントです。
勉強をおこなうときに「やる気」や「モチベーション」を頼りにする人がいるかもしれません。しかし、「今日は6時間勉強を頑張ろう」と思っていても、ついテレビなどを見てダラダラしてしまい、先延ばしにしてしまうことも多いのではないでしょうか。
毎日決まった時間に机に向かう習慣が身につけば、勉強が当たり前になり、決まった時間に勉強していないと逆に落ち着かなくなってきます。「頑張ろう」と意気込まなくても、自然と勉強モードに切り替わり、集中して勉強できるようになるでしょう。
たとえば、学校から帰宅後の1時間、夕食後の20分、寝る前の30分など、生活のリズムにあわせて無理なく取り入れてみてください。
習慣化するコツは、勉強時間の長さではありません。毎日同じタイミングで繰り返すことです。最初は短時間で構わないので、毎日続けることが大切です。
④問題集やテストでアウトプットする
学習した知識を定着させ、テストや試験で発揮できるようにするためには、インプットだけでなくアウトプットを意識することが重要です。
教科書を読むだけ、ノートをまとめるだけでは、使える知識になったとは言い難いでしょう。問題集やテスト形式の問題を繰り返し解くことで、本当に理解できているか、知識が定着しているかを確認できます。
演習やテストといったアウトプットにより、自分が理解できていない部分が明確になると、対策も立てやすくなるでしょう。勉強する「時間」だけにこだわらず、勉強する「内容」や勉強の「やり方」にもこだわりましょう。
⑤わからない箇所は理解するまでやる
問題集やテスト問題でアウトプットしていると、必ず間違えるポイントや苦手意識が強いポイントが発見できます。
苦手な問題や理解できない箇所にぶつかると、後回しにしたくなるかもしれません。しかし、間違えた箇所や苦手な箇所こそ、成績やテストの点数を伸ばすための重要なポイントとなります。
わからない箇所をそのままにしていると、次のテストでも同じミスをしたり、応用問題が解けなくなったりすることもあるため、放置せず対策することが大切です。
対策することで、徐々に理解できる範囲が広がり、苦手分野でも勉強をスムーズに学習できるようになります。結果的に勉強時間を効率的に使えるようになるでしょう。
中学生が勉強時間を増やすために心がけたいポイント
「勉強時間を増やしたい!」と思っても、なかなかうまく行かない方も多いのではないでしょうか。中学生が勉強時間を増やすために、日ごろから以下のことを心がけましょう。
それぞれ詳しく紹介します。
毎日の時間の使い方を客観的に把握する
勉強時間を増やすためには、まず、1日の過ごし方を見直しましょう。「時間がない」と思っていても、意外と無駄な時間を過ごしていることも少なくありません。
たとえば、学校から帰ってから何をしているかをチェックしてみてください。スマートフォンやテレビにどれくらいの時間を使っているかなどを記録してみると、気づかないうちに時間を無駄にしていたことに気づくかもしれません。
1日2時間だとしても1週間で14時間、1か月で60時間も無駄にしています。息抜きも必要ですが、1日10〜20分など、少しずつでも勉強する時間に変えていく意識が大切です。
隙間時間を有効に活用する
部活動や習い事などが忙しく、長時間のまとまった勉強時間を確保することが難しい学生もいるかもしれません。
まとまった勉強時間が取れないときは、10〜15分の隙間時間を使うことが、勉強時間を増やすコツです。
通学中の電車・バス、昼食を食べたあとの時間など、数分~十数分という隙間時間でも積み重ねれば大きな勉強時間になります。
隙間時間の勉強は暗記系の勉強をする、まとまった勉強時間では問題集を解くなど、時間と学習内容の組み合わせを工夫することも大切です。
規則正しい生活リズムを身につける
効率的に勉強するためには、十分な睡眠と規則正しい生活リズムを身につけることが必要不可欠です。
「勉強時間が足りない」と感じると、休憩を取らずに長時間勉強したり、睡眠時間を削って夜遅くまで勉強したりするかもしれません。
しかし、睡眠不足や疲れた状態では集中力や記憶力が低下してしまい、勉強時間に見合う成果が得られないことがあります。
高校受験を控えているのに生活リズムを崩したり、睡眠時間を削って勉強したりすると、試験当日に体調不良や寝不足で日ごろの成果が出ないなどのリスクが高まります。
勉強するときは集中し、休憩するときは勉強のことを忘れるなど、メリハリをつけることが大切です。勉強時間をむやみに伸ばそうとするのではなく、まずは早寝早起きを意識して生活リズムを整えましょう。
集中できる環境で勉強する
勉強時間を確保できても、勉強に集中できなければ身にならないこともあります。
勉強中はテレビを消し、スマートフォンやゲームなど気が散るものは手の届かない場所に移動させましょう。
家で勉強に集中できる環境をつくるのが難しい場合は、図書館や塾の自習室の活用がおすすめです。集中できる環境で勉強すれば、短い時間でも質の高い学習ができます。
中学生の子どもの勉強時間を伸ばすために親ができるサポート
中学生の子どもにとって親の存在は大きなものです。親のサポートによって子どもは勉強に向き合う意識が高まるかもしれません。
ここでは、勉強時間を伸ばすために親ができるサポートの一例を紹介します。
それぞれ詳しく紹介するので参考にしてください。
ポジティブな声かけをする
親のポジティブな声かけは子どものモチベーションを高め、間接的に勉強時間を伸ばす効果が期待できます。
たとえば、「毎日頑張ってるね」「昨日も長く勉強してえらいね」など、努力や取り組む姿勢に目を向けて褒めてあげることで、子どもは自尊心が高まり、「もっと頑張ろう」と思えるようになるでしょう。
勉強は成果が出るまでに時間がかかることもあります。成績やテストの点数など、結果ばかりを評価するのではなく、取り組む姿勢など過程を褒めることが大切です。
落ち込んでいるときや思うように成果が出なくて悩んでいるときは、「大丈夫、大丈夫!」「次に活かせるチャンスだよ」など、励ます言葉が安心感につながるでしょう。
親が味方になってくれていると実感すると、子どもは安心して勉強に取り組めます。
生活面や体調管理のサポートをする
生活面や体調管理のサポートは、中学生の保護者の大きな役割のひとつです。
たとえば、十分な睡眠時間がとれるように夜更かしを控える声かけをしたり、バランスの取れた食事を用意したりといったサポートは、集中力や学習意欲を保つうえで重要です。
テスト前や受験前は、無理をしてしまう中学生も多いでしょう。「無理しないで早めに休んでね」「体調管理も勉強のうちだよ」などの言葉かけは保護者ができるサポートのひとつです。
学習環境を整える
長時間勉強するためには、集中しやすい学習環境を整えてあげることも大切です。子どもが勉強中にうるさくしたり、リビングのテレビがついていたりすると、勉強に集中できなことがあります。
子どもが勉強している時間は保護者も資格の勉強や読書をおこない、学ぶ姿勢を共有するのがおすすめです。「親も頑張っている」と感じれば、より勉強への意欲が高まるでしょう。
自宅ではどうしても集中が続かない場合には、塾に通わせるのも選択肢のひとつです。自習室が使える塾のなかには、わからない箇所を塾の講師に直接質問・相談できることがあります。
塾には、目的に向けて効果的な対策ができるだけでなく、一緒に切磋琢磨できる仲間を見つけやすいなど、勉強に最適な環境が整っている点が大きなメリットです。必然的に勉強する時間を伸ばせるうえ、勉強の質も上がることが期待できます。
勉強に関する悩みや相談を一緒に考える
中学生の子どもは、勉強に対する不安やプレッシャーを抱えていることも珍しくありません。不安や悩みは勉強の妨げになってしまうため、親が日ごろから子どもの様子を気にかけ「何か困っていることはある?」などと声をかけてあげましょう。
「勉強方法がわからない」「なかなか勉強に集中できない」「このままでは受験に間に合わないかもしれない」など、さまざまな悩みを抱えており、勉強に集中できていないかもしれません。
子どもの不安や悩みに対して、親は一緒に対策や解決策を考えてあげましょう。悩みが解消されれば勉強への意欲も自然と高まります。
中学生は勉強時間の長さにこだわらず、効率や質を高めることが大切
中学生の一般的な勉強時間は、平均して2〜3時間程度です。実際の勉強時間は、学年や受験勉強の有無などで異なるでしょう。
勉強時間とあわせて大切なのは、勉強の「質」です。長時間勉強しても身につかない勉強方法なら、その時間が無駄になってしまう可能性があります。
紹介した効率的な勉強方法や、勉強時間を伸ばすコツを参考に、質の高い勉強に取り組んでみてください。