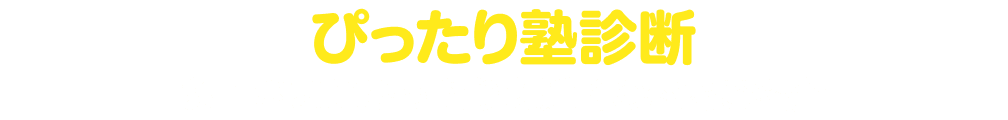「大学受験のために、塾に行くべきなのかな?」
「大学受験に備えて塾に行っている人は、どれぐらいの割合なのだろう」
「そもそも塾に行くメリットって何?」
このような疑問を抱く方がいるかもしれません。詳細は本文で解説しますが、結論をいうと、大学受験をするのであれば塾に行くべきです。志望校にあった対策を受けられる、経験豊富な講師陣から指導を受けられるなどのメリットがあるからです。
そのような背景もあり、「令和3年度子供の学習費調査」によると、高校生の通塾率は公立高校で33.2%、私立高校で38.3%という結果が出ています。そのため、塾に行くのは珍しいことではありません。難関大学を目指す場合、塾を活用することで、より効果的な対策ができることも多いでしょう。
そこでこの記事では、大学受験のため塾に通っている高校生の割合やメリットだけでなく、通ったほうがよい高校生の特徴、塾に行く場合の注意点、塾を選ぶ際のポイントも解説します。大学受験のために、塾に行くべきかどうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
- 大学受験のために塾に通う高校生の割合を紹介
- 大学受験のために塾に行くメリットとは
- メリット1.学習習慣が身につく
- メリット2.志望校にあった対策ができる
- メリット3.志望大合格を目指す仲間と切磋琢磨できる
- メリット4.専門性の高い講師から指導が受けられる
- メリット5.集中して勉強できる環境を手に入れられる
- メリット6.大学受験の情報を得られる
- メリット7.メンタルサポートを受けられる
- 大学受験のために塾に行く際の注意点
- 注意点1.塾に行くことが目的となってしまう場合がある
- 注意点2.高校と塾で授業内容を混同し、混乱してしまう可能性がある
- 注意点3.通塾に時間がとられてしまう
- 注意点4.塾費用がかかる
- 大学受験のために塾に通ったほうがよい高校生の特徴
- 周囲の環境がモチベーションになる人
- 勉強の進め方がわからず独学では不安な人
- 通っている高校が進学校ではない人
- 学校の授業についていけない人
- 難関大学を目指したい人
- 大学受験のために塾が必要ない高校生の特徴
- 自分で戦略を立てられる人
- 志望校の合格圏内に入っている人
- 大学受験に向けた指導がおこなわれる高校に通っている人
- 大学受験のために塾に行く場合の注意点
- 塾に行くことが目的化しないよう気を付ける
- 通塾の費用に気を付ける
- 大学受験対策の塾を選ぶ際のポイント
- 指導形態
- カリキュラムやコース
- 合格実績
- 教室見学・無料体験の有無
- 大学受験に適した塾の選び方を授業形態別に紹介
- 「集団授業」の特徴とメリット・注意点
- 「個別指導」の特徴とメリット・注意点
- 「オンライン授業(映像授業)」の特徴とメリット・注意点
- 大学受験のための塾選びは「Ameba塾探し」で決まり!
- 大学受験のために塾に行くべきかどうかは現在の学力などを踏まえて判断しよう
大学受験のために塾に通う高校生の割合を紹介
大学受験のために塾に通う高校生がどのくらいいるのか、実際の通塾率を見ていきましょう。
文部科学省が発表した「令和3年度子供の学習費調査」によると、高校生の通塾率は公立高校に通う生徒で33.2%、私立高校に通う生徒で38.3%でした(※1)。
さらに学年別にみると、1年生:34.5%、2年生:36.8%、3年生:42.1%という割合でした。
この結果を見ると、約3割~4割の高校生が塾に通っていることがわかります。
(※1)参考:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
大学受験のために塾に行くメリットとは
大学受験のために塾に行くメリットとしては、主に以下のようなことが挙げられます。
メリット1.学習習慣が身につく
塾に通うことで、毎週決まった曜日の決まった時間に塾の授業を受けることになります。また、学校の宿題に加えて塾の宿題もこなすため、自宅での勉強時間も増えます。
そういった環境に身を置くことで、学習習慣が身につくことが期待できるでしょう。
自宅ではなかなか集中して勉強することが難しいという人の場合、塾に設けられている自習室を利用できるのもメリットでしょう。
メリット2.志望校にあった対策ができる
大学受験で合格するためには、入試で問われる分野に特化して勉強することが必要です。
学校では決められたカリキュラムをもとに授業が進められますが、塾では志望校の入試傾向に沿った内容の授業を受けられます。
受験に必要な知識をより吸収しやすい環境といえるでしょう。
また、短い期間で大学合格を勝ち取るためには、受験への戦略を練ることがとても大切です。
得意分野が多く出題される大学を選ぶ、合格までのスケジュールを作成するなど、ひとりでは大変なことも多いですが、塾に通えば相談しながらおこなえるため安心です。
メリット3.志望大合格を目指す仲間と切磋琢磨できる
塾では学校の友人とは異なる同学年の仲間と切磋琢磨できるため、勉強に対する刺激を受けやすいという点もメリットです。
塾の模試を受けて塾内や全国での自分の学力的な位置を知るなどして、よい刺激を受けることも期待できるでしょう。
学校以外でも同じ学力レベルの友人や、大学合格を目指す友人ができると、勉強のモチベーション維持にもつながりやすくなります。
メリット4.専門性の高い講師から指導が受けられる
塾に行くことで、多くの受験生を合格に導いた経験を持つ、専門性の高い講師から指導を受けることができます。
塾には、これまで多くの受験生を送り出してきた実績があり、膨大な情報やデータが蓄積されています。
生徒がつまずきやすいポイントを講師がしっかり把握しているため、たとえば「理解すべきところ」と「丸暗記したほうが楽なところ」などをわかりやすく教えてくれるでしょう。
高校にはない情報を自分の大学受験のために役立てられるというのも、塾に通う大きなメリットのひとつです。
メリット5.集中して勉強できる環境を手に入れられる
塾に行くメリットとして、集中して勉強できる環境を手に入れられることが挙げられます。自宅と違って誘惑が少なく、学習に専念できる空間が整っているからです。
たとえば、自分の部屋ではスマートフォンやテレビ、家族の声などが気になって勉強に集中できないことがあります。塾では、同じ目標を持つ生徒が静かに勉強しているため、自分も自然と集中モードに入れます。
塾にいると「周りの子が頑張っているから、自分も頑張らなきゃ」という気持ちが自然に湧いてくるでしょう。この“適度な緊張感”が、勉強の効率を高めてくれます。
もちろん、その一方で塾に通っても集中できない人もいます。そのような時こそ、塾の講師に一度相談するとよいでしょう。
メリット6.大学受験の情報を得られる
塾には大学ごとの入試傾向や出題の特徴、変更された出願条件などを専門的に分析している講師やスタッフが在籍しており、自分ひとりでは収集しづらい情報を教えてもらえます。
たとえば学校では、志望大学に関する質問をしたとしても、「共通テスト重視」としか教えてもらえないおそれがあります。そもそも学校は大学進学に特化した教育機関ではなく、あくまで就職などを含めた進路指導やそのサポートが主だからです。予備校や塾のように、各大学の傾向を細かく把握しているとは限りません。
その一方で予備校や塾は、大学進学に特化した教育機関です。そのため各大学の傾向を把握していることが多く、「志望校は二次試験の論述で差がつくから、共通テスト対策だけでは不十分」と具体的なアドバイスをもらえるでしょう。
ただし、塾によって情報の質には差があるため、講師の経験や合格実績、情報更新の頻度を確認して選ぶことで、より信頼性の高い指導を受けることが可能になります。
メリット7.メンタルサポートを受けられる
塾に行くことによって、メンタルサポートを期待できるでしょう。精神的な不安や焦りを理解してくれる大人が身近にいることで、安心して学習に集中できます。
そもそも受験勉強はとても長く孤独な戦いで、模試の点が下がったり、周りの友だちと比べて落ち込んだりすることが多いものです。そのような場面で、塾講師が「それはよくあることだよ」「今が踏ん張りどころだね」と声をかけてくれると、自分の状況を冷静に見直すきっかけになります。
こうした支えは、家庭や学校では得られないこともあるため、塾が心のよりどころになることは多いです。ただし、塾によってサポートの質は異なるため、説明会や体験授業を通じて、信頼できる講師や相談環境が整っているかを自分の目で確かめることが重要です。
大学受験のために塾に行く際の注意点
大学受験のために塾に行く際の注意点としては、主に以下のようなことが挙げられます。
注意点1.塾に行くことが目的となってしまう場合がある
塾に通うことは、あくまでも「大学受験に合格する」「学力を向上させる」といった目的に対する手段です。
塾に行く目的や目指す目標をあまり意識しないまま塾に通ってしまうと、塾に行くこと自体が目的となってしまい、期待しているような成果につながらない可能性があります。
塾に行っているということに安心して実は自主的な学習習慣が身についていない、ということにならないよう注意しなければなりません。
注意点2.高校と塾で授業内容を混同し、混乱してしまう可能性がある
学校の授業と塾の授業では、学習する分野や課題に対するアプローチが異なる場合があります。
同じ分野・単元であっても、指導方針や目指す習熟度が違うこともあるでしょう。
さまざまなアプローチを知ることはプラスに働くことがある反面、かえって混乱してしまう可能性も否定できません。
学校の授業できちんと学力が上がっていると感じる場合、塾に通わずに学校の勉強を深掘りするほうがよいこともあります。
注意点3.通塾に時間がとられてしまう
塾が自宅や学校から近い距離にあれば問題はないのですが、離れたところにある場合、通塾時間が負担になる可能性も考えられます。
とくに受験間際は一分一秒を惜しんで勉強したいとう気持ちが出てきやすく、そのようなときに長い時間をかけて塾に通うことがストレスに感じることもあるでしょう。
また、保護者の送迎が必要になる場合、保護者にも一定の時間に制約ができ、負担となることもあります。
注意点4.塾費用がかかる
塾に通うためには、当然ながら費用がかかります。
大学に合格するためには仕方のない出費だと割り切ることも必要ですが、長いあいだ塾に行くことになると、費用面が負担となる場合もあります。
かかる費用は塾によっても異なりますが、通常の授業料に加えて入会金、教材費、季節講習費、模試代、施設維持費など、思ったよりも多くの出費となることもあります。
あらかじめトータルの費用を算出し、受験までの期間や塾にかけることのできる予算などと照らしあわせて塾を検討することも重要です。
大学受験のための塾にかかる詳しい費用については、下記の記事をご覧ください。
大学受験のために塾に通ったほうがよい高校生の特徴
塾に通うことのメリットや注意点を踏まえると、大学受験のために塾が必要な高校生と必要でない高校生の特徴も自ずと見えてきます。
塾に通ったほうがよい高校生の特徴としては、主に以下のようなことが挙げられます。
塾に通うべきか迷っている人は、該当する項目があるかチェックしてみてください。
周囲の環境がモチベーションになる人
さまざまな相手と競い合ったほうがやる気が出る、負けず嫌いな人は、塾に通って同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨するほうが成績が上がりやすいでしょう。
また、自宅には誘惑が多く、他人の目がないと集中できないという人にも塾がおすすめです。
塾に通って多くの学生と一緒に授業を受けることで、より勉強に集中しやすくなるでしょう。
自習室を自由に使用できる塾を選ぶと、より集中できる環境が得られやすくなります。
なお、自習室は受験間際になると席が埋まりやすい傾向にあります。
自習室の利用を考えている場合は、自習室の座席数と在籍生徒数のバランスをあらかじめ確認しておきましょう。
勉強の進め方がわからず独学では不安な人
大学受験に向けてどの科目を優先的に勉強すればよいかわからない、1週間の勉強スケジュールを自分で決められない、家庭学習での独学だけでは不安…という人にも塾はおすすめです。
塾に通うことで、講師から客観的な評価や勉強の仕方のアドバイスを受けることができます。
より効率的な正しい勉強方法を選ぶことは、大学受験合格への大きな近道となります。ただ、勉強方法に不安を抱えたまま独学で勉強を進めても、いまいち力が入らないでしょう。
講師とこまめに相談したり、自分にあわせたカリキュラムを作成してくれることで、安心して勉強に取り組めます。
通っている高校が進学校ではない人
通っている高校がいわゆる進学校ではない場合、高校で得られない情報を補うためにも塾に通うほうがよいといえます。
塾のほうが学校の授業進度より早いことが多いため、早期から大学受験に向けた勉強に着手できます。
大学受験専用のコースがある塾を選ぶと、より専門的に大学受験対策に励むことができますよ。
学校の授業についていけない人
学校の授業についていけない高校生は、大学受験のために塾に通ったほうがよいです。なぜなら、自分の理解度にあわせた指導を受けることで、学力の遅れを取り戻せるからです。
たとえば、数学の授業で講師の解説を聞いても式の意味がわからず、ノートを見返してもひとりで復習できない生徒がいたとします。このような場合、塾では丁寧に教えてもらえるため、学校では聞けなかったことを基礎から学び直すことが可能です。
さらに、塾では問題を解くコツや考え方も繰り返し教えてもらえるので、理解が深まり「できない」という不安を「できる」という自信に変えることができます。その結果、学校の授業にも少しずつついていけるようになり、受験に必要な土台を整えることができます。
一方で、塾に通っても受け身の姿勢のままだと成績は伸びにくいので、自分から質問したり、復習を丁寧に行ったりする姿勢が重要です。だからこそ、自分の理解度に合った塾を選び、疑問を解消できる環境をつくることが大切です。
難関大学を目指したい人
難関大学を目指したい人は、塾に通うべきでしょう。志望校のレベルに合った専門的な対策を受けられるからです。
例を挙げると、東京大学や京都大学、早慶といった難関大学は、共通テストの高得点だけでなく、記述力・論理的思考・応用力も問われます。たとえば数学であれば、公式の丸暗記だけでは太刀打ちできず、「なぜこの解法になるのか」という論理の流れを理解し、自分の言葉で表現できる力が求められます。
これを身につけるには、独学よりも、経験豊富な講師による個別指導や演習解説を受けるほうが効率的です。
ただし、塾に通えば誰でも合格できるわけではないため、自分の弱点を正しく把握し、授業や自習を計画的に活用することが成功の鍵となります。入塾前に無料体験や学力診断を受け、自分に合った塾を見極めることで、より的確な対策が可能になります。
大学受験のために塾が必要ない高校生の特徴
必ずしも塾に通う必要のない高校生の特徴としては、主に以下のようなことが挙げられます。
それぞれの特徴について、以下で詳しく説明しましょう。
自分で戦略を立てられる人
とくに現役合格を目指す場合、合格までの戦略が何より大切です。
限られた時間内で合格を目指すには、自分の得意分野にあった出題をする大学を選ぶ、その大学に適した参考書を用いて効率のよい勉強をするなど、多くの工夫をする必要があります。
勉強の仕方や合格までの戦略をが自分なりに立てられて、かつ成績にしっかりと反映できているという人は、必ずしも塾に通う必要はありません。
また、勉強のスケジュールを自分で立てられる、あるいは自分でスケジュールを管理するほうがやる気が出るという人も同様です。
周囲の誘惑に負けずに集中して勉強ができ、自分で立てたスケジュール通りに進めて結果が伴っているようであれば、自分のペースで進めるほうがあっているといえます。
塾に通うことでかえってやるべきことが増えて混乱してしまうおそれもあるため、無理に塾に通わずに自分のペースで勉強を進めていきましょう。
ただし、少しでも不安な場合は1科目でも塾に通うことがおすすめです。1科目でも通うことで、講師へ質問をしたりアドバイスをもらう機会を獲得できます。
基本は独学で進めて、定期的に戦略のすり合わせとして客観的なアドバイスをもらうと、安心して進めやすいでしょう。
志望校の合格圏内に入っている人
すでに志望校合格への道筋が見えていれば塾に通う必要はありません。
ただし、模擬試験の結果を目安としているのであれば、その結果を信用しすぎるのは禁物です。なぜなら、実際の試験問題は大学によってまったく異なるからです。
たとえば英語の問題ひとつをとっても、大学によって文法を正しく理解できる力を重視するのか、内容の大まかな概要を汲み取る力を重視するのか、内容が大きく異なります。
目安として、志望する大学の過去問を解き、合格最低点を余裕で上回る状態などであれば、塾に通う必要はないかもしれません。
大学受験に向けた指導がおこなわれる高校に通っている人
通っている高校が進学校である場合や、大学受験に向けた指導が積極的におこなわれている場合も、必ずしも塾に通う必要はありません。
塾の強みとして、大学受験に特化したコースがあることや、大学受験に関する情報が豊富であるということが挙げられます。通っている高校でこれらが十分フォローできていると感じるなら、無理に塾に通わなくてもよいでしょう。
大学受験のために塾に行く場合の注意点
ここでは、大学受験のため塾に行くことにした際の、注意点を解説します。
塾に行くことが目的化しないよう気を付ける
塾に行く場合の注意点として、塾に行くことが目的化しないよう気を付けることが挙げられます。通塾が目的化すると本来の「合格するための学力向上」という目標から外れてしまうおそれがあるからです。
たとえば、毎日塾に行っているから安心だと思い込んで、授業を聞くだけで満足し、復習や自習をおろそかにしてしまうとしましょう。こうした状態では知識が定着せず、模試の成績も伸び悩みます。「行っている=頑張っている」と錯覚するのは危険です。
塾は「学ぶ場」であり、「自分で理解し身につける努力」を重ねることが大切です。塾で学んだことを自分で復習する時間を必ず確保し、「何のために塾に行っているのか」を定期的に振り返るとよいでしょう。
通塾の費用に気を付ける
塾に行く場合の注意点として、通塾の費用に気を付ける必要があります。
理由は、長期的に見ると授業料や教材費、模試代、交通費などがかさんで、家計に大きな負担となるからです。
たとえば、大学受験に向けて有名塾に入ったところ、月謝が6万円ほどかかり、夏期講習や冬期講習を受けるとさらに10万円以上の出費が追加されがちです。
これに加えて、模試代が年間数万円、毎回の交通費も月に5千円ほどかかるため、年間では合計で100万円に達することもあり得ます。
その結果、家計を圧迫するかもしれません。
受験に合格したあと、大学に授業料を支払う必要があり、慎重に考えなければなりません。
そのため、事前に全体の費用見通しを立て、必要な講座に絞ることが重要です。併せて、定期的に通塾内容を家族で見直すことで、無駄を省きつつ効果的に学習を進められます。
大学受験対策の塾を選ぶ際のポイント
塾を選ぶ際のポイントを解説します。
指導形態
大学受験対策の塾を選ぶ際のポイントとして、指導形態が挙げられます。学習効率が大きく変わるためです。
たとえば、大人数の講義形式では、学校のように一斉に同じ授業を受けるため、わからないところがあっても質問しづらいことがあります。しかし個別指導であれば、自分の理解度にあわせて授業を進めてもらえるため、苦手な科目や問題をじっくり解消しやすくなります。
英語の文法が苦手な生徒が個別指導を選んだ場合、その子の苦手な項目を徹底的に復習するようなカリキュラムに調整してもらえるでしょう。「be動詞」と「一般動詞」の違いで混乱していた場合、講師がその場で図や例文を使って丁寧に説明することが可能です。理解が深まり、テストでも正確に解答できるでしょう。
指導形態の特徴を見極め、自分の性格や学習スタイルに合ったものを選ぶことが、受験成功への近道となります。
カリキュラムやコース
カリキュラムやコースを確認することも重要です。学力や志望校に合った指導内容でなければ、効率的な学習ができないためです。
たとえば、英語が得意で数学が苦手な生徒が、全教科一律の授業を受けていると、既に理解している英語に時間を割きすぎてしまい、肝心の数学の弱点補強に十分な時間を取れません。その結果、苦手分野が克服されず、模試の点数や偏差値も思うように上がらない状況が続きます。
こうした事態を防ぐには、「英語は維持、数学は集中強化」といった個別の戦略に対応できるカリキュラムが必要です。また、志望校の入試科目や出題傾向に特化したコースを選ぶことで、効率的に点数を伸ばせる対策ができます。
コースが志望校の入試形式に対応しているか、自分の得意・不得意に応じたカリキュラムが組めるかまで確認することが、合格への近道となります。
合格実績
大学受験対策の塾を選ぶ際、合格実績を確認しましょう。指導の質や成果を、客観的に示す指標になるからです。
仮に、A塾とB塾のどちらに通うか迷ったとき、A塾は過去5年で東京大学や早慶など難関校への合格者が多く、B塾はあまり有名ではない私大ばかりだとしたら、受験生や保護者は当然A塾を魅力的に感じます。第一志望が東京大学や早慶であれば、なおさらです。
ただし、表面的な合格数だけを見るのではなく、「どの学校に何人受かったか」「現役生なのか既卒生なのか」などの詳細まで見ることが大切です。100人合格と書いてあったとしても、10,000人在籍していたら合格率はたったの1%です。そうなると、話が少し変わってきます。
このように、実績は質と比率の両方を確認する必要があります。塾に直接確認するなどして情報の裏付けを取ることで、信頼できる塾なのかを見極められるでしょう。
教室見学・無料体験の有無
大学受験対策の塾を選ぶ際に、教室見学や無料体験の有無を確認することをおすすめします。理由は、実際の雰囲気や指導の質を、自分の目で確かめられるからです。
たとえば、チラシやホームページで「少人数制」と書いてあっても、実際に教室に行ってみると机の間隔が狭くて集中しづらかったり、講師が生徒の様子をあまり見ていなかったりするケースがあるかもしれません。体験授業を受けてみると、講師の教え方が合わないと感じたり、反対に「この講師なら続けられる」と思えたりする可能性もあります。
こうした感覚的な相性は、勉強を続ける上でのストレスになります。仮に「評判がよい塾」でも、自分に合わなければモチベーションが下がってしまい、成績も伸びにくくなってしまうのです。
こうしたリスクを避けるには、必ず事前に見学や体験ができる塾を選び、少なくとも1回は授業や教室環境を確認してから入塾を判断するとよいでしょう。
大学受験に適した塾の選び方を授業形態別に紹介
大学受験対策として塾に通う場合は、自分にあった授業形態を選ぶようにしましょう。
授業形態は、主に3つあります。
それぞれの形態の特徴やメリット・注意点について、以下で詳しく説明します。
「集団授業」の特徴とメリット・注意点
「集団授業」とは、複数の生徒に対して1人の講師が指導する形式の塾で、学校に近いイメージです。
集団授業型の塾には、下記のようなメリットがあります。
集団授業型の塾では、学力別にクラス分けされるケースがほとんどです。少し油断すると周囲から遅れをとるので、緊張感を持って勉強に励むことができます。
そのため集団塾には、授業の進行にあわせて自発的に勉強に取り組める、また塾内での仲間やライバルと比較して自分の位置を確認したいという競争心を持っている子にあう傾向があります。
また、定期的にテストや模試を実施しているため、自分の学力を客観的に把握しやすいというのも、大学受験に向けては重要なポイントです。
さらに、集団授業をおこなっている講師は経験や実績が豊富な講師であることが多く、そういった講師の授業を受けることで、学力を効率的に向上させられることが期待できます。
メリットも多い一方、次の2つには注意する必要があります。
集団授業では、体調不良で欠席したり、部活が長引いて遅刻をしたりすると、授業に置いて行かれる可能性があります。塾によっては、補講や振替をしてくれる場合もあるので、不安な場合は入塾前に確認しておきましょう。
また、人によっては常に他人と比較されることで過度なストレスを感じてしまい、かえって勉強に集中できない場合もあります。自分のペースでコツコツ勉強したい方は、次で紹介する個別指導の塾がおすすめです。
「個別指導」の特徴とメリット・注意点
「個別指導」とは、マンツーマン、あるいは生徒1~3人に対して講師1人が指導をおこなう、少人数制の塾です。
個別指導の塾には、次のようなメリットがあります。
個別指導では、習熟度や理解度などから一人ひとりにあわせたカリキュラムを作成してくれます。
自分の苦手なところだけをピンポイントで教えてもらえるため、効率的に勉強を進めることができるでしょう。
授業の途中でも質問をしやすい点もメリットです。
集団授業だと、恥ずかしくて授業中に質問しにくかったり、ノートをとっているうちに質問するタイミングを逃してしまうことがありますが、個別指導ではその都度質問できます。
また、塾に通う曜日や時間帯も選びやすいため、部活との両立も比較的しやすい点もメリットです。
一方で、以下に挙げる注意点があります。
個別指導は、生徒1人もしくは2人に対して講師1人で授業をおこなうため、集団授業と比べて費用が割高になる傾向があります。
費用をおさえたい場合は、受講する科目の数を苦手科目のみに絞ったり、授業の頻度を調整することをおすすめします。
また、講師との相性が悪いと、思うように成績が上がらない場合があります。
たとえば、数学が苦手で塾に通っても、講師のなかに数学が得意な人がいなければ教えてもらいづらいでしょう。
その塾の得意科目や特色は何か、どんな講師が在籍しているのか、あらかじめ確認しておきましょう。
「オンライン授業(映像授業)」の特徴とメリット・注意点
「オンライン授業(映像授業)」には、事前に録画した授業の映像をアーカイブのなかから視聴するタイプと、リアルタイムで授業を配信するタイプがあります。
オンライン授業には次のようなメリットがあります。
オンライン授業(映像授業)は、自宅にいながら授業を受けることができるため通塾の負担がなく、より多くの時間を勉強に費やすことができます。
また、地方に住んでいても有名講師や人気講師の講義を受けることができる点も魅力のひとつ。オンライン授業で活躍する講師は、多くの受験生を合格に導いた実績があり、生徒を飽きさせないようにわかりやすく教えてくれます。
集団授業や個別指導と比較して、授業料が安く経済的な負担が軽い点も大きなメリットです。
一方で、次のような注意点もあります。
録画された授業を視聴する形態では、いつでも好きなタイミングで授業を受けられますが、その場合は自分で授業を受けるタイミングを決めなければなりません。スケジュール管理が苦手な人にとっては難しいこともあるでしょう。
また、質問をしてもリアルタイムで回答してもらえないことが多いです。
塾によっては、チャットで塾のスタッフが質問に回答してくれるサービスがあります。不安な方は、入塾前に確認しておきましょう。
大学受験のための塾選びは「Ameba塾探し」で決まり!
塾に行く場合、数多くの塾のなかから自分にあった塾や授業形態を選ばなければなりません。ミスマッチを避けるためにも、複数の塾を比較・検討することが重要です。
そこで、後悔のない塾選びをおこなうにあたって役立つのが、塾・学習塾の検索サイト「Ameba塾探し」です。
Ameba塾探しでは、個別指導や集団授業、映像授業などの授業形式、地域、費用、カリキュラムなど、さまざまな項目で塾を比較できるため、複数の塾のなかから自分に最適な塾を選ぶ助けになります。
大学受験のための塾選びには、ぜひ「Ameba塾探し」を利用してみてください。
大学受験のために塾に行くべきかどうかは現在の学力などを踏まえて判断しよう
大学受験のために塾に通う高校生はたくさんいます。
しかし、必ずしも塾に通う必要はないため、現在の学力や学習習慣、志望校のレベルに応じて判断しましょう。
塾に通うことで、学習習慣が身につく、受験に最適な授業を受けられる、といったメリットがありますが、その反面、塾に行くことが目的になったり、通塾が負担になったりする可能性もあります。
また、塾に通うと決めた場合、どの授業形態が自分にあっているのか見極めることが大切です。
塾選びに迷ったら、ぜひ「Ameba塾探し」を活用してみてください。Ameba塾探しでは、たった10秒で塾が探せる“ぴったり塾診断”があります。
診断結果や今回ご紹介した塾の選び方も参考に、ぜひ自分にあった塾や予備校を見つけてみてくださいね。