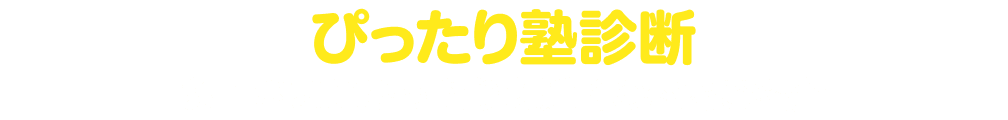2学期も後半にさしかかり学校の冬休み期間が近づいてくると、多くの塾では冬期講習の募集が開始されます。
現在塾に通っている方もそうでない方も、今年の冬期講習を受講するかどうか考えてみたことがあるのではないでしょうか。
そこで今回は、塾の冬期講習の受講を検討中の方に向けて、冬期講習の内容や費用相場、塾を選ぶ際の注意点などについて解説していきます。
冬期講習の選び方についてお悩みの場合はぜひ参考にしてみてください。
冬期講習とは
冬期講習とは、12月末〜1月上旬の冬休み時期に開催される特別講習を指します。
開催日程は塾によって異なりますが、年末年始休暇を挟んで5〜7日間程度としているところが多いです。
冬期講習の内容は、集団指導塾と個別指導塾で大きく異なります。
集団指導塾の冬期講習は、複数のコースやクラスから自分にあうものを選択して、数日間のカリキュラムを受講するのが特徴です。受講内容や期間、講習費用があらかじめ決まっているため、受けたい講座を計画的に申し込めます。
一方、個別指導塾の冬期講習は、担当講師などと相談しながら受講内容や講習日数を決めていくスタイルが一般的です。生徒一人ひとりの学習状況や冬休み中の予定に柔軟に対応できるので、自分に最適な冬期講習を一から組み立てたい方に向いています。
塾の冬期講習を受講する目的
冬期講習を受講する目的は、受験生と受験生以外で異なります。
【受験生】入試直前対策
受験生の場合、冬期講習の主な受講目的は入試対策です。
志望校の過去問演習はもちろん、出題傾向にあわせた問題演習を重点的におこない、志望校合格に必要なテクニックを身につけます。
また、入試前に集中して受験勉強に取り組める最後の期間でもあるので、重要単元の復習や苦手分野の克服にも時間をかけて取り組めます。
【受験生以外】2学期までの学習内容の復習と3学期の予習
受験生以外の場合は、2学期までの学習内容の復習を目的として冬期講習を受講する生徒が多いです。
多くの塾では、冬期講習中に重要単元の復習をおこなうため、学校の授業で理解しきれなかった単元があれば冬期講習を通して復習・定着を目指せます。
さらに、コースによっては2学期の復習から3学期の予習まで取り組むこともあります。
塾の冬期講習を利用するメリット
塾の冬期講習を利用するメリットは、主にこの3つです。
①受験の直前対策に力を入れられる
受験生にとって、冬期講習で志望校の入試に特化した学習に専念できるのは大きなメリットです。
これまで学習してきた内容の総仕上げとして過去問や模試、テストに取り組み、そこで見つかった抜け漏れや苦手分野を復習することでさらに合格の可能性を上げられます。
また、入試対策の知識が豊富な塾講師と一緒に対策することで、試験本番へのモチベーションを高めたり、精神的な不安を取り除いたりする効果も期待できるでしょう。
②これまでの学習内容を定着させて3学期につなげられる
冬期講習では主に2学期までの学習内容の復習をするため、これまでの学習内容が定着させることで3学期によいスタートを切ることができます。
総復習でいつの間にかできていた苦手分野を発見できれば、それが成績アップのチャンスです。
2学期までの学習内容でうまく理解できなかった単元がある人や、定期テストの点数が伸び悩んでいる人は、冬期講習で集中的に学習することでしっかり学習効果を感じられるでしょう。
③冬休み中も学習習慣を保てる
長期休み中は学校がなく生活リズムが崩れがちですが、冬期講習の決まったスケジュールで学習するようにすれば冬休み中も生活リズムと学習習慣を保てます。
自宅だとどうしてもダラダラしてしまったり、長期休み中に計画的に学習するのが難しかったりする人は、冬期講習を活用して学習習慣をキープしましょう。
また、塾によっては冬期講習がない日でも自習室を利用できるところもあります。
冬休みの宿題サポートをしてくれる塾もあり、自分で家で取り組むより終わらせやすいでしょう。
塾の冬期講習の平均期間と費用相場
ここからは、小学生・中学生・高校生の冬期講習の平均期間と費用相場について解説します。
それぞれ冬期講習の開講期間や費用相場が異なるため、冬期講習の受講をお考えの場合はぜひ目を通してみてください。
小学生
小学生の冬期講習は、主に12月末と年末年始休暇明けの1月上旬で実施されています。
集団指導塾では学年ごとに講習回数が異なるのが特徴です。
たとえば、日能研の2025年度冬期講習スケジュールは以下のようになっています。
【日能研の冬期講習スケジュール(※)】
| 学年 | 冬期講習の概要 |
|---|---|
小学2年生 | 国算2科目・各2回・計4回 / 4日間 |
小学3年生 | 国算社理4科目・各2回・計8回 / 4日間 国算2科目・各2回・計4回 / 4日間 |
小学4年生 | 国算社理4科目・各4回・計16回 / 4日間 国算2科目・各4回・計8回 / 4日間 |
小学5年生 | 国算各10回・理社各8回・計36回 / 9日間 国算各10回・計20回 / 9日間 |
※ 参照:日能研 荻窪校 冬期講習
5年生は12月〜1月にかけて講習がありますが、2〜4年生は12月末の前期4日間か1月上旬の後期4日間のどちらかを選択して受講できます。
なお、個別指導塾の場合、冬期講習のコマ数は一人ひとり自由に決められるのが一般的です。学習したい内容にあわせて受講する科目数やコマ数を設定できます。
小学生の冬期講習(集団指導)にかかる費用相場は、おおよそ以下の通りです。
【小学生の冬期講習にかかる費用相場】
| 学年 | 費用相場 |
|---|---|
1〜5年生 | 2万〜6万円 |
6年生(中学受験) | 4万〜12万円 |
冬期講習の費用は受講する講座数などによって大きく変わり、受講回数が多ければ多いほど費用は高くなります。
たとえば、中学受験に向けた6年生の冬期講習では通常の冬期講習に加えて正月特訓を実施している塾が多く、受講する場合は追加で費用がかかります。
さらに個別指導塾の場合は、集団指導塾の費用相場よりも比較的高めになるのが一般的です。受講するコマ数も一人ひとり異なるため、費用を確認したい場合はまず塾に直接相談してみましょう。
中学生
中学生の冬期講習は、12月下旬〜1月上旬にかけての約2週間で実施している塾が多いです。
中学1〜2年生は通常の冬期講習のみが一般的ですが、高校受験を控えた中学3年生ではそれに加えて科目別・志望校別の入試特訓講座や正月特訓などの特別講座があり、何を受講するかによって講習スケジュールも変化します。
たとえば、Z会進学教室の中学生の2025年度冬期講習スケジュールは以下の通りです。
【Z会進学教室の冬期講習(※)】
学年 | 冬期講習の概要 |
|---|---|
中学1年生 | 英数国:12月27日(土)~1月5日(月)+確認テスト1月6日(火) / 計7日間 理社:12月23日(火)~12月25日(木)+確認テスト / 計4日間 |
中学2年生 | 英数国:12月27日(土)~1月5日(月)+確認テスト1月6日(火) / 計7日間 理社:12月23日(火)~12月25日(木)+確認テスト / 計4日間 中2作文特別講座 / 計3日間 中2神奈川の特色検査 / 計2日間 |
中学3年生 | 英数国理社:12月27日(土)~1月5日(月)+確認テスト1月6日(火) / 計9日間 単元別特訓講座 / 各1〜3日間 学校別入試対策講座 / 各1〜3日間 正月特訓 / 1日間 |
※参照:高校受験をする中学生 2025年度 冬期講習・直前講習 概要|Z会進学教室(首都圏) 中学生
中学生の場合、このように受講する講座が一人ひとり異なるため、冬期講習にかかる費用も人によってさまざまです。
参考程度ですが、一般的な中学生の冬期講習にかかる費用相場としては以下のようになっています。
【中学生の冬期講習の費用相場】
| 学年 | 費用相場 |
|---|---|
| 中学1〜2年生 | 3万〜10万円 |
| 中学3年生 | 5万〜20万円 |
通常の冬期講習は5〜8万円ほどですが、そのほかの費用は特別講座をいくつ受講するかで大きく変動します。
また、個別指導塾では集団指導塾よりも講習費用が割高になることが多いです。
高校生
高校生の冬期講習は、小中学生のように4教科・5教科がセットになっているわけではなく、必要な科目や講座を組み合わせて受講するのが一般的です。
たとえば、河合塾や駿台予備学校といった大手予備校では冬期講習のパンフレットがあり、それを見て必要な講座をピックアップして申し込みます。
申し込んだ講座のみ受講する形なので、期間中ずっと冬期講習があるわけではありません。予定にあわせて受講スケジュールを調整しやすいのも特徴です。
また、高校生の冬期講習の特性上、冬期講習にかかる費用も受講する講座数によって大きく異なります。そのため、ここでは一例として河合塾と駿台予備学校の講座ごとの費用をご紹介します。
【河合塾と駿台予備学校の費用例】
| 塾・予備校名 | 講習・コース | 1講座あたりの費用 |
|---|---|---|
河合塾 | 冬期講習 | 1講座(90分×5回)21,700円 / 塾生:21,200円 |
| 直前講習(高3・高卒) | 1講座(90分×4回)17,400円 / 塾生:17,000円 | |
駿台予備学校 | A<600分(50分×12)講座>コース | 1講座(50分×12単位)29,300円 |
| B<600分(50分×12)講座>コース以外 | 1講座(50分×3単位)13,000円 1講座(50分×6単位)19,700円 1講座(50分×9単位)25,200円 |
参照:河合塾 「冬期・直前講習(高校生・高卒生)受講料・お申し込み方法」 駿台予備学校 冬期講習パンフレット
それぞれ2〜5講座受講すると試算すると、費用相場としては5〜15万円ほどになります。
さらに大学受験に向けて受講講座数が増えればもっと費用がかかりますし、個別指導塾や医学部などの専門塾は予備校よりも割高になりがちです。
塾の冬期講習に通う際の注意点
実際に塾の冬期講習に通うことを決めたら、以下の注意点に気をつけて塾選びをしましょう。
冬期講習に通う目的を明確にする
せっかく冬期講習に通うなら、なんとなく行ったほうがよさそうだからと通うのではなく、明確な目的をもって通うようにしましょう。
たとえば、受験生なら志望校・入試形式に特化した入試対策講座を受講すれば、自学では難しい発展的な入試対策ができます。
受験生以外の場合でも、2学期までの学習内容でわからなかった単元があれば、それを集中的に復習できるよい機会になるでしょう。
冬期講習を有意義な学びの時間にするには、このように受講することで達成したい目的を明確にすることが大切です。
通塾生でない場合、冬期講習のみ受講できるか確認する
冬期講習は夏期講習などと比べて受講期間が短いため、通塾生以外の受付を制限している塾もあります。
したがって、2学期中に塾に通っていなくても冬期講習を受講できるかは最初に確認が必要です。
塾によっては冬期講習中に無料体験授業を実施していたり、登録料などを払えば通塾生と同じように冬期講習を受講できたりすることもあります。
詳しくは各塾の問い合わせ窓口に直接ご相談ください。
個別指導塾と集団指導塾の指導内容の違いを理解して塾を選ぶ
塾の冬期講習と一口にいっても、個別指導塾と集団指導塾では講習内容が異なるので注意して選びましょう。
まず、個別指導塾はスケジュールも指導内容も一人ひとりの学習進度や目的にあわせて設定できるのが特徴です。
決まったコースやクラスがあるわけではなく、担当講師と相談しながら講習内容を決定します。
一方、集団指導塾の冬期講習はあらかじめコースやクラスが設定されています。
それぞれ講習スケジュールや講習内容が決まっているため、その中から自分に適したものを選ぶシステムです。
個別指導塾と集団指導塾ではこのような違いがあるので、申込時にはこれを理解して受講目的にあった塾を選ぶようにしましょう。
複数の塾の冬期講習の内容や費用を比較する
冬期講習の指導内容や期間、費用は塾によって大きく異なります。
そのため、内容や費用に満足できる冬期講習を選びたいなら、複数の塾の冬期講習を調べて比較検討することが大切です。
とくに冬期講習の費用は受講する科目数や講座数、日数などによって変わってくるので、しっかり比較したうえで納得いくものを選ぶようにしましょう。
冬期講習の申込時期
冬期講習の申込開始時期は塾によって異なるので、早めの情報収集が大切です。
一般的に10月中旬〜11月ごろから申込開始となる塾が多く、一部の塾では先行受付も実施されています。
なお、集団指導塾の冬期講習では先着順で受付をしているところもあります。こうした冬期講習は定員を満たすと申し込めないこともあるので、冬期講習を受けたい塾があれば早めに申し込むようにしましょう。
また、冬期講習から塾に通い始める場合、冬期講習前に学力テストの受講が必要なケースが多々あります。
冬期講習の登録とテスト受講に少し時間がかかるので、講習開始ギリギリではなく遅くとも11月中には申し込めると余裕をもって冬期講習を迎えられるでしょう。
冬期講習の内容や費用、注意点を踏まえて自分にあった塾を選ぼう
今回は、塾の冬期講習を検討中の方に向けて、冬期講習の内容や費用相場、塾を選ぶ際の注意点などについて解説してきました。
冬期講習は、受験生にとっては入試前最後の追い込み期間であり、受験生以外であっても学力をアップする大きなチャンスです。
ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、自分に最適な冬期講習がある塾を見つけてみてください。