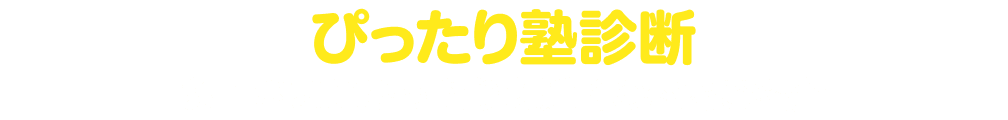冬休みを迎えるにあたって、冬期講習に通うべきかどうかを悩んでいる中学生の方も少なくありません。
冬期講習はただ通えばよいというわけではなく、通うことによるメリットを十分把握することが重要です。
本記事では、中学生が冬期講習に通う意味やメリット、冬期講習の活用法などを解説します。
さらに、通う冬期講習の選び方も紹介しますので、冬期講習に通うべきか悩んでいる中学生の方は、ぜひ参考にしてください。
- 冬期講習は中学生に必要?行くべき理由とは
- 学校の授業内容の総復習と苦手科目の克服
- 定期テスト・入試に向けた短期集中学習
- 家庭学習だけでは補いきれないポイントを学べる
- 冬期講習に行くか迷ったときの判断ポイント
- 学習の目的を明確にする|復習・受験対策・苦手克服
- 現在の学力と目標との差を確認する
- 家庭学習だけで補えるかどうかを考える
- 時間・費用・通いやすさを総合的に確認する
- 学年別に見る冬期講習の活用法
- 中学1〜2年生:基礎固めと学習習慣の定着
- 中学3年生:高校受験直前の総仕上げと弱点補強
- 定期テスト対策中心の短期参加も効果的
- 中学生向け冬期講習の選び方
- 授業形式
- 料金
- カリキュラム
- サポート体制
- 合格実績
- 口コミなどでの評価
- 冬期講習に行くべきか迷ったときに試してほしい方法
- 体験授業を受けて雰囲気を確認する
- 短期プランや1科目からの参加も選択肢に入れる
- 家庭での予習・復習計画を立てて塾利用を比較する
- 冬期講習に行くかどうかは学力や目的に応じて判断しよう
冬期講習は中学生に必要?行くべき理由とは
そもそも、学校の授業が進まない冬休みに、中学生は冬期講習に通う必要はあるのでしょうか。
冬期講習が中学生に必要な理由や中学生が冬期講習に通うことによるメリットは、主に以下が挙げられます。
それぞれについて詳しく解説します。
学校の授業内容の総復習と苦手科目の克服
冬休みの間は学校の授業は進まないので、学校の進度を気にせずに勉強ができます。これまでに学んだことを総復習して理解度を深めるのに、冬期講習はまたとないチャンスといえるでしょう。
また、冬期講習では多くの中学生が苦手としている分野に関して、集中的に講義をすることもあります。そういった講義を受講することで、苦手分野の克服にもつながります。
定期テスト・入試に向けた短期集中学習
中1や中2は冬休みが終わって1か月~1か月半程度すれば期末テストの時期になり、中3は冬休みが終わればすぐに受験を迎えます。
冬期講習では、定期テストや入試に向けて短期的に集中学習をおこなうことが可能です。「冬期講習でしっかり勉強した」という自負は、テストや入試でのよい結果につながるでしょう。
家庭学習だけでは補いきれないポイントを学べる
冬期講習に通わずとも、自宅での学習でもある程度の勉強はできます。とはいえ家庭学習だけでは細かいところまで理解が及ばない場合もあるでしょう。また、勉強中にわからないことが出てきても、その場ですぐに解決できません。
冬期講習に通うことで細かいポイントまでしっかりチェックできるだけでなく、わからないことがあった場合にも、講師にすぐに質問できます。
冬期講習に行くか迷ったときの判断ポイント
もうすぐ冬休みを迎えるものの、まだ冬期講習に行くべきか悩んでいる中学生の方もいるかもしれません。
冬期講習に行くか迷っているのであれば、以下に挙げるポイントを意識したうえで判断するとよいでしょう。
それぞれの判断ポイントについて詳しく解説します。
学習の目的を明確にする|復習・受験対策・苦手克服
冬期講習は行くこと自体が目的ではなく、何かしらの目的を達成するための手段です。目的は人によって異なりますが、主なものとしては復習・受験対策・苦手克服などが挙げられます。
塾に行くべきかどうかを判断するためには、その目的を達成しようと思ったときに、家庭学習だけでどうにかできそうかを考えてみるとよいでしょう。
家庭学習だけでは達成が難しいのであれば、冬期講習に通うことをおすすすめします。
現在の学力と目標との差を確認する
高校受験に合格するためには、学力を求められる水準まで引き上げなければなりません。そのためには、現在の自分の学力と求められる学力の間にどれくらい差があるのかを、適切に判断する必要があります。
差が大きいと、残された時間でギャップを埋めるのはなかなか大変です。しかし、冬期講習を利用すれば短期間で学力を大きく向上させられる可能性があります。
家庭学習だけで補えるかどうかを考える
冬期講習は、学校の授業が進まない間に勉強ができる数少ない機会です。学校が始まってしまえば学校の授業についていくための勉強に時間を費やすことになるので、これまでの復習などを時間をとっておこなうのはなかなか難しいでしょう。
冬休みにおこなうべき勉強を家庭学習だけでこなすのが難しいと思われる場合は、冬期講習で家庭学習だけでは足りないところを補ってもらうのがおすすめです。
時間・費用・通いやすさを総合的に確認する
冬期講習に通えば、何かしらの成果を得て、通ったことがプラスに働く可能性は高いです。ただし、冬期講習には費用がかかりますし、塾の立地によっては往復でかなりの時間を要する場合もあります。
そういった時間や費用に見合うようなメリットが得られそうかどうか、しっかり吟味しましょう。
学年別に見る冬期講習の活用法
中学校に入って最初の冬休みを迎える中1、来年には受験学年になる中2、受験を目前に控えている中3それぞれにとって、冬期講習をどのような形で活用すべきかは異なります。
ここからは、学年別の冬期講習の活用法を紹介します。
中学1〜2年生:基礎固めと学習習慣の定着
中1や中2は、来たるべき受験に備えて学校で習ったことをしっかりと定着させることが重要です。そうすることで、中3になったときに「1・2年の内容を全然覚えてない…」と焦らずに済みます。
また、冬期講習に通って半ば強制的に勉強することは、学習習慣の定着にもつながります。自然と学習する習慣を身につけられれば、受験勉強に励むときの苦労も少なくなるでしょう。
中学3年生:高校受験直前の総仕上げと弱点補強
中3は冬期講習が終われば、すぐに私立の受験を迎えます。そのため、冬期講習は受験直前の総仕上げと弱点補強に充てるのが望ましいです。
冬期講習では受験を意識した実践形式の演習もおこなわれるので、そういった機会を活用して受験本番に平常心で臨めるようにしましょう。
定期テスト対策中心の短期参加も効果的
冬期講習は冬休み中ずっとおこなっている塾が多いですが、その期間、毎日通うことが必須というわけではありません。定期テスト対策を目的に、1クールだけ、1講義だけといった形で受講することも可能です。
また、集団授業の塾ではクラスやコースごとにカリキュラムが決められていますが、個別指導塾では生徒ごとにオーダーメイドのカリキュラムを組んでもらえます。定期テスト対策をおこなうために冬期講習に通うのであれば、その旨を講師に伝えて専用のカリキュラムを組んでもらうとよいでしょう。
「冬期講習に通う目的は何か」ということを意識することで、冬期講習をより効率的に活用できるようになります。
中学生向け冬期講習の選び方
冬期講習は、自分の性格や目的にあったところを選ばなければ期待していたような効果が得られないかもしれません。
中学生が冬期講習を選ぶときに重視すべきポイントとしては、主に以下が挙げられます。
それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
授業形式
冬期講習の授業形式は、集団授業・個別指導・映像授業・オンラインなど、塾によってさまざまです。
集団授業は、学校の授業と同じように十人~数十人程度の生徒と一緒に授業を受ける形式です。クラスはレベル別で分けられていることが多いので、同じくらいの学力の生徒と一緒に切磋琢磨できる点がメリットです。
ただし、お子さんによっては「比べられている感じがして嫌だ」「質問しにくい」と感じることもあるかもしれません。
個別指導では、講師1名に対して生徒が1~3名程度で授業がおこなわれます。マンツーマンもしくはそれに近い形での授業になるので、授業は講師と生徒で会話を交わしながらおこなわれるのが一般的です。
生徒の理解度や進度に応じて柔軟にカリキュラムを組んでもらえ、講師に質問をしやすいのもメリットです。ただし、講師と生徒の距離が近いことで緊張感が減ってしまうケースも考えられます。
映像授業では、専用のブースで事前に録画された授業を見る形で授業を受けられます。映像なので、気になるところは繰り返し再生することで理解を深められます。ただし、リアルタイムの授業ではないので、理解が難しかった場合にその場で質問し、すぐに解決するのは難しいでしょう。
オンラインには、映像授業タイプとオンラインでの個別指導のタイプがあり、近くに塾がない方や、高品質の指導を受けたい方に向いています。
さまざまな形式の授業のなかから、自分にあっていると思うものを選ぶことが重要です。
料金
冬期講習は、受講する講義の種類や数によって料金が変わります。とくに中3の場合、子どもを志望校に合格させてくれるなら費用は惜しまないという保護者も多いかもしれません。
とはいえ、可能であればなるべく安いところを選んで家計への負担を軽減したいという方もいるでしょう。
塾の公式サイトに掲載されている情報だけで料金を計算できる場合もありますが、計算が難しい場合もあります。後者の場合は、体験授業後の面談などで料金について確認することをおすすめします。
カリキュラム
冬期講習は、塾ごとにカリキュラムが異なります。2学期の復習を重点的におこなうところもあれば、学年の復習を広くおこなうところ、受験対策をメインにしたところもあるでしょう。
目的と合致するカリキュラムを設けている冬期講習を選ぶことで、学習効果が高まり、納得のいく勉強につながります。
先述した料金と同様に、カリキュラムの詳細がわからない場合は、教室に問い合わせてみるのがおすすめです。
サポート体制
サポート体制の内容も、冬期講習選びで確認すべきポイントのひとつです。
自習室で勉強ができれば、自宅では集中できない子でも集中できる環境で勉強できますし、質問対応可能な講師が常に待機していれば、わからないところが出てきてもすぐに解消できます。
また、学校の宿題対応もおこなってくれるような塾であれば保護者の方も安心です。
塾の公式サイトで確認したり、体験授業を受けたうえでサポート体制について確認したりするとよいでしょう。
合格実績
とくに中3の場合、志望校合格を目指して冬期講習に通うからには、志望校への合格実績が豊富な塾を選ぶのが望ましいです。
公式サイトで合格実績を公開している塾が多いので、そういった情報をもとにして塾選びをおこなうのがおすすめです。
塾によっては教室ごとの合格実績まで細かく公開していることもあるので、その場合は無理なく通える教室のなかで、合格実績が優れている教室を選ぶとよいでしょう。
口コミなどでの評価
塾は実際に通ってみるまで良し悪しがわからないこともありますが、入塾前に情報をしっかり収集しておくことで、あう・あわないの判断材料のひとつになります。
とくに、同じような境遇の人の口コミは参考になることが多いです。塾に関して授業内容や講師の質などの口コミをまとめているようなサイトもあるので、塾選びの際に参考にするのもよいでしょう。
冬期講習に行くべきか迷ったときに試してほしい方法
冬期講習に行くべきなのかどうか、考えているだけではよくわからない中学生の方もいるのではないでしょうか。
そんなときには、以下に挙げる方法を試してみることで、冬期講習に通うべきかどうか、冬期講習での目標などがハッキリする可能性があります。
それぞれの方法について詳しく解説します。
体験授業を受けて雰囲気を確認する
塾によっては、実際に受講する前に体験授業で、授業の雰囲気や講師の指導方法などを確認できる場合があります。体験授業を受ければ、自分にあう・あわないは何となくわかることが多いです。
あっていると思えば通塾を検討すればよいですし、イマイチだと感じたら別の塾を考えればよいでしょう。
短期プランや1科目からの参加も選択肢に入れる
冬期講習が始まってからでも、講習後半の講義に参加できる場合があります。
ひとまず1クールや1科目だけ受講してみて、通ったほうがよいと思えたら、後半の日程で追加受講するのも選択肢のひとつといえます。
家庭での予習・復習計画を立てて塾利用を比較する
冬期講習のカリキュラムは、塾によって異なります。実際に学習計画を立ててみれば、自学自習で対応できそうな内容と塾で教えてもらったほうがよい内容が、自ずとわかってきます。
自分の学習計画をもとに、自分にとって一番あいそうなカリキュラムを提供している冬期講習を選ぶとよいでしょう。
冬期講習に行くかどうかは学力や目的に応じて判断しよう
中学生は冬期講習に通うことで、学校の授業内容の総復習をおこなったり、苦手単元の克服をしたりすることができます。
冬期講習に通うべきかどうか迷っている方は、学習の目的を明確にし、冬休み中におこなうべき勉強を家庭学習だけでこなせるかどうかを考えてみるとよいでしょう。
通う塾を選ぶ際は、授業形式や設けられているカリキュラム、サポート体制などをもとに比較することで、自分にあった冬期講習を選びやすくなります。
塾に関する口コミをまとめているサイトもあるので、そういったところを利用するのもおすすめですよ。