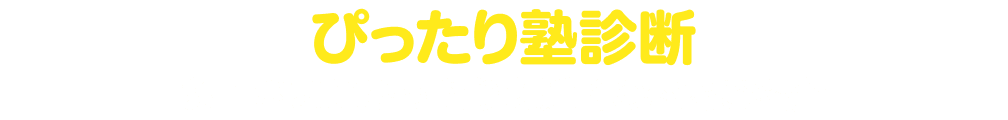「数学の授業について行けない」「教科書を見ても内容が入ってこない」など、数学に苦手意識を持つ人は多いのではないでしょうか。
中学・高校になると、二次方程式や微積分など難しい内容も増えてきます。ひとつの単元でつまずくと、その後の単元もまったく理解ができず、成績が下がってしまうお子さんも少なくありません。
本記事では、数学の苦手克服のために効果的な対策方法を5つ紹介します。役立つツールや、保護者のサポート方法も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
「数学が苦手……」まずはその理由を探ろう
数学に対する苦手を払拭したいという方は、まず「なぜ苦手意識を持ったのか?」を明確にしましょう。
よくある3つの理由について、以下で解説します。
特定の単元から理解できなくなった
とくに多いのは、中学〜高校の何らかの単元が理解できていないケースです。とくに、以下の単元は「難しい」と感じる人が多いとされています。
まずは、「高校1年生の後半からわからなくなってしまった」「中学時代から苦手だった」など、数学に対する苦手意識を持ったタイミングを思い出してみましょう。過去の教科書を読み返したり、定期テストの点数を振り返ったりすると、つまずいた単元を明確にできるかもしれません。
いつから苦手になったか思い出したら、その単元から復習をしていきましょう。「ほかの単元とどう関連するか?」を意識しながら復習すると、その後の単元もスムーズに復習できます。
数学(算数)に対する苦手意識が強い
とくに苦手な単元はないのに、なんとなく数学が苦手だと感じている人もいます。「国語のほうが理解しやすい」「数学の授業が退屈」「先生が苦手」などの理由で、数学は嫌と思い込んでしまっているケースです。
苦手意識の強い人や、学習意欲の低い人は、まず数学を学ぶ理由を理解するのが近道でしょう。詳細は後述しますが、 自分自身の日々の暮らしにおいて数学がどのように役立つか・役立っているのかがわかれば、苦手・嫌いといった感情が和らぐ可能性があります。
昨今はYouTubeやTikTokなどのソーシャルメディアでも、数学を学ぶ理由を紹介している動画や、おもしろく授業している動画も多く投稿されています。こうしたコンテンツを、数学嫌いを克服するためのきっかけとして活用するのもよいでしょう。
学習全般で集中力が続きにくい
体育や部活動など、体を動かす時間が好きな一方で、数学や国語など机に向かって学習する教科が好きではない人もいるでしょう。
もし、スポーツが好きで数学が嫌いなら、スポーツに数学や数学的思考がいかに重要かを考えてみましょう。たとえばスポーツの場合、戦略を練って、理論的に試合を展開していく思考力が重要となっています。フィジカルの高さや技術だけでは、スポーツで勝つことはできないのです。
「数学がスポーツや部活動にいかに活きるのか」を理解すれば、数学に対するモチベーションを高めるきっかけになります。部活や習い事の先生と相談して、数学がどのように役立つか説明してもらうのも、重要性を知る方法としておすすめです。
数学を学ぶ意味を再確認しよう
すでに触れた部分もありますが、苦手な数学を克服するためには、数学が自分自身の生活にどう関与しているのかを考え、学習する意味を再確認しておかなければなりません。
たとえば、数学を学ぶと以下の点で役立ちます。
それでは、数学を学ぶ意味やメリットについて、以下で詳しく解説します。
日々の計算がしやすくなる
最も身近な例ですが、数学が得意になると、割引価格や単価計算がすぐにできて便利です。
「1,450円が20%OFFってことは、1,160円だな」「7個入1,400円だから1個200円だな」などさっと計算ができて、会計をスムーズに済ませたり、節約をしたりするのに役立つでしょう。
割り勘計算、料理の分量計算、時間の計算などもスムーズにできるようになります。数学の力は、日常を支える確かな武器となるのです。計算力が身につけば、暮らしの中の多くの場面で冷静かつ的確な判断が可能になるでしょう。
論理的思考が身につく
論理的思考力とは、簡単にいうと「筋道を立てて矛盾のないように考え、結論を導き出す考え方」のことです。論理的思考が身につくと、以下のようなメリットがあります。
たとえば何らかのトラブルに遭遇した場合も、やるべきこと、後回しでよいこと、無駄なことを分類し、優先順位を理論的に整理して動けます。また、何か失敗してしまったとき、感情的にならず「なぜこうなったのか?」「何が課題でそれに対する解決策は何か?」を冷静に考えられるでしょう。
このように、数学を学んで論理的思考が身につくと、日常生活のあらゆる場面でメリットがあります。
よりハイレベルな学校へと進学できる
よりハイレベルな学校へと進学したい場合、数学力を伸ばしておくことで、全体の成績を押し上げるだけではなく、ほかの教科の問題解決に役立つ可能性があります。
高校受験や大学受験では数学の配点が高く設定されていることも多く、全体を占める割合も高い傾向があります。数学の苦手を克服しておくことで全体の平均点を押し上げられるため、志望校合格にも一歩近づくでしょう。
また、数学を学ぶ上で養った思考力や能力が、ほかも科目を解くときにも役立つ可能性があります。たとえば、社会科や理科においては、データを読み解く力として数学力を活かせるでしょう。
数学の苦手を克服する5つの方法
では、実際に数学の苦手克服を目指した場合、どのように学習を進めていけばよいのでしょうか。 数学の苦手を克服する方法や勉強方法の例として以下があげられます。
以下の項目では、具体的にどのような勉強をすればよいのか、詳しく解説します。
基礎固めを徹底する
まずは、基礎的な内容を復習しましょう。基礎知識が抜けていると、それらに付随してわからない単元が増えてしまい、結果として苦手意識が高まってしまいます。理解不足の単元を復習すれば、それをきっかけになって数学が理解できるようになるケースも多いでしょう。
復習の方法としては、まとめ教材や教科書を使うのがおすすめです。たとえば、高校生が中学まで遡って復習するなら「中学3年間の数学」をまとめた参考書を活用すると、効率的に学習できるでしょう。
教科書を最初から読み返してみる、自分なりにノートに内容をまとめてみるなどして、基礎固めをしていきましょう。
簡単な問題からステップアップし成功体験を積む
数学が嫌いな人は、成功体験を積むのが重要です。「できない」「苦手だ」と思っていると、いつまでも苦手なままになってしまいます。「自分でもできそう!」と感じられるきっかけを作りましょう。
まずは、簡単な問題集を用意して、正解できたという成功体験を積み重ねましょう。中学3年生が1〜2年生の問題集をやっても、高校生が中学生向けのものをやっても問題ありません。とにかく「これなら解ける」とスムーズに解ける感覚を掴むのが重要です。
こうして成功体験を積むと、数学に対するネガティブなイメージが少しずつ薄れてきます。以前よりも数学に対して前向きに臨めるようになったら、少しずついまやっている内容の問題にもチャレンジしてみてください。
不正解だった問題を活用する
これまで間違えた問題をまとめて、間違えてしまった原因を分析するのもおすすめです。間違いをまとめてみると、間違えやすいポイントがわかったり、理解できていない単元が判明したりします。
まずは、過去のプリントやドリル、定期テストの解答などを集めてください。そして、ひとつ前の定期テストの範囲に関するミスをまとめてみましょう。ノートにまとめてもよいですし、面倒ならミスした回答と正解を交互に写真に撮ってまとめるのもおすすめです。
自分専用の不正解集を作成したら、繰り返し復習していきましょう。なかには「〇〇が理解できればほとんどのミスはなくせるようだ」と、共通点が見つかる人もいるはずです。
間違いを振り返ったら、類題を解いてみると、より理解が深まり学習内容も定着しやすいのでおすすめです。
思考力を養う
思考力を養うことも、数学の成績伸ばすためには重要です。すぐに答えを見ずに粘り強く考える習慣をつけると、思考力や集中力が身につきます。
途中式を丁寧に書く意識をつけるのも、思考力を養うのにおすすめです。間違えを振り返る際、途中式を丁寧に書いておけば、どこで間違えたかわかって振り返りがしやすくなります。
「とくに苦手な科目はない」と感じる人は、まず思考力や集中力といった数学を解くのに必要な基礎力を身につけることから始めてみましょう。
学習習慣を身につける
苦手な科目ほど、1日5分でもよいので学習習慣を身につけるとよいでしょう。学習習慣が身につけば、1日あたりは数分であっても、数学力は着実にアップしていきます。
確実に習慣化していくために、1回あたりの負担はできる限り小さくしましょう。習慣化が苦手な人は、週1〜2回やろうと思っても、忘れたり面倒になったりしてやらなくなりがちです。毎日5分であれば、忘れずに実行できて習慣化もしやすいでしょう。
また「帰ったら手を洗ってリビングで5分だけやる」「晩ごはんの時に参考書を用意しておいて、食後にリビングで10分やる」など、前後の行動もあわせてルーティンを組んでおくと、習慣化しやすくなります。
数学の苦手を克服するのに役立つツールや手段
数学に対する苦手意識を克服するためには、参考書や塾を活用するのもおすすめです。活用できるツール・手段としては、以下のような例があげられます。
それぞれどのように活用すればよいかを以下で解説します。
参考書や問題集
参考書としては、小学6年間や中学3年間の内容をまとめた「まとめ教材」がおすすめです。大人向けの教材も多くありますが、学生でも問題なく使用できます。
まとめ教材は、これまでの内容を振り振り返りやすいようにさまざまな工夫がされています。基礎が定着していない、どこかの単元からわからなくなったといった人には最適です。
参考書・問題集の選び方に迷ったら、ひとまず大型書店に行ってみましょう。参考書をいくつか試し読みしてみると「これは読みやすいな」「これは読みにくそう」と違いがわかって、自分にあったものを探しやすくなります。
塾や家庭教師
効率よく学習するなら、塾や家庭教師を活用するのがおすすめです。苦手科目は、どうしても頭に入りにくく、集中もしにくいでしょう。中学〜高校からは学習内容も難しくなり、親がサポートしきれない場面も増えてきます。
塾や家庭教師なら、勉強しなければならない環境をつくれるので、自分一人よりも学習習慣は身につきやすくなります。また、わからない部分を丁寧に解説してもらえるので、独学と比べて苦手を克服しやすいでしょう。
極端に苦手意識がある場合は、個別指導塾や家庭教師がおすすめです。費用はかかりますが、苦手科目だけ週1〜2回であれば、比較的安く利用できます。
友だちと通うのがあっている、負けず嫌いで集団のなかで競い合うのが好きな人は、集団指導塾がおすすめです。ほかの生徒と切磋琢磨しながら、緊張感をもって学習ができます。
映像授業
部活や習い事が忙しい、文章を読むのが苦手といった人なら、映像授業がおすすめです。YouTubeなどの映像コンテンツが好きな人にも、映像授業が適しています。
最初は1日1本だけ、1.5倍速でもよいので、とにかく映像教材を視聴する習慣を身につけるところからスタートしましょう。前述のとおり、習慣化のためには、少しでも毎日続けることが大切だからです。
最初から有料教材はハードルが高いと感じる場合は、大日本図書が文科省教材として30秒の動画教材を作成・公開しているので活用してみてください。YouTubeなどの動画教材を活用するのもよいでしょう。
ただし、SNSの映像教材は内容に誤りがあるケースも少なくありません。長く活用したい、受験対策に利用したいと考えている場合は、きちんと内容の校正がされている有料教材を使用することをおすすめします。
【保護者向け】数学が苦手なお子さんに対するサポート
数学が苦手なお子さんを持つ保護者の方は、サポート方法に悩むことも多いでしょう。具体的なサポート方法を以下にまとめました。
否定しない、急かさない
まずは、否定したり急かしたりしないように意識しましょう。とくに「数学苦手なんだから」「なんでこんなこともわからないの」と否定するのは避けてください。
中高生のお子さんは、親に否定されたり急かされたりすると、非常に強いストレスを感じます。親子間のコミュニケーションがうまく取れなくなる原因になるため避けましょう。
マイペースなお子さんや、時間感覚が弱い人については、適度に勉強を促してあげたほうがよいケースもあります。しかし、基本的にはミスに対して怒ったり、勉強するよう急かしたりはせず、本人のペースを尊重してあげるのがよいでしょう。
積極的に学習のプロを頼る
中高生の数学は内容が難しくなるため、親が教えられない内容も増えてくるでしょう。家庭でのサポートが難しく感じた場合は、塾や家庭教師といったプロ頼るのがおすすめです。費用はかかりますが、そのぶんわかりやすく、本人にあった教え方で指導をしてくれます。
お子さんがなかなか理解してくれなかったり、保護者としても内容が難しいと感じたりする場合、そして「どうしてわからないの?」と否定的な感情をいだいてしまう場合には、積極的にプロに頼っていきましょう。
まとめ
数学が苦手な人は、基礎から丁寧に学習しなおすのがおすすめです。わからない単元を克服できれば、その後の単元もスムーズに理解できるようになります。
また、ネガティブなイメージを払拭するために、成功体験を積み重ねたり、数学を学ぶ意味を考え直したりするのも効果的でしょう。
ただし、中学・高校になると難しい単元も登場し、自力では理解できない内容も増えてきます。自分一人では対処できないと感じる場合には、周囲の友だちや、塾・家庭教師に頼ってみましょう。