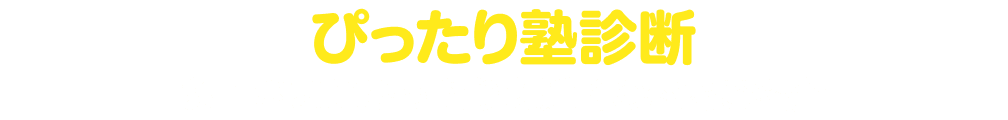勉強のやり方がわからず悩んでいる学生や、悩んでいる子どもにできるアドバイスはないか探している保護者の方もいるのではないでしょうか。
学校では勉強の内容は教わっても、個別に勉強のやり方まで教えてくれるケースは多くありません。勉強のやり方は誰かが教えてくれるわけではないため、自分で最適な方法を見つける必要があります。
本記事では、勉強のやり方がわからないと感じる原因や、成績を伸ばすための基本的な勉強のサイクルを紹介します。
科目別に意識するべき勉強のやり方も紹介するので、何をすればよいかわからず悩んでいる方や、わが子にアドバイスをしたい保護者の方はぜひ参考にしてください。
- 「勉強のやり方がわからない」のはなぜ?主な理由や原因
- 勉強する目的が明確になっていない
- 苦手科目や弱点がわかっていない
- 学校では勉強のやり方まで教えてくれないから
- 勉強のやり方がわからない学生必見!効率的に成績を上げる基本的なサイクル
- ①明確な目標を立てる
- ②現状を客観的に把握する
- ③学習計画を立てる
- ④インプットとアウトプットをバランスよく繰り返す
- ⑤苦手科目や間違えた箇所を復習する
- ⑥改善を繰り返しながら勉強を習慣化する
- 【主要科目】勉強のやり方や意識すべきポイント
- 国語の勉強方法で意識すべきポイント
- 数学の勉強方法で意識すべきポイント
- 英語の勉強方法で意識すべきポイント
- 理科・物理・化学の勉強方法で意識すべきポイント
- 社会・地理・歴史の勉強方法で意識すべきポイント
- 勉強のやり方がわからない人が注意したいNG勉強法
- 勉強時間を長くすることだけにこだわる
- 教科書を読んだだけで理解したつもりになってしまう
- 詰め込み学習や一夜漬けに頼る
- インプットが多く問題演習などのアウトプットが少ない
- 勉強のやり方がわからないのは当然!学習方法を身につけて成績アップを目指そう
「勉強のやり方がわからない」のはなぜ?主な理由や原因
勉強のやり方がわからないと感じる主な理由や原因には、以下のことが考えられます。
それぞれ詳しく紹介します。
勉強する目的が明確になっていない
勉強の目的がはっきりしていないと、学習に対する意欲が湧かず、どのように取り組めばよいのかも見えてきません。
たとえば、親に「勉強しなさい」「勉強は将来にとって大切だから」といわれても、将来の夢や行きたい志望校など具体的な目標がないと、実感が湧かず勉強に意義を見出しにくいでしょう。
ゴールがなければ計画的に勉強できず、何から始めればよいのかもわからない状態に陥ってしまいます。勉強のやり方も場当たり的になり、効率も悪くなってしまうため注意が必要です。
苦手科目や弱点がわかっていない
目的や目標があっても、苦手な科目や注力すべきポイントが明確でないと、勉強方法に困ってしまいます。
とくに中学生や高校生は学習範囲が広く、どこが理解できていないのかがわからないと、何を優先して勉強すればよいか判断が難しくなります。
「とりあえず全科目勉強する」と始めても、結局すべてが中途半端になってしまうこともあるでしょう。勉強の方向性や、効率よく成績を上げていくやり方を見つけるためには、自分の弱点を把握し、克服するために何をすればよいかを考えることが大切です。
学校では勉強のやり方まで教えてくれないから
学校では教科書の内容やテスト範囲については教えてくれますが、「どうやって勉強すればよいか」まで丁寧に教えてくれるケースは少ないでしょう。
家庭学習に慣れていない状態で学習を進めると、非効率な勉強になってしまい「時間をかけて勉強しているのに点数が伸びない」などの状態に陥ることがあるかもしれません。
また、人それぞれ適した勉強方法は異なります。ある人にとって効率的な方法も、ある人にとっては非効率なやり方になってしまうかもしれません。
たとえば、とにかく問題を解いたほうが覚えやすい人や、図やイラストなどにしたほうが覚えやすい人など、適切な学習方法はさまざまです。
効率的かつ自分にあった勉強方法は誰かが教えてくれるのを待つのではなく、自分で考えたり、先生や塾の講師に相談したりすることが大切です。
勉強のやり方がわからない学生必見!効率的に成績を上げる基本的なサイクル
勉強のやり方がわからない方は、学習の基本的なサイクルを覚えておきましょう。
サイクルに沿って学習を進めることで、着実な学力の向上が期待できます。以下の6つのステップで進めていきましょう。
①明確な目標を立てる
勉強を始める前に、まずは明確な目標を立てることが大切です。目標が曖昧なままでは、勉強のやり方も定まらず、モチベーションも続きません。
たとえば、「志望校に合格する」などの長期的な目標から、「〇月の模試でAランクの評価を獲得する」などの中期目標、「次の数学のテストで20点アップを目指す」などの短期目標を立てましょう。
具体的な目標を立てると、達成するために必要な時間や勉強量、取り組むべき内容が見えてきます。
②現状を客観的に把握する
目標であるゴールが決まったら、次は「今の自分の実力と現状」を把握しましょう。たとえば「次の数学のテストで20点アップを目指す」と目標を立てた場合、現在の自分が20点伸ばすためには、何を克服すべきなのかを把握します。
過去のテストや模擬試験の結果をもとに、応用問題を解く力が足りないのか、そもそも基礎学力が足りていないのか、計算問題や証明問題など、どこでミスしているのかなどの弱点を把握しましょう。
現状を理解することで、勉強の優先順位がはっきりし、やるべきことや、取り入れる勉強方法が明確になります。
③学習計画を立てる
現状の分析ができたら、次は学習計画を立てましょう。目標までの時間は有限であり、多くの場合、複数の科目を同時進行で対策しなければなりません。
ただ漠然と勉強するのではなく、「いつ、何を、どのくらい」学習するのかを具体的に決めておくことが大切です。
たとえば、「月曜日は英語の単語暗記と文法を復習する」「土曜日と日曜日は時間があるので試験形式で時間を区切って問題集や過去問を解く」など具体的な計画を立てましょう。
科目や内容、時間を明確に設定すれば「今日は何を勉強しよう」と迷わず、すぐに勉強に取りかかれます。
④インプットとアウトプットをバランスよく繰り返す
勉強は、知識を入れる「インプット」と、実際に演習する「アウトプット」のバランスを考えておこなうことが大切です。
たとえば、アウトプットを重視しすぎても、知識が入っていなければ同じ結果を繰り返してしまいます。反対に、インプットばかりを繰り返しても、テストや応用問題で活用できなければ意味がありません。
学校の授業は、先生の説明を聞く、教科書を読む、授業の内容をノートに写すなど、インプットがメインです。自宅学習には問題演習やテスト形式での練習など、アウトプットの要素を積極的に取り入れましょう。
アウトプットは記憶の定着にも効果があるとされています。インプットとアウトプットの繰り返しは、「覚えているつもり」「勉強しているつもり」を防ぐのにも効果的です。
⑤苦手科目や間違えた箇所を復習する
勉強した内容やテストで間違った箇所はそのままにせず、「なぜわからないのか」「どこができなかったのか」を確認し、復習することが大切です。
とくに、テストや問題演習で間違えた箇所を放置すると、次も同じミスを繰り返す可能性があります。解けた問題や得意科目ばかりを勉強していると、成績が伸び悩むかもしれません。
復習することを習慣化して、弱点を補いましょう。自分で解決できない場合は、必要に応じて学校の先生や塾の講師に相談することも大切です。
⑥改善を繰り返しながら勉強を習慣化する
計画通りに勉強しても、思い通りの結果につながらないこともあります。思うような結果が得られなかったのも、ひとつの成果です。
「どうすればもっと効率よくできるか」「今の方法で問題はなかったか」と振り返り、少しずつ改善していく意識が大切です。
たとえば、勉強時間が多すぎてサボってしまうことが多かったなら、1日あたりの学習量を調整する、時間帯を変えるなどを検討しましょう。
反対に、勉強時間が少ないと感じるなら増やすことも検討してみましょう。大切なのは、結果を参考にして次につなげることです。
【主要科目】勉強のやり方や意識すべきポイント
勉強のやり方や意識すべきポイントは科目によって異なります。そこで、ここからは以下の主要科目の具体的な勉強のやり方を紹介します。
紹介する内容はあくまでも一例であり、人によって適した勉強のやり方は異なります。
勉強のやり方がわからないと悩んでいる方は、紹介する内容を参考にしながら、自身に適した方法に調整してください。
国語の勉強方法で意識すべきポイント
国語では、文章の要旨や意図を読み取る「読解力」、短時間で内容を整理する「情報処理能力」、文章を短い文にまとめる「語彙力」や「要約する力」などが求められます。
そのため、国語の勉強は「読む」「考える」「書く」力をバランスよく鍛えることが大切です。漢字や語彙の学習はノートに書くなど、暗記で覚えられるかもしれません。
一方、読解問題を鍛えるには、多くの長文問題に挑戦することが大切です。長文問題では、文章全体の構成を意識して読みましょう。
多くの文章に触れることで、おおまかな構成や流れのパターンがわかると、読むスピードも早くなります。段落ごとの要約をノートにまとめると、文章の流れや主張がつかみやすくなるでしょう。
一般的な試験問題やテストでは、設問の解答につながる根拠となる文章が、本文のなかに必ず存在します。
「自分はこう思うから」ではなく、「本文にこう書いてあるから」と照らし合わせて回答できるように練習することが大切です。
数学の勉強方法で意識すべきポイント
数学の勉強は、基礎を固めることが大切です。まずは教科書や授業で学んだ公式、解き方を理解しましょう。
わからないまま進めると、応用問題に対応できなくなる可能性があります。基本問題を何度も繰り返し解き、公式の使い方を定着させたら、次は応用問題や過去問に挑戦しましょう。
間違った箇所があれば、間違った理由を分析します。計算のケアレスミスであれば問題ないかもしれません。しかし、考え方や解き方が根本的に間違っているなら、基礎に立ち返って復習しましょう。
必要に応じて図にして書いて理解を深める、先生や塾の講師にアドバイスをもらい、わかるまで説明してもらうことが大切です。
英語の勉強方法で意識すべきポイント
英語は、「読む・書く・聞く・話す」が問われる科目です。
志望校の試験問題で重視されるものや、苦手分野を重点的に対策しましょう。そのなかでも、単語と基本文法は欠かせない重要な要素です。毎日少しずつ単語や文法を暗記し、問題集を使ってアウトプットして定着させましょう。
リスニング対策では、教科書の音読や英語音声を聞く習慣をつけることが効果的です。英語の音声に慣れておくと、自然と聞き取りやすくなることもあります。
スピーキング対策では、英文を音読しながら読む方法がおすすめです。繰り返しおこなうことで、頻出する文法なども覚えやすくなります。
英語は母国語でないため、日本に住んでいると日ごろ使わない言語です。まずは英語に慣れることが重要なため、自分のレベルにあった簡単な問題集や参考書を毎日繰り返し、着実に身につけていきましょう。
理科・物理・化学の勉強方法で意識すべきポイント
理科や物理、化学は、用語の暗記に加え、現象のしくみを理解することが大切です。
テストや試験では用語の穴埋めのほか、記述式の問題が出題される傾向にあります。元素記号や用語の暗記でカバーできる部分は、隙間時間を使って効率的に覚えましょう。
加えて、教科書の解説や図をよく読み、基本原則や法則を理解し、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明できるようにすることが大切です。
しかし、教科書を読むだけでは理解しづらい部分も多いかもしれません。実験や実習には積極的に参加し、それでも理解できない場合は、テレビや動画サイトの実験番組なども参考にしましょう。
社会・地理・歴史の勉強方法で意識すべきポイント
社会科は暗記が中心ですが、それゆえに覚えることが多く、単純な暗記では何がどれだったか混乱してしまうことも少なくありません。
たとえば歴史の場合、年号を基準に覚えても「年号と名前だけは覚えているけど、何が起こったか覚えていない、説明できない」という方も多いのではないでしょうか。単に年号を暗記するだけでなく、関連づけて覚えることが効率よく覚えるためのコツです。
文字だけで覚えるのではなく、具体的な人物像や出来事、話の流れ(何がきっかけで誰が何を起こし、歴史がどう変わったのか)と一緒にあわせて覚えると、スムーズに覚えやすくなります。歴史を忠実に再現した漫画なども多いため、必要に応じて活用しましょう。
地理では、地図や資料を見ながら特徴や場所を確認し、国名や地形と結びつけて学ぶと記憶が定着しやすくなります。近年では、動画サイトで世界中の土地を旅する動画なども投稿されているため、具体的なイメージを掴むために活用してみましょう。
暗記が中心の科目だからこそ、混乱しないために、イメージや因果関係を紐づけておくことが大切です。
勉強のやり方がわからない人が注意したいNG勉強法
勉強のやり方がわからないからといって、以下の勉強方法は成果につながりにくいため、避けるようにしましょう。
勉強時間を長くすることだけにこだわる
勉強のやり方がわからないと、「とりあえず時間をかける」ことにこだわってしまうケースが少なくありません。
勉強時間が長いと、頑張った感覚が味わえるでしょう。しかし、かけた時間が成果につながっていないのなら意味がありません。
たとえば、2時間ダラダラと机に向かうより、30分集中して取り組んだほうが成果として出ることもあります。時間をかけるだけではなく、前述した成績を伸ばすためのサイクルを参考にし、効率的な勉強をおこないましょう。
教科書を読んだだけで理解したつもりになってしまう
勉強方法がわからないと、「教科書を読んだ=勉強した」と勘違いしてしまう場合があります。勉強は、成績やテスト、受験で反映させることが大切です。
そのためには、勉強した知識が実際に使えること、しっかり説明できること、数か月後も覚えていることが重要です。
一度触れただけで理解したつもりにならず、定期的に復習する、問題を解いてアウトプットすることを心がけましょう。
詰め込み学習や一夜漬けに頼る
勉強のやり方がわからないと、「テスト前だけ一気に勉強する」などの詰め込み学習や、一夜漬けをおこなってしまうかもしれません。詰め込み学習や一夜漬けは、一時的な効果はあっても、知識が定着しにくく、すぐに忘れてしまうリスクがあります。
とくに受験勉強は長期戦になるため、一時的な成果よりも、継続できる学習方法で少しずつでも着実に覚え、試験日に成果を出すことが求められます。
一夜漬けや詰め込み学習は生活習慣の乱れや体調不良にもつながるため、過度に頼るのは控えましょう。
インプットが多く問題演習などのアウトプットが少ない
教科書を読む、ノートをまとめる、動画を見るなどの「インプット」ばかりで満足してしまうのは危険です。問題を解くなどの「アウトプット」の量も増やしましょう。
授業や動画視聴などのインプットは、基本的に受け身の学習であることから、楽に感じるかもしれません。知識を覚えれば勉強した感覚にもなるでしょう。
しかし、成績アップや志望校の合格に求められるのは、テストや試験問題で点数をとることです。つまり、重要なのは「インプットした知識をどれだけアウトプットできるか」です。
インプットとアウトプットは常にセットであることを忘れず、覚えた知識は使えるようにしておきましょう。
勉強のやり方がわからないのは当然!学習方法を身につけて成績アップを目指そう
学校では勉強のやり方を教えてくれないことが多いため、勉強のやり方がわからないのは、ある種必然的なことかもしれません。
大切なのは、「勉強のやり方がわからない」で終わらせるのではなく「どうすれば効率的な勉強につながるか?」「自分に適した勉強方法は?」など、積極的に考えることです。
自身で課題を見つけ、主体的に取り組む能力は、受験勉強期間や進学後、就職後でも重要な能力になります。紹介した内容を参考にしつつ、自分にあった勉強方法を探してください。
必要に応じて学校の先生や塾の講師に相談し、具体的かつ客観的なアドバイスを受けることもおすすめします。