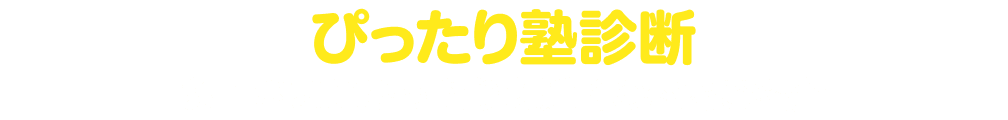小学生の子どもが勉強せず、焦りや不安を感じている保護者の方は少なくありません。
小学生は未熟な部分が多く、学習に取り組む際に親のサポートが必要な場合もあります。しかし、干渉しすぎると勉強嫌いになることも考えられます。
そこで本記事では、小学生の子どもが勉強しない原因や、保護者ができるサポート、声かけの具体例を紹介します。
子どものやる気を削いでしまうNG行動も紹介するので、勉強しないわが子に悩んでいる保護者の方は、ぜひ参考にしてください。
- 小学生の子どもが勉強しない!考えられる6つの原因
- ①学校の授業内容についていけていない
- ②勉強方法がわからない
- ③勉強に意味を感じられていない
- ④ゲームやスポーツなど勉強以外のことに興味・関心が向いている
- ⑤勉強に集中する習慣・環境が整っていない
- ⑥勉強を強制されることに嫌気がさしている
- 勉強しない小学生に効果的な対処法|具体例を紹介
- 勉強習慣が身につくサポートをする
- 小さな成功体験を積ませて自尊心を育む
- 勉強に集中できる時間・学習環境をつくる
- 勉強が楽しくなる・好きになる学習方法を取り入れる
- 子ども本人の悩みや意見を聞く
- 親の声かけで子どものやる気が変わる!具体例を紹介
- 子どものやる気・モチベーションを高める声かけの具体例
- 考える力や自発性を育てる質問型コミュニケーションの具体例
- 小学生の子どもが勉強しないときにやってはいけない親のNG行動
- 勉強することを強制する
- 諦めて放置する
- 叱る・怒ることで恐怖を与えてコントロールする
- 兄弟・姉妹やほかの子どもと比べる
- できなかったことばかりに目を向ける
- 子どもの意見に耳を傾けない
- 小学生の子どもが勉強しないのは普通のこと!親がうまくサポートしてあげよう
小学生の子どもが勉強しない!考えられる6つの原因
小学生が勉強しない理由はさまざまです。「勉強が嫌いだからだ」「怠けているからだ」と決めつけず、原因を明確にして適切に対処しましょう。
小学生が勉強しない原因としては、主に以下のことが考えられます。
それぞれ詳しく紹介します。
①学校の授業内容についていけていない
子どもが勉強しない理由のひとつに、授業の内容が理解できていないことが挙げられます。内容がわからないまま進んでしまうと、授業中もつまらなく感じ、自宅学習のやる気を失ってしまうことも少なくありません。
算数などは、基礎部分でつまずくと応用問題が解けなくなることも多いでしょう。わかならいことがきっかけでその後の授業にもついていけなくと、勉強への苦手意識が強まっていきます。
「わからない」が「楽しくない」「やりたくない」につながっているかもしれません。勉強の苦手意識が強まると「自分は勉強ができない」と、勉強を遠ざける悪循環に陥ることもあります。
②勉強方法がわからない
小学生の場合、どうやって勉強すればよいのかわからない子どもも少なくありません。何をすればよいのかがわからないと、机に向かっても手が進まないこともあります。
小学生は、計画的に学習を進める力が未熟な時期です。勉強するより先に、自主的に学習の目標を立てる力を身につけることが必要な場合もあるでしょう。
親からすると、勉強をサボっているように見えて、ついひとこと言いたくなるかもしれません。しかし、勉強したくない、やる気がないというよりは、勉強のやり方がわからずに困っている可能性もあるため、子どもの状況を理解してあげることが大切です。
③勉強に意味を感じられていない
勉強する目的や意義を実感できなければ、自主的に勉強しようという気持ちになれません。とくに小学生の低学年のうちは進学や受験に対して現実味が薄く、「将来のためだから」といわれてもイメージしづらいでしょう。
知識がどのように役立っているかを日常生活の身近な事柄と紐づけて学ばせ、本人が「もっと知りたい」と、興味・関心をもってくれるよう工夫することも大切です。
④ゲームやスポーツなど勉強以外のことに興味・関心が向いている
ゲームやスポーツ、遊びなど、子どもにとって勉強以外に楽しいことはたくさんあります。子どもは自制心が未熟なことも多く、興味・関心が勉強以外のことに向いていると、勉強は後回しになります。
勉強が嫌いなわけではなく、勉強よりも好きなことに集中したいだけかもしれません。子どもの興味・関心の幅を広げたり、好奇心を育てたりすることも大切なため、勉強以外のことに興味が向くことが一概には悪いとはいえないでしょう。
しかし、勉強がわからなくなると本人にとってマイナスになる可能性もあるため、両者のバランスを考えることも大切です。
⑤勉強に集中する習慣・環境が整っていない
集中して勉強できる環境が整っていないと、学習に取り組むことが難しくなります。たとえば、テレビがついたままの部屋や、周囲がうるさい環境、ゲームやおもちゃが手の届くところにある状態では集中力が続きません。
また、決まった時間に机に向かう習慣が身についていないうちは、集中力を維持することも難しいでしょう。
子どもが自然に勉強するようになるためには、整理整頓する、決まった時間になったらテレビを消して机に向かうなど、「準備」を習慣づけることが大切です。
⑥勉強を強制されることに嫌気がさしている
親から「勉強しなさい」と言われたり、厳しく注意されたりすると、子どもは勉強に対して拒否反応が起こることがあります。「やらされている」という感覚が強くなると、自主的に取り組む意欲が削がれるかもしれません。
「勉強しなければ叱られる、注意される」などの印象やストレスが結びつくと、勉強嫌いになる可能性もあるため注意が必要です。
勉強しない小学生に効果的な対処法|具体例を紹介
勉強しない小学生の原因がわかったところで、ここからは、勉強しない小学生への具体的な対処法を以下に挙げます。
次より各項目について紹介していきます。
勉強習慣が身につくサポートをする
勉強をどれくらい長くするかより、まずは勉強する習慣を身につけさせることが大切です。習慣を身につけさせるためには、まずは決まった時間に短時間から始めましょう。
たとえば、「学校から帰ってきたら宿題を終わらせて、その後にゲームをしていいよ」「毎日夕食前の10分だけ算数ドリルをやろう」など、時間と内容を固定し、無理なく取り組める習慣をつくることが大切です。
低学年の子どもや、ひとりで取り組むことが難しい子どもは、親がそばに座って一緒に問題を解くなどの工夫をしましょう。親は問題の答えを教えるのではなく、ヒントを与えたり、考え方の道しるべを教えたりと、子どものサポート役に徹してください。
まずは成績やテストの点数を伸ばすことではなく、「勉強することが当たり前」と感じる習慣を身につけることが重要です。
小さな成功体験を積ませて自尊心を育む
勉強にポジティブな印象をもてば、自主的に取り組める可能性があります。簡単に解ける問題からはじめたり、成果が目にみえるように工夫したりして、成功体験を積ませましょう。
たとえば、低学年であれば、漢字を正しく書けたら好きなキャラクターのシールをノートに貼ってあげる、計算問題を3問解いたらスタンプを押すなど、簡単な工夫で構いません。
高学年なら、難しい応用問題だけではなく、比較的簡単に解ける問題が多いドリルを買ってあげるなどが効果的です。
保護者は、子どもができたことや成果に対して「よくできたね」「頑張ったね」と褒めてあげましょう。目に見える成果や親からの評価は子どもの自尊心を育てます。
勉強に対して自信がもてるようになると、「もっと難しい問題をやってみたい」「別の教科も成績を伸ばしたい」と、自発的に取り組むようになるかもしれません。
勉強に集中できる時間・学習環境をつくる
子どもが勉強に集中できる環境をつくるのも保護者ができるサポートのひとつです。たとえば、学習に適した机や椅子を用意する、勉強時間になったらテレビを消して静かにする、などもよいでしょう。
子どもが勉強しているときは親も資格の勉強をする、なども効果があるかもしれません。小さな兄弟・姉妹がいたり、自宅周辺の騒音が気になったりする場合は、塾に通わせるのもひとつの手です。
塾には自習室や子どもの指導に長けた講師、切磋琢磨できる仲間など、勉強に集中できる環境が整っています。
勉強が楽しくなる・好きになる学習方法を取り入れる
勉強に対する苦手意識をなくすためには、「楽しい」「好き」と思える工夫を取り入れることが効果的です。
たとえば、算数が苦手な子に対し、果物や飲み物など日常生活のなかにある身近なものを使って問題をつくるのもよいでしょう。
漢字を覚えるのが苦手な子どもに対し、家族と一緒にカードゲームやアプリを使ってクイズ形式で出題するなどして、「楽しい」という感情と学習をつなげる工夫をしてみてください。
遊びながら学べる環境をつくると、勉強に対する抵抗感が薄れて、自主的に学ぶ姿勢が育つでしょう。
子ども本人の悩みや意見を聞く
親は、勉強しないわが子を叱るのではなく、まずは子ども本人の悩みや意見を聞くことからはじめましょう。
前述したとおり、子どもが勉強しない原因はさまざまです。たとえば「勉強のやり方がわからない」と悩んでいる子どもに集中できる環境を用意しても学習が進まない可能性があります。
「将来の目標がなく、勉強に意味を感じられない」と悩んでいる子どもや、勉強以外のことに興味が向いている子どもに、勉強のやり方を教えても積極的に取り組めるとは限りません。
親の主観で悩みを判断してサポートするのではなく、子どもの話をよく聞いて、一緒に解決策を探したり、悩みに寄り添い、対応を考えたりするようにしましょう。
親の声かけで子どものやる気が変わる!具体例を紹介
子どもにとって親の存在は大きなものです。親のひとことで、子どもはやる気になったり、自信をもったりすることあります。ここからは、子どもに対する親の声かけの具体例を紹介します。
それぞれ詳しく紹介します。
子どものやる気・モチベーションを高める声かけの具体例
親の声かけにより、子どもの勉強へのモチベーションが高まることもあります。テストの点数や成績だけにフォーカスせず、過程を評価する声かけが大切です。
たとえば、「いわれる前に机に向かえてすごい!」「〇〇分集中して勉強をがんばったね!」など、努力に対するポジティブな評価は子どもの自信につながるでしょう。
「昨日より宿題を終わらせるのが速くなってるね!」など、具体的に褒めると子ども自身が成長を実感しやすいかもしれません。
「わからないところを自分で調べてえらいね」など、自主性をほめる声かけも効果的です。問題を間違えても「次はできるよ!」と励ましましょう。
声かけにより勉強へのモチベーションが高まり、自主性が育まれれば、学習習慣が身ににつき、成績にも反映されることが期待できます。
考える力や自発性を育てる質問型コミュニケーションの具体例
問いかける形のコミュニケーションは、子どもの自発性を育みます。
たとえば、「今日はどの教科からやる?」や「この問題はどうやって答えを考えたの?」と質問すると、子どもは自分の判断を言葉にする、考える機会が生まれます。
また「わからないところは、どうやって調べればよいと思う?」など、解決方法に気づかせる問いかけも有効です。
「どこが難しかった?」などと質問すれば、子どもが弱点に気づくきっかけになり、復習すべきポイントを発見できるかもしれません。
この質問型コミュニケーションは、「はい」「いいえ」だけでは答えられない形でおこなうことが大切です。積極的におこなうことで、子どもが自分で考える癖が身につくでしょう。
小学生の子どもが勉強しないときにやってはいけない親のNG行動
ここでは、小学生の子どもが勉強しないときにやってはいけない親のNG行動について紹介します。具体的には以下のとおりです。
それぞれ具体的な声かけの内容を紹介しながら解説します。
勉強することを強制する
子どもが勉強しないからといって「テストが近いんだから勉強しなさい!」「ゲームする時間があるなら勉強しなさい!」などの声かけをすると、子どもは勉強を「やらされている」と感じてしまいます。
勉強が義務になってしまうと、勉強に対する興味や好奇心は育たない可能性が高くなります。低学年で自主的に机に向かう習慣や自制心が身についていない子どもに対しても、「勉強しなさい!」と強制するのではなく「あと10分遊んだら、一緒に漢字ドリルをやろう」などと声をかけましょう。
勉強することを強制するのではなく、子どもが自主的に取り組めるよう、促す気持ちを忘れないことが大切です。
諦めて放置する
子どもが自主的に勉強しないからといって、諦めて放置するのもNGです。学習習慣が身についていない子どもは、自主的に勉強しないことは珍しくありません。
学習習慣が身についていないうちは、親のサポートが大切です。放置された子どもは、「自分は勉強しなくていいんだ」「親から期待されていないかも…」などと感じてしまうこともあります。
子どもに対して親が無関心になると、子どもの自発性や自己肯定感が下がり、勉強への意欲を失ってしまうかもしれません。
前述したモチベーションや自尊心を高める声かけや、親ができるサポートを参考にして、子どもが自ら学ぶ力を育みましょう。
叱る・怒ることで恐怖を与えてコントロールする
子どもが勉強しないと、ついイライラして叱ったり怒ったりしたくなるかもしれません。
「何回言えばわかるの!」「勉強しないならゲーム禁止!」など、叱ることや怒ることは一時的には効果があるかもしれませんが、恐怖を与えてコントロールすると勉強が嫌いになる可能性があります。
子どもは親から怒られることが怖くて、勉強の悩みを相談できなくなることもあるでしょう。「怒られるから勉強をする」「怒られないなら勉強をしない」など、親の態度で勉強するかどうか決めるようになることも考えられます。
大切なのは、怒りでコントロールして一時的に勉強させるのではなく、自発的に勉強に向かう姿勢を育むことです。
兄弟・姉妹やほかの子どもと比べる
「お姉ちゃんはちゃんとやってたのに」「同じクラスの〇〇くんはもっといい点数をとってるよ」など、他人と比較する言葉は、子どものやる気を削ぐ可能性があります。
親は子どもの競争心を煽ろうとしていても、子どもにとっては自分の努力や能力を否定されたように感じ、自尊心が傷つけられてしまうでしょう。
学習のペースや成長の速度は個人差があるため、他人と比較するのではなく、子どもの個性に注目してあげることが大切です。
できなかったことばかりに目を向ける
「なんで〇〇分しか勉強しないの!」や「どうしてこんな簡単な問題を間違えたの!?」など、間違いや失敗ばかりを指摘してしまうと、子どもは学ぶ意欲を失う可能性があります。
たとえば、テストで80点を取ったなら、子どもは80点をとるために頑張ったはずです。「なんで20点もミスしたの?勉強しないからでしょ!」と責める言い方をすると、子どもは頑張った成果を否定されたように感じるでしょう。
反対に、「この前より10点アップしたね!」「ここは全部正解してる!すごい!」など、できた部分に目を向けてあげると、自己肯定感が生まれ「もっといい点を取りたい」「苦手な部分を克服したい」と前向きな気持ちになるかもしれません。
学習した成果がすぐに成績に反映されるとは限らないため、テストの点数だけではなく、頑張っている姿勢、頑張ろうとしている姿勢に注目して褒めてあげることも大切です。
子どもの意見に耳を傾けない
子どももひとりの人間です。幼く未熟だからといって、親が一方的に「こうしなさい」「ああしなさい」と決めつけてしまうと、子どもは自分の気持ちや考えを大切にされていないと感じてしまう可能性があります。
前述したとおり、勉強しない理由には「難しくてわからない」「学校でイヤなことがあった」「家で勉強したいけど、うるさくて集中できない」など、子どもなりの事情があるかもしれません。
「勉強しないのは怠けているからだ」などと決めつけず、子どもの言葉にしっかり耳を傾けることが大切です。子どもと信頼関係を築けると、悩みを相談してくれ、適切なサポートができるようになるでしょう。
小学生の子どもが勉強しないのは普通のこと!親がうまくサポートしてあげよう
小学生のうちは、勉強するやり方がわからないケースも少なくありません。勉強しないのには子どもなりの理由があるかもしれないため、原因を理解し、親が適切なサポートをおこないましょう。
また、小学生の子どもにとって親の存在は大きいため、適切な声かけも重要です。勉強しないことに対して叱ったり否定したりすると、自信を失ってより勉強が嫌いになる可能性もあります。
紹介した内容を参考にサポートや声かけをおこない、子どもが積極的に勉強に向かうよう自発性を育みましょう。