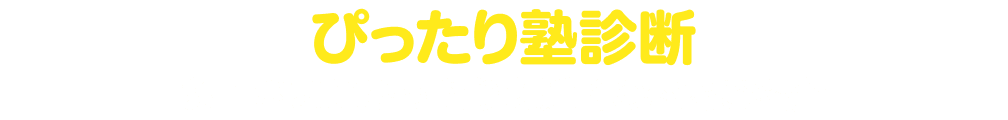塾に通わせているにも関わらず、お子さんの成績が上がらないと悩んでいる保護者の方は少なくありません。
「成績が上がらない」と塾にクレームを入れるべきか、塾をやめるべきか、迷っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、塾に通っているのに成績が上がらない理由やその対処法、成績が上がらない子どもの特徴、小学生・中学生・高校生別に最適な塾の選び方などを紹介します。
お子さんの成績に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
- 塾の成績が上がらないとクレームを入れて塾をやめるべき?
- 塾に通っても成績が上がらない9つの原因
- ①塾の授業レベルと生徒の学力レベルがあっていない
- ②家庭学習の習慣がない
- ③わからないところをそのままにしている
- ④塾の指導方法と生徒の学習スタイルが合っていない
- ⑤モチベーションや目標設定が不明確
- ⑥塾の授業だけで満足してしまい復習をしない
- ⑦基礎学力が不足したまま応用問題に取り組んでいる
- ⑧塾から出される宿題をやっていない
- ⑨自分の意思で塾に通っていない
- 塾の成績が上がらない小学生の対処法
- 塾に通う目的を明確にしよう
- 学習習慣を身につけよう
- 塾の成績が上がらない中学生の対処法
- 家庭学習を習慣づけよう
- ライフスタイルにあわせて塾に通おう
- 塾の成績が上がらない高校生の対処法
- 目的やレベルにあわせた授業選びをしよう
- 復習を徹底し積み残しがないようにしよう
- 塾の成績が上がらない原因を親子で話し合おう
- 成績だけじゃない!代表的なクレーム例を紹介
- ①塾の指導法に関するクレーム
- ②塾の学習システムに関するクレーム
- ③授業料や季節講習費など料金に関するクレーム
- ④受講生に関するクレーム
- 塾の成績が上がらないと悩んでいる方に最適な塾の選び方を紹介
- 小学生の塾選びのポイント
- 中学生の塾選びのポイント
- 高校生の塾選びのポイント
- 塾で成績が上がらないことに関するよくある質問
- 成績が上がらない子の特徴は?
- 塾に行ったら成績は上がるのか?
- 塾で成績が上がる確率は?
- 中学生で勉強できない子の特徴は?
- 塾の成績が上がらない原因を見つけて最適な環境で学習しよう
塾の成績が上がらないとクレームを入れて塾をやめるべき?
お子さんを塾に通わせているのに、思うように成績が上がらない場合、クレームを入れて塾をやめるべきなのでしょうか。結論からいうと、成績を理由に塾をやめるのは早計です。
費用がかかっているだけに、塾には一定の成果を求めがちです。しかし、塾に通いさえすれば成績が上がるわけではありません。
そして、お子さんの成績が上がらない理由が塾にあるとは限りません。まずは成績が上がらない原因を探ることが先決です。
お子さんに勉強以外の悩みはないのか、部活動で疲れていないのかなど、さり気なく聞いてみましょう。お子さんが無理をしていないか、よく観察することも大切です。
塾に通っても成績が上がらない9つの原因
塾に通っているのに成績が上がらないのには理由があります。ここでは、成績が上がらない子どもの特徴や原因について詳しく解説していきます。
お子さんに当てはまる項目がないかチェックしてみましょう。
それぞれの特徴を詳しく紹介していきます。
①塾の授業レベルと生徒の学力レベルがあっていない
特に多いのが、塾の授業レベルが高すぎる・低すぎるというケースです。
スピードが早すぎて理解が追いつかなかったり、逆に退屈すぎて身が入らなかったりすると、成績が上がりにくくなります。
例えば、授業の予習復習をしたい子どもが受験対策をメインにした進学塾へ行けば、求める内容が違うので効率的な成績アップにはつながりません。
また、子どもの性格によっても、あう・あわないがあります。熱血指導でモチベーションが高まる子どももいれば、寄り添ってくれる指導で成績が上がる子どももいます。
さらに、集団授業と個別指導どちらがあっているかも、子どもの性格によります。授業内容や雰囲気のミスマッチを防ぐために、必ず無料体験授業を受けて、相性を確認しましょう。
下記記事で塾の選び方について詳しく解説していますので、併せて参考にしてみてください
②家庭学習の習慣がない
どれだけ良い塾でも、家庭学習ゼロで成績を上げるのはかなり難しいでしょう。
週1〜2日だけ塾に行く場合、ほかの5〜6日でどんどん学習内容が抜けていってしまいます。塾で学んだことを定着させるためにも、家庭での予習・復習を徹底することが大切です。
しかし、なかには「塾(での勉強を)を頑張った」「疲れた」と言って、家で勉強しない子どももいます。
この状態のまま塾に通っても、家庭学習の習慣が身につかず、学んだことが定着しないまま先に進むため、成績が上がらなくなってしまいます。
塾の勉強だけで満足していないか、今一度チェックしてみましょう。
③わからないところをそのままにしている
わからない部分をそのままにして、どんどん内容が理解できなくなるケースも少なくありません。
特に数学(算数)や英語は、簡単な内容から積み上げていくので、前段階で理解できていないと、次の段階に進んだとき、まったくわからなくなってしまいます。
「授業中に質問しにくいな」「授業終わりは友だちとすぐ帰りたい」という子どもは、塾で質問をせず、結果として授業についていけなくなってしまいます。
理解できない授業が3回ほど続くと、理解するのを諦めてしまい、何となくわからないまま授業を受けることになります。
定期テストで成績が大きく下がって、初めて周囲の大人が理解できていないことに気付き、リカバリーにとても時間がかかるケースが多いのです。
④塾の指導方法と生徒の学習スタイルが合っていない
生徒一人ひとりには、それぞれに合った学習スタイルがあります。講師と1対1でじっくりと理解するのが得意な生徒、集団授業で学校のような気持ちで覚えるのが得意な生徒、実際に手を動かして学ぶのが得意な生徒など、タイプは様々です。
また、じっくり考えて理解したい生徒にとって、スピード重視の授業は苦痛になることもあるでしょう。
塾の指導方法が自分の学習スタイルと合っていない場合、どれだけ真面目に授業を受けても、効率的な学習ができず成績向上につながりません。
自分がどのような方法で学習すると理解しやすいかを把握し、それに合った指導を行う塾を選ぶことが重要です。
⑤モチベーションや目標設定が不明確
「なぜ勉強するのか」「何のために塾に通うのか」という目的が曖昧なまま通塾していると、学習への意欲が湧かず、成績も上がりにくくなります。
目標が「親に言われたから」「みんなが通っているから」といった受動的な理由だけでは、困難に直面したときに頑張り続けることができません。
志望校合格、定期テストで○点以上取る、苦手科目を克服するなど、具体的で自分が納得できる目標を設定することが大切です。
また、長期的な目標だけでなく、「今月は英単語を200個覚える」「次の小テストで満点を取る」といった短期的な目標も設定することで、日々の学習にメリハリがつき、モチベーションを維持しやすくなります。
⑥塾の授業だけで満足してしまい復習をしない
塾の授業を受けただけで「勉強した」と満足してしまい、復習をしない生徒は成績が上がりにくい傾向にあります。人間の記憶は、学習した直後から急速に忘れていくため、復習なしでは知識が定着しません。
エビングハウスの忘却曲線によると、学習した内容は1日後には約70%忘れてしまうと言われています。
塾で理解できたと思っても、復習しなければ次の授業までにほとんど忘れてしまい、結果として同じ内容を何度も学習することになります。
効果的な学習のためには、塾の授業後24時間以内に復習し、さらに1週間後、1ヶ月後と定期的に復習することが必要です。
塾の授業はあくまでも理解のきっかけであり、本当の学力定着は復習によって実現されることを認識しましょう。
⑦基礎学力が不足したまま応用問題に取り組んでいる
基礎がしっかりと身についていない状態で応用問題に取り組んでも、理解が進まず成績向上にはつながりません。
特に進学塾では、ある程度の基礎学力があることを前提に授業が進められることが多いです。
例えば、分数の計算が曖昧なまま方程式を学んでも、計算でつまずいてしまい本質的な理解に至りません。英語でも、基本的な文法や単語力が不足していれば、長文読解は困難を極めます。
成績が上がらない場合は、一度立ち止まって基礎に戻る勇気も必要です。恥ずかしいと思わずに、わからないところまで遡って学習し直すことが、結果的には最短距離での成績向上につながります。
塾の先生に相談して、自分の現在の学力レベルに合った指導を受けることが大切です。
⑧塾から出される宿題をやっていない
塾に通っているのに成績が上がらないお子さんは、塾から出される宿題をやっていない可能性があります。
塾によっては毎回の授業で宿題を出しますが、きちんとやらないと学んだことが定着しないだけでなく、わからないところもそのままになります。
わからないところがそのままになっていると、新しく学ぶ内容も理解できません。学んだことが身についていない状態が続くと、当然成績は下がります。
塾で出された宿題は必ずおこなうよう、保護者からも声掛けをしましょう。日々の積み重ねが成績アップにつながることをお子さんに伝え、励ますことも大切です。
⑨自分の意思で塾に通っていない
塾に通っているのに成績が上がらないお子さんは、自分の意思で塾に通っていないケースがあります。
親から「塾に行きなさい」と言われてしぶしぶ通っている場合、どうしても勉強への積極性に欠けます。
自分なりの目的を持って学んでいるわけではないので、学習も受け身になります。無理矢理塾に通わされているという不満が募ると勉強自体が嫌いになり、ますます成績を上げるのが難しくなります。
塾の成績が上がらない小学生の対処法
塾の成績が上がらない小学生は、目的意識を持つ、学習習慣を身につけるといった対策が有効です。
以下では、塾の成績が上がらない小学生の対処法を2つ紹介します。
塾に通う目的を明確にしよう
通塾するうえでとても大切なのが、子どもが納得する目的を持てているかどうかです。
目的を持たずに塾へ通っても、勉強する意味を見出せず、成績が上がりづらくなります。 そのため、理想の将来像や、現状の課題などを考えて、目的を持つことが重要です。
とはいえ、小学生のなかには勉強をしたくない子どもが一定数おり、進路について深く考えることもありません。
一方で「授業で恥をかきたくない」「学校の授業がわからず退屈」といったストレスは、多くの小学生が抱えています。こうしたネガティブな感情を、塾へ行くことで解決するというのも、立派な目的になるでしょう。
現状の課題や将来像を考えると、塾へ通うことで何が解決するか、どんな未来が実現できるかが明確になって、目的も持ちやすくなります。
学習習慣を身につけよう
小学生のうちから学習習慣を身につけておくのも、成績を上げるために効果的です。
塾での学習だけでは、成績は上がりません。習ったことを家で復習する、次の授業に向けて予習をするといった学習習慣が身について、はじめて成績アップを実感できます。
1日10分でも良いので、家庭学習を身につけていきましょう。
どうしても家で集中できない場合は、塾の自習室や図書館などを活用するのがおすすめです。家にはゲーム・テレビ・漫画など誘惑がたくさんあるので、自宅外で学習したほうが良いケースも多くあります。
学習時間や環境を工夫して、少しずつ学習習慣を身につけていきましょう
下記記事では、塾が必要ない小学生と通塾したほうがよい小学生について解説しています。子どもの塾通いに悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
塾の成績が上がらない中学生の対処法
塾の成績が上がらない中学生は、家庭学習を身につけることが重要です。また、ライフスタイルにあわせて塾のスケジュールを考えるのも重要になります。
以下では、塾の成績が上がらない中学生の対処法を解説します。
家庭学習を習慣づけよう
小学生と同様に、中学生も家庭学習の習慣をつけることが重要です。
中学生は定期テストや高校受験の対策が必要となり、学習内容も膨大になります。そのため、予習・復習をどれだけできるかが、成績に直結するのです。
まずは家に帰ってすぐ、ご飯の前などに10〜20分ほど家庭学習をすることから始めましょう。歯磨きのように毎日できるかが重要なので、時間は短くても問題ありません。
無理のない範囲で少しずつ、家庭学習をする習慣を身につけてください。
ライフスタイルにあわせて塾に通おう
ライフスタイルにあわせて塾に通うことも、成績を上げるためには重要です。中学生になると、部活や学校行事で忙しくなり、塾通いが負担になることも少なくありません。
忙しいなかで無理に塾へ通っても、疲れていて集中できない、学習内容が頭に入ってこないなどマイナスの側面が多く、結果として成績も上がりません。
気付かぬうちにストレスが溜まり、どんどん勉強嫌いになってしまう可能性もあります。土日や部活休みの日に通うなど、ほかの予定にあわせたスケジューリングをしましょう。
下記記事では、中学生が塾に行くことで得られるメリットや、自宅学習の注意点などを解説していますので、ぜひ参考にしてください。
塾の成績が上がらない高校生の対処法
高校生になったら、塾選びの方法や、復習のやり方などを工夫していくのが、成績アップのポイントになります。
次より塾の成績が上がらない高校生の対処法を紹介しますので、参考にしてください。
目的やレベルにあわせた授業選びをしよう
高校生は塾に通う目的が多様化するので、自分の目的やレベルにあわせた塾・授業選びをすることが大切です。
大学進学、就職、専門学校など、高校生は進路が分かれていきます。将来像を見据えて塾や授業を選ばないと、授業の内容やスピードがあわず、成績が上がりづらくなります。
また、自分の学力レベルや志望校にあったコース・カリキュラムで受講しないと、効果的な学習は難しく、結果として成績は上がらないでしょう。
進学予定だけど志望校は未定という方は、先に学力テストを受けたり志望校選びのアドバイスを受けたりすると、適切な塾選びがしやすくなりますよ。
復習を徹底し積み残しがないようにしよう
高校生は学習が専門的になるので、復習を徹底して学習内容を定着させることが非常に重要になります。
特に、積み上げ教科(前に学習した内容が次の単元で必要になる教科)の英語・数学は、理解できない部分を放置すると、どんどん状況が悪化します。
塾に複数科目で通っている場合は、まず英語・数学だけでも良いので、復習を徹底しましょう。
暗記系科目の国語・理系教科・地歴などは、通学時間やトイレ時間など、隙間時間を活用して復習するのがおすすめです。
下記記事では、具体例を挙げて高校生の塾の選び方について解説しています。お子さんのケースと照らし合わせてぜひ参考にしてみてください。
塾の成績が上がらない原因を親子で話し合おう
塾の成績が上がらないと悩んでいる保護者の方は、上記で紹介した成績が上がらない原因をもとに、親子で話し合いましょう。
感情的になったり叱ったりするのではなく、お子さんの気持ちを汲み取りながら話せば、お子さんの意外な本音が聞けるかもしれません。
家庭だけで対処できない場合には塾へのクレームという形ではなく、現在の状況を塾に相談するのがおすすめです。
成績だけじゃない!代表的なクレーム例を紹介
ここまで塾での成績が上がらない原因や対処法を紹介してきましたが、実際のクレームにはどんなものがあるのでしょう?
ここでは、学習塾における代表的なクレームを紹介します。
①塾の指導法に関するクレーム
授業を受けるなかで、「講師の説明がわかりにくい」「テキストの解説ばかりで演習の時間がない」「前回の授業の復習がなく、どんどん先に進む」など、塾の指導法に関するクレームが発生することがあります。
講師がおこなう説明がわかりにくい、理解しにくい場合は、その科目に苦手意識を持ってしまう可能性があります。講師の変更が可能なようなら申し出るようにしましょう。
また、演習や復習が少ないと、授業で学んだことが定着しにくくなります。自宅学習で演習の量を増やすのものひとつの手ですが、塾にも伝えて対策するようにしましょう。
②塾の学習システムに関するクレーム
集団授業をおこなう進学塾では、定期的に塾内テストを実施して、成績に準じたクラス分けをおこないます。
その結果、子どもが上のクラスではなく下のクラスに変更になった場合にクレームが発生することがあります。
塾は学力に応じたクラス分けをおこなっているため、下のクラスから上のクラスになるには、成績を上げることが先決ですが、一部の保護者からは上のクラスで受講したいとクレームになることもあります。
また、塾のなかには膨大な量の宿題を課すことがあります。学校の宿題をして、さらに塾の宿題をするとなると、夜遅くまでかかることもあり、宿題の量についてクレームを入れる保護者もいます。
入塾してから後悔しないためにも、入塾前に塾のシステムについて理解しておき、子ども自身がその塾でやっていけるかどうか、子どもの意思を確認しましょう。
③授業料や季節講習費など料金に関するクレーム
入塾前に塾から料金についての説明を受け、納得した上で入塾の申し込みをしますが、いざ塾に通いだすと、テスト・模試代や夏休みや冬休みの季節講習費と、追加で費用がかかることがあります。
とくに季節講習は通常の授業料よりも高額になる傾向があるため、講習費が高いとクレームになることがあります。
季節講習が高いと感じる場合は、必要な講座のみ受講する、または最低限必要なコマ数にするなど、予算内に収めることを意識してください。
④受講生に関するクレーム
集団授業をおこなう塾では、大人数の生徒が同じ授業を受けます。真面目に授業を受けている生徒がほとんどですが、特定の生徒が授業中にうるさいとクレームになることもあります。
また、特定の生徒がいじわるをする、勉強の邪魔をするといったクレームもあります。こういった場合は、担当講師と教室長両方に現状を伝え、対処してもらうようにしましょう。
塾の成績が上がらないと悩んでいる方に最適な塾の選び方を紹介
塾に通っているのに成績が上がらないと悩んでいる方のために、小学生・中学生・高校生別に最適な塾の選び方を紹介します。
こちらを参考にお子さんの学年にあわせた塾選びをしてください。
小学生の塾選びのポイント
小学生の塾選びでは、いつ、どのような目的を持って塾に通うかがポイントとなります。
中学校受験をする予定があるなら、中学受験のカリキュラムが始まる3年生の2月に進学塾へ通い始めるのがおすすめです。
英語を学ばせたいと考えるなら、リスニング能力が育ちやすい低学年に英語塾に通い始めるのがベストです。
学校の授業をしっかり定着させたいなら、成績が下がったタイミングで補習塾への入塾を検討しましょう。
小学生の塾選びのポイントは、以下の記事でも詳しく紹介しています。塾に通いはじめる時期についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
中学生の塾選びのポイント
中学生の塾選びでは、高校受験を視野に入れる必要があります。志望校合格を目指して進学塾に入るべきか、基礎学力をつけるために補習塾に入るべきかを、現在の学力と照らし合わせて決めましょう。
また、自習室の有無も大きなポイントとなります。中学生になると、塾の授業だけでなく自分で勉強する力も必要となります。勉強に適した環境を整えることにも重きをおきましょう。
さらに、進路相談にのってくれる講師やカウンセラーがいる塾を選ぶのもおすすめです。塾選びでは、授業以外のサポート体制にも注目してください。
以下の記事では、中学生の塾はどう選ぶかを紹介しています。事例とともに解説しているので、ぜひご覧ください。
高校生の塾選びのポイント
高校生の選びでは、どのように大学受験対策をするかが大きなポイントとなります。
個別指導塾なら、現在の学力にあわせて大学合格までのカリキュラムを組んでもらえます。苦手科目がある方や、マイペースで頑張りたい生徒におすすめです。
大学合格を目標に仲間と切磋琢磨したい方は、集団授業をおこなう進学塾や予備校がおすすめです。
また、近くに自分にあった塾がない方や、独学のほうが集中して勉強できる方は、映像/オンライン授業をおこなう塾を選びましょう。
以下の記事では、高校生の塾選びについて詳しく紹介しています。塾を選ぶ際の注意点も解説していますので、ぜひご一読ください。
塾で成績が上がらないことに関するよくある質問
塾に通っているのに成績が上がらないという悩みは多くの保護者や生徒が抱えています。
ここでは、塾と成績に関してよく寄せられる質問について、具体的な特徴や改善のポイントを交えながら解説します。
成績が上がらない子の特徴は?
成績が上がらない子には共通する特徴があります。
最も多いのは「受け身の姿勢」で学習している子です。塾の授業を聞いているだけで満足し、自分から質問したり、積極的に問題を解いたりしません。
また、「わからないことをそのままにする」傾向も見られます。恥ずかしさや面倒くささから質問を避け、理解が曖昧なまま次に進んでしまいます。
さらに、「計画性がない」ことも特徴的です。その場しのぎの勉強で、定期的な復習や予習をしないため、知識が定着しません。
これらの特徴を改善することで、成績向上の可能性は大きく高まります。
塾に行ったら成績は上がるのか?
塾に通えば必ず成績が上がるわけではありません。成績向上には、塾での学習と家庭学習の両方が必要不可欠です。
週に数回の塾だけでは、学習時間として不十分な場合が多く、重要なのは、塾をどう活用するかです。
塾で学んだ内容を家で復習し、宿題をきちんとこなし、わからない部分は積極的に質問する。このような能動的な姿勢があって初めて成績は向上します。
また、塾と生徒の相性も大切です。指導方法や授業レベルが合っていなければ、どんなに評判の良い塾でも効果は期待できません。
塾選びと学習への取り組み方、両方が揃って成績アップにつながります。
塾で成績が上がる確率は?
塾で成績が上がる確率は、一概には言えませんが、適切な塾選びと本人の努力があれば多くの生徒が何らかの成績向上を実感しています。
ただし、これは「成績が上がった」の定義や期間によって大きく変わります。
成績向上の確率を高めるポイントは3つあります。1つ目は生徒の学力レベルに合った塾を選ぶこと、2つ目は明確な目標を持って通うこと、3つ目は塾の指導に加えて家庭学習を継続することです。
中学生で勉強できない子の特徴は?
中学生で勉強ができない子の特徴として、まず「小学校の基礎が定着していない」ことが挙げられます。
分数の計算や漢字の読み書きなど、基本的な学力が不足していると、中学の学習内容についていけません。
次に「学習習慣が身についていない」ことも大きな要因です。部活や遊びを優先し、毎日の勉強時間が確保できていない生徒が多く見られますが、定期テスト前だけの詰め込み学習では、実力はつきません。
また、「勉強方法がわからない」という特徴もあります。ノートの取り方、暗記の仕方、問題集の使い方など、効率的な学習方法を知らないため、努力が成果につながりにくいといえるでしょう。
塾の成績が上がらない原因を見つけて最適な環境で学習しよう
塾に通っているのにお子さんの成績が上がらないと、塾にクレームを入れてやめることを検討する方もいることでしょう。しかし、成績が上がらない原因がわからないまま塾をやめるのはおすすめできません。
お子さんの成績が上がらない理由としては、「授業形態や講師との相性があっていない」「宿題や復習をしていない」「お子さんの意思で通っていない」「塾に行くだけで満足している」などが挙げられます。
お子さんの成績が上がらない理由を明確にし、塾のサポートを受けながら対処するのがおすすめです。
塾に通う目的や、お子さんの性格にあった塾選びも重要なポイントとなりますので、お子さんの学年や成績を考慮しながら、最適な環境で学習できるようにしましょう。